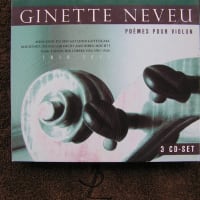「ワグナーを聴くならもっと低音が欲しいところですね~」。
これは先日の1日(金)の午後に我が家にお見えになった湯布院のAさんが「ワルキューレ」(ワグナー作曲、ショルティ指揮)を試聴しながら、独り言のように何気なく洩らされた言葉。
その時は別段気にもかけず、聞き流していたのだが、4日(月)の早朝5時ごろに目が覚めたとたんにこの言葉を思い出した。おそらく無意識のうちに我が深層心理に深く刻み込まれていたのだろう。
「ボーカルや室内楽なら今のままでも十分だけど、オペラやシンフォニーを聴くとなるとたしかにちょっと物足りないよねえ。よ~し、いっちょう、やったるか」と寝床の中で一大決心。
ガバッと跳ね起きて一目散に1階のオーディオルームへ。現在、200ヘルツ以下を受け持っているフォステクスのウーファー・ユニット「SLE-20W」(口径20センチ)「3発」を、これから「4発」にしようという魂胆である。ちなみに200ヘルツ以上の受け持ちは言わずと知れた「Axiom80」。
ここで、ちょっと話が逸れるが「ウーファー」という呼称は「ウーハー」とも称される。「ウィキペディア」によると英語で「Woofer」とあって、これは低音再生を担当するスピーカー・ユニットのことであり、名称は大型犬やオオカミ、ライオンなどの唸り声から付けられたとある。
「Woo」(ウー)は「唸り声」そのもので、「~fer」は「リーダース」によると「生み出す、含む」という意味だから、そういうことになるのだろう。
さて、このところ、オーディオ装置を”いじる”のはいつもこのパターンで、「朝飯前の仕事」になっている。とにかく一日の中で一番ヤル気が出てきて、頭と身体もフレッシュな状態だし、カミさんが勤めに出かける前に力仕事を加勢してもらわねばならないのも一つの理由。
何せ、SPボックスを降ろすのは簡単だが、逆に持ち上げるとなるととても一人では無理なのでカミさんの加勢は必須要件。非常にご親切な「お隣さん」に頼む手もあるが、70代中ごろの年齢の方なので腰でも傷められたらたいへんなことになる。
左右両方のSPボックスの裏蓋のすべてのネジの取り外しやSPコードの半田付け、ネジの取り付けなどをして4発目の「SLE-20W」をつけ終えたのが、ちょうどカミさんが早朝の散歩から戻ってくる6時半ごろ。1時間半ほどの作業時間だった。
「おい、ちょっと加勢してくれ~」「またねえ」といつものように気乗り薄ながらも手助けしてくれて無事終了。

まだ早朝だからと気兼ねしながらもこらえきれずにボリュームを上げ気味にして、すぐに「ワルキューレ」の試聴開始。
「やっぱり凄い。3発と4発では大違い」というのが実感。”ローエンド”まで伸びるというよりも、40ヘルツ当たりの充満したエネルギー感が実に心地いい。
理論上からすると、口径20センチのウーファーが3発の場合は1発のときに比べて√3≒1.7倍に、4発の場合は√4=2倍に匹敵するエネルギー増の計算になる。したがってわずかの差のようにみえるが、聴感上はそれ以上の違いがある感じ。
それと如実に思い知らされたのが最近導入したCS放送のスカパー「クラシカ・ジャパン」の音とCDの再生音との差。
「クラシカ・ジャパン」は24時間放送なので、録画、再生に忙しくてブログも書く暇がないほどの忙しさ(このブログにしても8日ぶりに登載!)だが、「衛星アンテナとちゃちなチューナー」で聴く音とCDで聴く音の違いが一番分かるのが低域の重量感だった。関連して前者は全体的に「音が薄い」印象がするのが顕著に分かってきたのもウーファー4発の効果。
現在使っているCDトランスポート(ワディア270)の価格が7桁で、チューナーは5桁だから文字通り”桁違い”なので致し方ないところだが、やはりCDの再生能力の凄さを改めて実感した。
さて、そもそもはじめから4発入りのボックスを作ったのに、なぜわざわざ途中から3発にしたのだろうかと今さら不思議だが、どうもその時のはっきりした理由が思い出せない。
おそらく、当時は比較的コンパクトな低音が欲しかったのだろうが、周辺環境の変化につれてノウハウが進化して「4発」にふさわしい状況になったのだろうとは実に手前味噌。
「しまった!先月の上旬に奈良から遠路はるばるお見えになったMさんには是非4発で聴いてもらえばよかったのに」と悔やまれるが、もう後の祭り。自分の場合、こういうケースが”しょっちゅう”ある。
何せオーディオ装置のうちの市販品はデジタル系を除いてすべて改造しているし、ほかはすべて手作りなので”いかよう”にも扱う箇所がものすごく多い。まあ、試行錯誤の連続で失敗と楽しみが同居しているようなシステムなので必然的な宿命みたいなものだろう。
関連してつい先日、我が家で試聴した高校時代の同窓のU君からメールが来て、「あるオーディオ店でマッキンとJBLの組み合わせを聴いてみたが、ただ機器を置いて鳴らしているだけという印象でとても”味わいのある音”とは思えなかった」とあったので、「オーディオは家に機器を据えつけてからがほんとうの始まり」という趣旨のことをコメントした。
高級な機器を購入してポンと置けば即座に「いい音」が出るなんて、「オーディオとはそんなに甘いものじゃないですよ」と経験上からつくづく思うのだが、あまり偉そうに言う資格もないところ。
ところで先日、近くの本屋に出かけたついでに最近のオーディオ機器の情報を関係書籍の立ち読みで収集してみた。
何せ自分が使っているスピーカーやアンプ類はすべて30年以上も前の製品ばかりなので、もしかして時代遅れではなかろうか、自分が知らないだけでもっと「好みの音」があるのではないだろうかという疑問は常に持っている。
オーディオの黄金時代の製品に対して近年の日進月歩の技術が果たしてどこまで追いついているんだろうかとの興味は尽きない。ただし、こと真空管に限っては60年以上も前の1950年代の製品に対して近年製造された真空管の性能は未だ追いついていない。まあ、しっかりしたメーカーが本気になって作れば軽く凌駕するとは思うのだが、何せ使い道がオーディオだけなので商売になるわけでもなく、本気になれるはずがない。
しかし、問題は「スピーカー」。
システムの中で音決めの最たるものなので、常にアンテナを張りつつ、「ポイントは低域の再生能力だ」と個人的に思いながらも、未だに画期的な製品は現れていないようだが今回の立ち読みでは大方の傾向が分かった。
昔はウーファーに38センチ(15インチ)口径1発とか2発使用のシステムをよく見かけていたが、近年は15センチ~20センチの口径のユニットを2発使ったものが実に多い。
どうやらこれが主流と言ってよさそうだが、これは38センチ口径のコーン紙が大きすぎて重たくなり、音声信号に対する追従性が悪くなるので、その辺をカバーするために小口径のユニットを複数使うということなんだろう。(ただし、38センチ口径以上のユニットでも「励磁型」ともなると、これは別次元の世界になる。)
以前、「Axiom80」の愛好者だった千葉のSさんの話だが「Axiom80に組み合わせるウーファーは38センチ口径で十分と言っている人がいて驚きました。これでは両者の音のスピードが合うはずがありませんよね~」で、まったく同感。
したがって自分も同じような理屈で「Axiom80」のために、あえて20センチ口径のユニットを複数使っているわけだが、しかし、2発ぐらいならいいがこれが4発の使用ともなると並列接続する場合、インピーダンスが2オーム(ユニットのインピーダンスが8オームの場合8÷4=2オーム)となるので、アンプに膨大な負荷がかかってとても無理な相談。
※ オームの法則「電圧=電流×抵抗」により、抵抗が低くなるにつれて沢山の電流が必要となってアンプの負担が重くなる。
このため市販のシステムがせいぜい2発どまりなのもよく分かるが、自分の場合ステレオアンプを左右チャンネルごとに1台使っており、SP端子のLとRにユニットを2本ずつつないで4オーム負荷にして解決している。
もう一つ、最新システムは二つのウーファーユニットの間に(ボックスの中で)仕切りを入れているのも十分頷ける。ボックス内の背圧がユニットの背後の空間内で干渉し合うのを避けているのがその理由だが、自分も4つのユニットの間をそれぞれ厚い板で仕切っている。それも定在波を防ぐために平行ではなく斜めに仕切っている。
まあ、以上によりどうやら大間違いの方向には行っていないようでまずは”ひと安心”だが、あとは信用のおけるオーディオ店で最新システムを一度試聴してみなければ・・・。