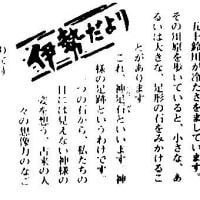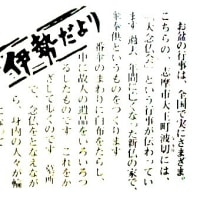伊勢の両神宮とともに、昔からお伊勢さんの名刹、金剛証寺のある朝熊山の事を少し書いておこう。
伊勢の朝熊山
朝熊山は、伊勢志摩国立公園の最高峰(朝熊ヶ岳、主峰の経ケ峰は海抜555m)で、その山上からは、鳥羽湾はもとより、東海十八州を一望におさめ、晴れ渡った日には遠く富士山までも見渡せる程雄大な眺めをもっている。
この山の名前の起こりについては、既にブログのバックナンバー(2010年5月、「伊勢の朝熊山あれこれ」参照)に記しておいたが、昭和の半ばに伊勢志摩スカイライン(有料道路)が通じてからは、信仰のみならず、観光の名所としても広く知れ渡るようになった。その陰で、この山地が地質学や岩石・鉱物、動・植物学上の、大変価値のある貴重な場所だと言う事は、あまり知られていない。
朝熊山の地質と岩石
朝熊山は、伊勢市から鳥羽市にかけて聳える東-西性の山地で、紀伊山地の東北端にあって、海抜350m~550mのほぼ定高性の尾根が続いている。地質は、中央構造線のすぐ南に位置する関係上、西南日本地質区外帯の地質構造に支配され、山地を挟む縦走断層や構造線によって地塊化し、尾根を軸とする中心部には、先新生代の蛇紋岩や橄欖岩、斑糲岩などの塩基性深成火成岩類の貫入があって、山肌や道路沿いの崖面など至る所で露頭を見る事ができる。
朝熊山の北斜面は、山麓を東西に走る活断層(朝熊ヶ岳断層と言う)の影響によって、35度以上の急斜となっているが、南方は褶曲山地を成す島路山へと続き、河谷の発達した壮年期地形を見せている。
この朝熊山の貫入岩体を挟むように、広域変成帯(三波川変成帯と言う)が広がり、山の中腹までは、主に角閃岩や緑色片岩、石英片岩などの結晶片岩と、石墨千枚岩が分布している。
朝熊山の鉱物
最近、鉱物コレクターが少しずつ増えていると聞く。特に、中国産の巨大で美しい結晶や美・貴石が頻繁に輸入され、リーズナブルな価格で取引され、市場に出回るようになった事も、その一因であろう。だが、国産鉱物となると、昭和年代まではたくさんあった大小の鉱山が全て閉山し、昔ながらの産地の消滅も著しい昨今、とても中国産の多彩な鉱物には太刀打ちが出来ない。そのような時代ではあるが、各地の鉱産地についての情報が、なぜかブログで氾濫しているように思う。新種や希産種、美晶鉱物の採れる場所などは、もっと情報を管理しなければと思いながら、朝熊山の鉱物を知ってもらう為に、少しだけ紹介する次第である。
これまでに、採取され朝熊山の鉱物種としてチェックされているものは、およそ40種である。代表的なものは、蛇紋石、異剥石、透輝石、方解石、霰石、水苦土石、含水石榴石、ソーダ珪灰石、磁鉄鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱、武石である。このうち、含水石榴石は、東京の国立科学博物館にライトブルーの標本が保管されているが、その産出場所の詳細は未だに不詳である。そして、朝熊山上にあった野間万金丹跡辺りの路面から、かつては頻繁に採集された武石と、伊勢志摩スカイライン中腹の崖面に小脈を成して産した水苦土石は、残念ながら幻の鉱物となってしまった。
山上の露頭から今でも採集できる鉱物と言えば、蛇紋石と異剥石であるが、この異剥石の巨晶は裂開面が大変きれいに輝き、全国的な希産鉱物ではないかと思われる。
朝熊山上の植物
山上広苑の自然観察遊歩道に沿って散策すると、ウバメガシが目に付き、ヤブツバキやアラカシ、ツブラジイ、シロダモ、ソヨゴ、ヤブニッケイ、ヤマモモ、ヒメユズリハ、アセビなどの常緑樹もよく目立つ。朝熊の名を冠したアサマリンドウやアサマツゲなどもあり、ジングウツツジ、ドウダンツツジ、サラサドウダンなども、花時の美しさは格別である。
植生の垂直分布の上からは、ツブラジイ、アラカシ、ヤブツバキ、サカキ、ヒサカキなどの生育する暖地性の常緑広葉樹林域である。
かつて、山頂付近にはスギの老齢林があって、林床にはアサマツゲや次に記す「朝熊(山)七草」が生育していたが、昭和半ばの伊勢湾台風の際この林は全滅してしまい、現在はと言うと、著しい自然環境の変化によってその跡地に発育したシイ、カシ類を中心とする萌芽林が成長し、常緑のブッシュ(雑木林)を呈している。林床の各所には、ウラジロやコシダなども繁茂し、蛇紋岩地帯の尾根を歩くと、クロマツの疎林が残存し、カマツカやコバノガマズミ、コバノトリネコ、メギ、ツクバネウツギ、コウヤボウキ、コガンビ、キハギ、ハイネズなどが観察される。
特に、当地の蛇紋岩地帯を代表する植物種としては、ジングウツツジ、ヒロハドウダンツツジ、アサマツゲ、シマジタムラソウ、シュンジュギク(別名、アサマギク)などが数えられる。
朝熊山七草
三重県植物誌の著者、伊藤武夫先生(故人・著名な植物学者)は、1932年発行の同書において、朝熊山に顕著な代表的植物として、次の七草を選び「朝熊山七草」として発表している。
アサマギク、テイショウソウ、スズコウジュ、アサマリンドウ、トリ
ガタハンショウヅル、ミスミソウ、チャボホトトギス
いつも思うことだが、人類社会の近代化は、歴史を通じて、家屋や食物から生活道具、調度品に至るまで、長い間自然物を利用し、自然の恩恵のもとに暮らしてきた。ある地方の史跡や観光資源の根源も、自然環境への崇拝やその活用であり、暮らしと自然界の姿(地形や地質、岩石・鉱物、動・植物、気候など)との拘りが当たり前だった時代からの遺産である。その事を念頭において、観光化された自然景観(山々や渓谷、海岸など)を真摯に見つめ直さないと、誰が政治や行政を担当しても、開発と保全の表裏をはき違え、「する事、成す事」において、今あるかけがえの無い自然資産の後世への継承を、大きく見誤ってしまうのではないか・・・。人は亡くなれば「自然の土に帰る」と、昔の人はよく言ったものだ。