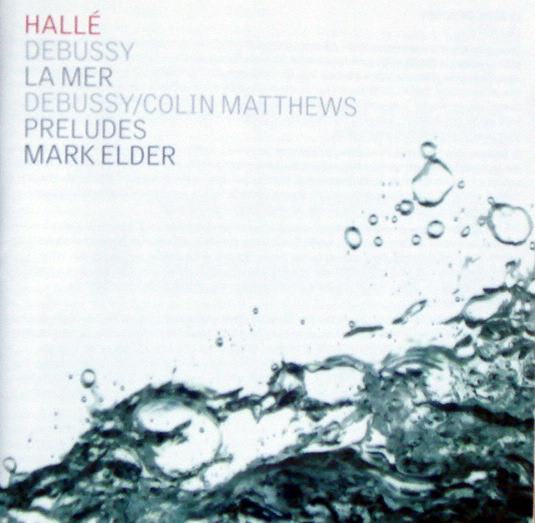カラヤン&ワイセンベルクのコンビによるベートーヴェンの「ピアノ協奏曲全集」(管弦楽/ベルリン・フィル)のレコードについてはこれまでにも「第4番」などを取り上げてきたと思う。この二人による全集録音は1974年から77年にかけ3年あまりも歳月かけ行われ写真の「第5番」のレコ-ディングが最初であった。写真のLP盤は米エンジェル盤/S-37062で1975年発売されたものだが国内盤は「東芝EMI」から当時「帝王ふたり<皇帝>中の<皇帝>」の「キャッチ・フレーズ」でリリースされたことを覚えている。
後にこの「皇帝」を加えて全集盤で発売されたが一般的評価はそれほど高くはなかったようだ。しかし筆者個人的な感想だがこれほどまでに上品で繊細な雰囲気をかもしだした「皇帝」のレコードは少ないと思っている。1977年ベルリン・フィル来日公演にもワイセンベルクはソリストとして同行、東京・普門館のb「ベートーヴェン・ツィクルス」では「第3番」とこの「皇帝」を披露した。昨年「東京FM」開局40周年を記念してこの時の「ベートーヴェン交響曲全ツィクルス・ライヴ」の録音が高音質ステレオでリリースされたことは記憶に新しいがワイセンベルクとの協奏曲ライヴ音源も存在するらしい(当時FM未放送)のでぜひCD化を望みたいところである。