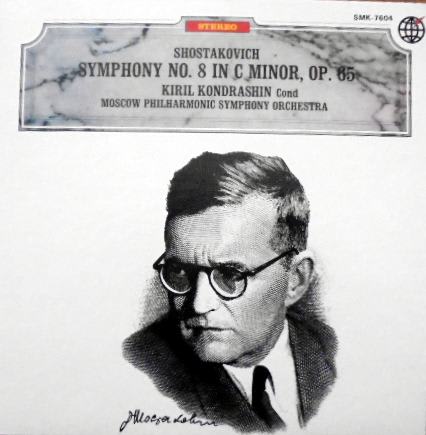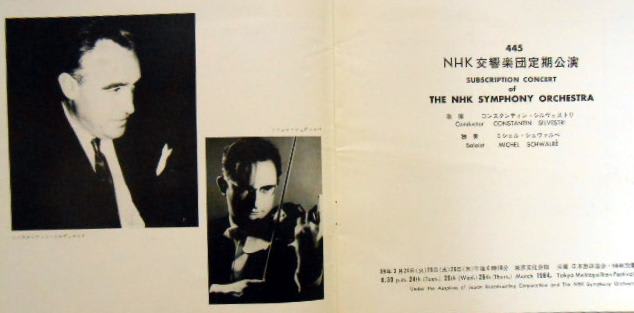レオポルト・ルートヴィッヒ(Leopold Ludwig/1908~1979)&「ハンブルク国立フィル」による「チャイコフスキー交響曲第5番」は「第6番<悲愴>」(1959年録音)と共にステレオ録音だがこの「第5番」の国内盤は数年前に「オイロディスク・ヴィンテージ・シリーズ(デンオン)」でCD化されるまで未発売だったと思う。写真のLPは「独オイロペーシェル(Europäischer)-Opera レーベル」初出モノラル盤(Nr.1185)だが音質は大変良好である。記録によれば録音は「悲愴」に続き1960年3月にハンブルクの「クルトゥアラウム」で行われている。ルートヴィッヒは「ウィーン国立歌劇場」の首席指揮者を務めるなど「オペラ指揮者」として活躍、1950年から71年までは「ハンブルク国立歌劇場」の総監督を務め人気を博したがオーケストラ作品もこのほかロンドン交響楽団との「マーラー/交響曲第9番」(1959年録音)やエミール・ギレリスとフィルハーモニア管弦楽団とのベートーヴェン「ピアノ協奏曲第4番・第5番<皇帝>」(1957年録音)等々名盤を遺している。











 (ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/1961年初来日公演プログラム)
(ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/1961年初来日公演プログラム)