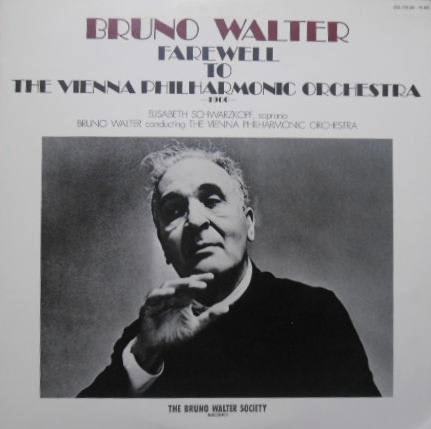先頃、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ1965年初来日時の「読売日本交響楽団」との共演ライヴが「Altusレーベル」より初CD化された。3月13日、東京文化会館におけるライヴ録音で当日のプログラム、モーツアルト「ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466」・ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番変ホ長調作品73<皇帝>」(指揮:イントリッヒ・ローハン)が収録されている。(Altus-ALT274) モノラル録音だが音質は良好でライヴ音源ファンの私は興味津々に聴き入った。彼はその後何度か来日を果たすが極度な完璧主義でコンディション不調時は度々コンサートが中止となりファンをガッカリさせた。思い返せばスケジュール通り無事コンサートをこなしたのは唯一この初来日の時だけではなかったか?当時、彼は日本に約1ヶ月余り滞在、各地で公演し4月2日・3日には「NHK交響楽団」とも共演、アレクサンダー・ルンプフの指揮でリスト「ピアノ協奏曲第1番」・ラヴェル「ピアノ協奏曲ト長調」を披露した。