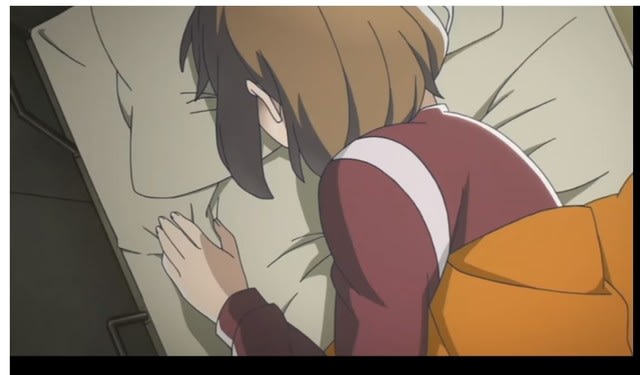なぜこのアニメにかくも惹きつけられるのか、と自問してみると、ふたつのことに思い至る。
①自分が遠い昔に失ってしまった「青春」のきらめきが、数知れぬ結晶となって散りばめられている。
恥ずかしながら……という感じだが、これは大きい。とにかくすべての描写がまぶしい。だから、逆にもし今ぼくが10代だったら、ここまで熱中しなかったかもしれぬし、悪くすると、もっと冷笑的な目で見たかもしれない。10代のワタシはかなり斜に構えてましたしねえ。
もうひとつ理由がある。これもまた、この齢になったからこそわかることではある。
②「物語」のほとんどの要素が、この一作のなかに詰め込まれている。
当ブログはもともと「純文学」と「物語」について考えるブログであって、だからこの②こそが、ここで『宇宙よりも遠い場所』を大まじめに論じている所以なのだった。
ストーリーを転がしていく大切な要素のひとつに「境界を越える」というものがある。慣れ親しんだ日常から旅立った主人公(たち)が、「ここではない何処か」(異界)へと辿り着くまえに、そのふたつの世界を隔てる「境」を越えるのだ。
もっとも見やすい例は、『千と千尋の神隠し』におけるトンネル。その源泉のひとつである『不思議の国のアリス』のウサギ穴。水平か垂直かの違いだけで、これだってトンネルだろう。ファンタジーとは限らない。純文学でも、川端康成の『雪国』では、やはりトンネルがふたつの世界の「境」となる。
ついでにいうと、川端康成ってひとは、抒情詩のような文体ゆえにあまりそう思われてはいないようだが、じつは鏡花や谷崎に劣らぬくらい物語性の強い作家だ。
『宇宙よりも遠い場所』第8話「吠えて、狂って、絶叫して」もまた、キマリたち4人が、「南極」という「異界」に辿り着くために、「境界」を越える話である。
さて。Bパート(後半)はとにかく船酔い、船酔いだ。画面自体が揺れているので、見ているこちらもかるく酩酊を味わえる。くだくだしくは書かない。画像を貼らせて頂くので、お察しください。
かなえが様子を見に来て「つらくとも、食事だけは摂ってね」というので、食堂に行って無理やり押し込むが、結局ダメ。「体力つけなきゃ」と甲板に出て「艦上体育」を試みるも、体がうごかない。
出航まえのあの穏やかな日向ぼっこの構図が反復されるのが切ない
だが、ここまではふつうの遠洋航海でも起こりうることだ。彼女たちが赴くのは「南極」なのである。
「クジラが見える」というのでキマリは信恵に望遠鏡を借りて覗くが、この体調で一点を見つめるものだから、とうぜん自爆。
そこに保奈美が4人を呼びに来て、室内の荷物をもっとしっかり固定するようアドバイスする。
今回の穏やかならざるサブタイトルは、南下して緯度が増すほどに波が荒くなっていくことから、「吠える40度、狂う50度、叫ぶ60度」と呼ばれていることに由来する。これ、ウィキペディアにもちゃんと載っていた。
地球の自転によって生まれる風や海流は、大陸によって遮られ、弱められる。しかし南極への航路にはその大陸がない。船はそこを強引に突っ切っていく。ゆえに荒波が船を直撃するわけだ。
とうぜん、揺れる。「ジェットコースターみたいよー」と、保奈美。
報瀬だけは母から聞いて知っていたようだが、ここまで口にしなかったのは、やはり自分で経験しないと実感がわかなかったせいか。
夜。いよいよ波が荒くなってくる。
歴戦の強者(つわもの)たるこの人は「嫌いじゃないですね。戦ってる気がして」と勇ましいが……。
こっちはこうなる。
かるく死んでますかね……
しっかりしているようでも、やはり年下ということだろう。結月が、「こんなんで私たち、南極行って、何かできるんでしょうか」と弱音を吐く。「私たちも、あんなふうに強くなれるんでしょうか……」
報瀬が、やや激した口調で、「がんばるしかないでしょう。ほかに選択肢はないんだから」と言い返したそのとき。
「コンパサー」が発動する。
「そうじゃないよ!」
「選択肢はずっとあったよ。でも選んだんだよ、ここを。」
「選んだんだよ、自分で!」
「人生は選択の連続。その選択には責任が伴う。そして人は、その絶えざる積み重ねによって自己を形成していく」とは実存主義の極意だ。キマリはサルトルなんて知らぬだろうけど、立派な実存主義者である。さすがは「表の主人公」。
日向が「よく言った!」といって飛び起き、サントラのDisc 2、6番目に入っている「最後まで諦めない」という勇壮な曲が掛かる。そのまま廊下に出ていこうとする日向に、結月が「どこ行くんです?」と訊き、日向が口を抑えて「トイレ……」と答え、曲が途中でストップする、というギャグを挟んで……。
結局は4人でトイレのために廊下に出る。ほとんど「坂」と化した床の上でこんなことになったりして、わちゃわちゃしたあげく……。
キマリが、「この旅が終ったときには、ぜったいこれも、すっごく楽しいって思ってる!」と笑顔で言い切って、ほかの3人も微笑を浮かべ、全員で、目と目を見かわす。「ONE STEP」という挿入歌がかかる。「ハルカトオク」「宇宙を見上げて」の2曲はこれまでクライマックスシーンで必ずどちらかが使われたが、「ONE STEP」はこの時が初めてだ。
ここからの展開は、初見のさい、ぼくにはまったく予想できなかった。自分が保守的なつまらぬ人間だなあとつくづく思う。結月が「ちょっと、外行ってみたいですね」と言い出すのである。3話で、ハシゴをかけて上ってくるキマリたちに「何やってるんです、怒られますよ!」と声をかけた結月が(夢のなかの出来事だったけど)これをいうのは誠に意義深いのだが、それにしても、だ。
扉を開けて……。
初見の際には、思わず「あああああーっ」と声が出たものだ。
これについては、『20 「暗喩」の豊かさ、あるいは、「現実」と「物語」とのあいだ』のコメント欄に詳しい考察を頂いたので、ぜひ参考にされたい。『宇宙よりも遠い場所』に対する批判的な意見のなかには、このシーンを取り上げるものも多いので、リアリズムの見地に立ったこのような擁護は貴重なものである。
この考察によれば、ようするに「このシーン、見た目ほどは危なくない」らしい。そうなのかもしれない。ただ、いずれにしても、スタッフがここの場面を「見るからに危ない」ものとして見せているのは確かだ。「物語論」の立場からは、その点こそが重要になる。
「境界を越える」というのは、並大抵の行いではないのである。命がけなのだ。「アリス」にしても、わりとあっさり越えちゃってるけど、ほんとはそこで命を落としてもフシギじゃないくらいのことなのである。「千と千尋」のばあい、トンネルを越えた時よりも、ちょっと後になって大変な事態を招いたが、いずれにしても只では済まない行為なのだ。
このアニメはそこをきっちりやっている。しかも「4人だからこそ乗り越えられる」という点をユーモアまじりに強調しており、「物語」として間然する所がない。
キマリたちは頭から水しぶきを浴びる。舐めてみると、しょっぱい。海水なのだ。これも、「海上にいることを身をもって知る」というリアリスティックな意味のほかに、「洗礼を受ける」という象徴的な意味がある。「境界越え」に付随する儀礼だ。
だからこのシーンの後は、彼女たちはもう、別の場所に立つことになる。相変わらず船の上にはいるのだが、そこはもう、これまでと同じ場所ではないのだ。
次のシーン、爽やかな顔で食堂の弓子の前に立つ4人。やっと、船に「乗れる」ようになったみたいね、と弓子。「自転車に乗る」のと同じで、たんに船に乗っかってるんじゃなくて、船を自分の身体が乗りこなしている、という感じであろうか。
日向が、「はい。昨日クジラも見ましたから」と答える。この返事からも、これが先ほどのシーンの翌日ではなく、何日かが経過した後だとわかる。
そして、
ついに南極圏が目の前に
キマリのナレーションで。
「雲もなく、鳥の姿もなく、視界すべてが、一面の青。
どんなに目を凝らしても、見渡すかぎりの水平線。
たしかに船の音は 聞こえているはずなのに、
その圧倒的な景色が、音を消していた。
そこにあるのは、宇宙を思わせる、無音の世界。」
(立派な文章である。ああみえて、キマリにはけっこう文才がある……と思う。)
出航直後の4人のあの表情が反復されて、
第8話「吠えて、狂って、絶叫して」はおわる。