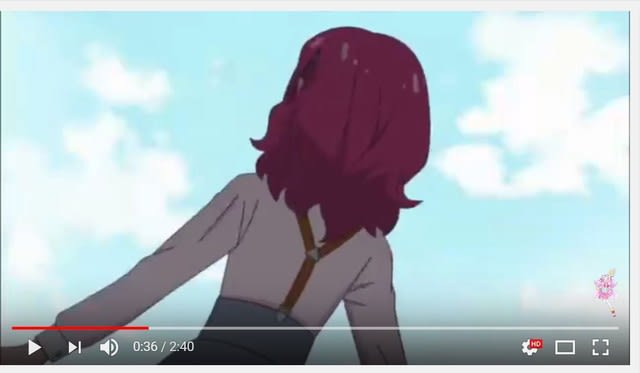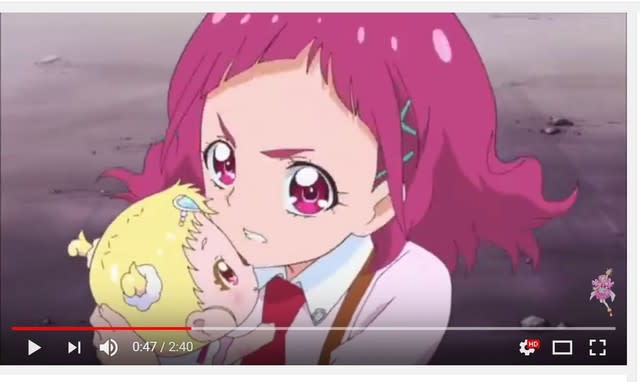ぼくがこれまで1年を通して第1話から最終話までみたシリーズは、前回ふれた『GO! プリンセスプリキュア』(2015年)だけだ。何となく途中からまったく見なくなった年もあれば、気が向いたときだけ飛び飛びに見ていた年もある。そもそもプリキュアという番組をまるっきり失念していた時期もある。それはまあ、そんなものだろう。
だから過去シリーズと比較するにしても、自信をもって対象にできるのは「GOプリ」だけで、あとはオボロげな記憶をネット情報で補足しながら、ってことになるんだけれど、たぶん今作のもっとも大きな特徴は、主役の野乃はなをはじめ、5人のプリキュアたちの未熟さが目立つ、という点にあるように思う。
未熟というか、もっと強く、「内面に欠落を抱えている」というべきかもしれない。もっとシンプルに、「さびしさ」といったほうがいいか。
プリキュアチームの中心となる子は、初代の「キュアブラック」を除けばほぼ全員が「ピンク」をイメージカラーにしているので、「桃キュア」と称されているらしいのだが、その歴代の桃キュアのなかで、たぶん野乃はなは群を抜いて子供っぽく、もろい。
歴代の桃キュアたちは、「まじめな優等生」と「さほど取り柄のない凡庸な子」との2タイプに分かれる(後者には、「スポーツは得意だが勉強はいまいち」というパターンも含む)。
ただ、「取り柄のない凡庸な子」であっても、じつは芯には「強靭な意志」と「求心力(リーダーシップとは少し違う)」を持っている。そうでなければ、時には年長者も混じる混成チームのセンターにはなれない。
野乃はなはもちろん「凡庸」のほうだが、「強靭な意志」と「求心力」はどうか。むろん、ヒーローとして闘い続けてる以上、その意志の強さは疑いもないが、それはあくまで「キュアエール」としての顔であり、ひとりの中2女子としての「野乃はな」自身はまた別だ。
たとえば、「次のテストで平均点を10点上げる」とかなんとか、目に見えるかたちで目標を設定して努力している様子ってものは、見るかぎりまったく伺えない。この点は、学業、スポーツはもとよりバレエ、バイオリン、礼儀作法など「プリンセス」にふさわしい技能を修得すべく日々研鑽を怠らなかった「GOプリ」の春野はるかの対極にある。

「求心力」はどうだろう。春野はるかのばあい、その人柄もさることながら、常人ばなれした努力と、費やした努力の分だけめきめきと向上する潜在力の高さによっても仲間たちを惹きつけていた。だから見ているこちらにも、彼女に寄せる仲間の信頼が納得できた。
野乃はなにはそれはない。いや、キュアエールに変身したときは強いし、頼りがいのあるカッコいいヒーローなのだ。しかし野乃はな自身はちがう。彼女の「求心力」の依って来るゆえんをひとことでいうのはむずかしい。
①元気さと素直さと愛嬌のよさ。
②相手の長所をすばやく見抜いてそれを全肯定してあげる優しさ。
③自分がおかしいと感じたことに本気で怒る正義感。
といったところか。
たしかにこれらは魅力になりうるだろうけど、子どもっぽいといえば子どもっぽくて、危うさと裏腹でもある。じっさい、元気さと素直さと愛嬌だけでは社会は回って行かないし、相手をひたすら肯定してるだけでは必ずしも相手の成長に寄与しない。ただ甘やかしてるだけってことにもなりかねない。そして、「自分がおかしいと感じたこと」が、ぜったいにおかしいことである保証もない。向こうには向こうの事情がある。少なくとも、あるていどは向こうの事情だって汲んでやらねばならない。それが大人の社会だ。
それが現実ってもののややこしさで、ただヒーローとして、襲来してくる敵を撃退してればいいのとは違う。
つまりキュアエールとしての闘いは、もとより苛酷なものに違いないにせよ、明快といえば明快ではある。野乃はなが所属している社会ってやつはもっと複雑で、はな自身はまだ、それにあんまりうまく適応できてはいない。
カッコいいヒーローとしてのキュアエールと、不器用で幼い野乃はなとの懸隔。もっといえば乖離。このことは、はっきりと作品のなかで前景化されつつある。
26話の冒頭でも、「さあやは女優、ほまれはスケート、えみるはギター、ルールーはアンドロイド。みんなは何かを持っているのに、私には何もない。」などと、冗談めかした口調ながら、際どいことを述べていた。みずから進んで虎の尾を踏みにいくような発言である。さいわい、今回は久しぶりの「さあや回」であったため、話題はすぐに変わったけれど。
いずれにしても「野乃はな」は、当初から幼かったうえに、全49話ないし50話の折り返し地点をすぎても、さほど成長した様子がみえない。はじめに「未熟」と呼んだゆえんだけれど、しかしおそらく、それこそまさに、ぼくが野乃はなに肩入れしちまう理由なのだ。
ああいうもんじゃなかろうか。
そりゃ世間には幼少期から優秀なひともいっぱいいるとは思うけど、やっぱり大多数の者は、中学時代からそんなに明確な目標をもってはいないし、ものすごい努力をしてるってわけでもないだろう。
ぼく自身、中2の頃を思い返せば、夢もなく、将来への展望もなく、努力もせず、あまり周囲にも馴染めぬまま、右往左往するばかりであった。恥ずかしながら、3年間かけて卒業までにめざましく成長した実感もない。
だから、作品の中のキャラクターとして、春野はるかは尊敬するが、その名のとおり遥か遠くにみえる。いっぽう野乃はなには、すぐそこにいるかような共感をいだく。そういうことだ。
はなとは別のかたちにせよ、ほかのプリキュアの面々も何かしら欠落をかかえている。
今回ようやく2回目の「当番回」(プリキュアになった02話を含めれば3回目)をもらった薬師寺さあやは、気が回りすぎ、細やかすぎるがゆえに、周囲が求める「さあや像」を察知し、それに自身を合わせようとして、自分のありかを見出せなかった。
輝木ほまれは、容姿に恵まれ、スケートという特技をもち、大人びていて、生来のスター性を備えているゆえに、いざ銀盤を離れてふつうの中学生に戻ると、集団に溶け込みきれない傾向があった。
愛崎えみる(CV 田村奈央)は、はなの妹と同じクラスの小6だが、一風(どころではないか?)変わった家庭で育ったゆえに、いろいろ過剰なところがあって、同世代のクラスメイトと円滑なコミュニケーションがとれなかった。

ルールー・アムール(CV 田村ゆかり)は、なにしろ17話まで敵陣営にいたアンドロイド(!)なので、感情生活においてはまだまだ幼く、IQはずば抜けてはいても、精神年齢においてはえみるとさほど変わらない(それもあってえみるともっとも親しい)。

このようなメンバーだからこそ、上で述べた、はなの子どもっぽい、どこか危うい特性が、とりわけ②の「相手の長所を見抜いて全肯定する優しさ」が生きたのである。とりあえず「あなたはそれでいい。なにひとつ卑下することはない。とにかく私はあなたのそばにいて、あなたのことを応援する。」というメッセージを送る。それは彼女の母すみれがこれまで折にふれて何度となく繰り返し伝えてくれたことだ。
出会ったとき、はなはまずそのメッセージを発した。そして、それがどうにか相手の心に届いたところで、ようやくそれぞれとの交流がはじまったのだ。
すでに述べたとおり、それは必ずしも相手の成長に寄与するとは限らない。とくに年少のえみるや、かつて敵として悪事に手を染めたルールーに対しては、ほかにもっと然るべき対処があったかもしれない。
しかし、それは大人の理屈というものだろう。とりあえずは自分の傍まで、こちらの言葉が届く場所まで相手が近づいてくれないことには、話すことすらできぬではないか。そのために、はなは、今の自分にできることをやった。むろん「アホの子」だから計算づくじゃない。本能だ。
そして4人はおのおのの仕方で彼女を受け容れた。
それくらい、はな自身をも含め、彼女らの「さびしさ」が大きいものだった、ということでもあろう。
絵柄は明るく華やかで、ギャグもたっぷりまぶしてあるからつい見過ごしてしまいそうになるが、この作品に描かれた彼女たちの「未熟さ」はひどく切実で、やっぱりぼくには、ひどくリアルなものに思える。