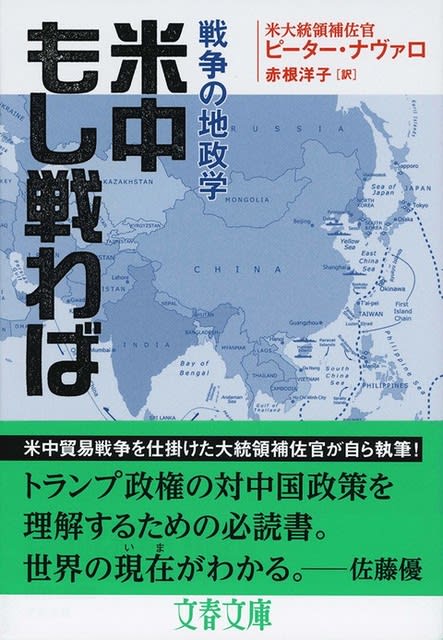元はといえば「なんで純文学はこんなに読まれないんだろう😢」という切実なギモンを抱いて、大塚英志さんはじめ「物語」にかんする論考を読んだり、エンタメ小説を読みはじめたところ、これがむやみに面白くて、どんどん深入りしていった。それも、ケン・フォレットあたりに夢中になってるうちはまだよかったんだけど、
「いや、現代における真の《物語》とはエンタメ小説でもなればラノベでもない。つまり活字媒体ではない。むしろマンガやアニメこそが、現代社会の物語と……否、《神話》と呼ぶべきだ!」
なんて逆上せあがってしまったもんで、気がつけばアニメ関連のカテゴリのほうが多くなり、ネット上から拝借した画像を貼りまくったりして、すっかりカラフルでポップなブログになってしまった。
それはそれでまあ、かまわないんだけど、ふと我に返ってみると、「あれれ……?」という気分もある。
たしかに今や自分の中の「純文学信仰」はかなり薄れてしまったが、むろん、「純文学など無用」「純文芸誌は出版社にとっての不良債権」「芥川賞なんて文芸春秋社のための単なるイベント。やめちまえ」とまで考えているわけではない。良質の純文学は、いつの時代にも、どんな社会にも必要だ……と思ってはいるが、とりわけ若い世代に幅広く純文学が読まれるような世の中は、よほどのことがないかぎり、もう二度とこない気がする。
それでも、『火花』が芥川賞をもらえばベストセラーにはなる。ただのミーハー気分(死語?)もあろうが、「純文学ってなんかムツカシそうだけど、どんなんだろう? この機会にちょっと見てみたいな」という知的好奇心も少しは与っているはずだ。
アマゾンを見ると、『火花』の文春文庫版には現時点において1500件弱のレビューが付いていたが、ふだん純文学を、というかおそらく小説自体をあまり読まないそんな若い人たちの赤裸々な意見がみられる。
「くだらなすぎて呆れた。小説というものは、もっときちんと勉強をした、高い品性の持ち主が書くべきだ。」
などという率直な感想もあって、おもしろい。じゃあ町田康や村上龍の受賞作はどうなるんだろう……とも思うが、これはもう、ノースロップ・フライというカナダの優秀な文芸批評家が述べているとおり、「時代が進めば進むほど、小説の主人公はますます卑小になっていく。」のだから、しょうがない。
小市民的になるのだ。それこそ「物語≒英雄譚≒神話」から遠ざかっていくわけである。
もし仮に、自分の身近にまじめで優秀な高校生がいて、
「ちゃんとした文学ってものを読みたいんだけど、何がいいですか」
と訊かれたら、
『三四郎』夏目漱石 新潮文庫ほか
『若き日の詩人たちの肖像』堀田善衞 集英社文庫
『迷路』野上弥生子 岩波文庫
『野火』大岡昇平 新潮文庫
『黒い雨』井伏鱒二 新潮文庫
『豊饒の海』三島由紀夫 新潮文庫
『流れる』幸田文 新潮文庫
『芽むしり 仔撃ち』大江健三郎 新潮文庫
あたりを挙げるだろう。社会や歴史の実相を学ぶ上での勉強になる、ということもあるけれど、これらの作品には、登場人物の「内面」「省察」「思想」がしっかり叙されているからだ。
W村上よりも上の世代ばかりだが、やはり龍さんが華々しくデビューした1970年代半ば(昭和だとちょうど50年代)から、ニホンにおいては「小説の主人公がますます卑小になっていく」勢いが加速し、主人公たちからは内面や省察や思想がなくなって、薄っぺらになった。
『限りなく透明に近いブルー』のリュウなんて、卑小どころか犯罪者である。麻薬及び向精神薬取締法違反。あと暴行罪も成立するか。
ついでだから書いておくけれど、あの中にはヘロイン、モルヒネをはじめ「総ざらえ」といいたいくらいに各種の麻薬が出てくるが、違法薬物は、どんなことがあろうと絶対、絶対、やってはいけない。いけません。
「いや、現代における真の《物語》とはエンタメ小説でもなればラノベでもない。つまり活字媒体ではない。むしろマンガやアニメこそが、現代社会の物語と……否、《神話》と呼ぶべきだ!」
なんて逆上せあがってしまったもんで、気がつけばアニメ関連のカテゴリのほうが多くなり、ネット上から拝借した画像を貼りまくったりして、すっかりカラフルでポップなブログになってしまった。
それはそれでまあ、かまわないんだけど、ふと我に返ってみると、「あれれ……?」という気分もある。
たしかに今や自分の中の「純文学信仰」はかなり薄れてしまったが、むろん、「純文学など無用」「純文芸誌は出版社にとっての不良債権」「芥川賞なんて文芸春秋社のための単なるイベント。やめちまえ」とまで考えているわけではない。良質の純文学は、いつの時代にも、どんな社会にも必要だ……と思ってはいるが、とりわけ若い世代に幅広く純文学が読まれるような世の中は、よほどのことがないかぎり、もう二度とこない気がする。
それでも、『火花』が芥川賞をもらえばベストセラーにはなる。ただのミーハー気分(死語?)もあろうが、「純文学ってなんかムツカシそうだけど、どんなんだろう? この機会にちょっと見てみたいな」という知的好奇心も少しは与っているはずだ。
アマゾンを見ると、『火花』の文春文庫版には現時点において1500件弱のレビューが付いていたが、ふだん純文学を、というかおそらく小説自体をあまり読まないそんな若い人たちの赤裸々な意見がみられる。
「くだらなすぎて呆れた。小説というものは、もっときちんと勉強をした、高い品性の持ち主が書くべきだ。」
などという率直な感想もあって、おもしろい。じゃあ町田康や村上龍の受賞作はどうなるんだろう……とも思うが、これはもう、ノースロップ・フライというカナダの優秀な文芸批評家が述べているとおり、「時代が進めば進むほど、小説の主人公はますます卑小になっていく。」のだから、しょうがない。
小市民的になるのだ。それこそ「物語≒英雄譚≒神話」から遠ざかっていくわけである。
もし仮に、自分の身近にまじめで優秀な高校生がいて、
「ちゃんとした文学ってものを読みたいんだけど、何がいいですか」
と訊かれたら、
『三四郎』夏目漱石 新潮文庫ほか
『若き日の詩人たちの肖像』堀田善衞 集英社文庫
『迷路』野上弥生子 岩波文庫
『野火』大岡昇平 新潮文庫
『黒い雨』井伏鱒二 新潮文庫
『豊饒の海』三島由紀夫 新潮文庫
『流れる』幸田文 新潮文庫
『芽むしり 仔撃ち』大江健三郎 新潮文庫
あたりを挙げるだろう。社会や歴史の実相を学ぶ上での勉強になる、ということもあるけれど、これらの作品には、登場人物の「内面」「省察」「思想」がしっかり叙されているからだ。
W村上よりも上の世代ばかりだが、やはり龍さんが華々しくデビューした1970年代半ば(昭和だとちょうど50年代)から、ニホンにおいては「小説の主人公がますます卑小になっていく」勢いが加速し、主人公たちからは内面や省察や思想がなくなって、薄っぺらになった。
『限りなく透明に近いブルー』のリュウなんて、卑小どころか犯罪者である。麻薬及び向精神薬取締法違反。あと暴行罪も成立するか。
ついでだから書いておくけれど、あの中にはヘロイン、モルヒネをはじめ「総ざらえ」といいたいくらいに各種の麻薬が出てくるが、違法薬物は、どんなことがあろうと絶対、絶対、やってはいけない。いけません。
文学史には「薬物系」という流れがあり、20世紀にはバロウズという怪物的な人も出たけれど、それはそれ、これはこれで、「虚構」と「現実」とは厳正に弁別されねばならない。
あと、村上龍という作家はその後、起業家などとの交流を広げ、作品をどんどん分厚く、大きくしていったわけだけど、それもまた別の話だ。
話を戻そう。「小説の主人公がますます卑小になっていく」ことは、社会学のレベルでいえば、「モダン(近代)の終焉」「知識人の解体」と軌を一にしている。
「目指すべき理想の社会(未来)」とか、それに伴う「目指すべき理想の人格」ってものが霧消してしまった、なくなっちゃった、ということだ。
だから「内面」もなければ「省察」も「思想」もない。必要ない。むしろ邪魔かもしれない。
いまは「なんでもいいからカネをいっぱい儲けた奴が勝ち」という社会で、それはまあ、世の中なんていつの時代でも、どこの地域でも蓋を開けてみりゃそうなんだけど、ただ、それでも昔はどこかに遠慮というか恥じらいがあって、ここまで露骨に、傍若無人にオモテに出すことは慎んだもんである。
マイケル・ルイスの『世紀の空売り』(映画『マネー・ショート』の原作。文春文庫)は面白くてタメになる一冊で、ほんとうに優秀な高校生ならば、上に挙げた「純文学」より先にこちらを読むべきなのかもしれないが、この解説を藤沢数希さんが書いている。
文庫版が出たのは2013年で、「解説者略歴」には、「ツイッターのフォロワー7万人超」とある。
その続編の『ブーメラン 欧州から恐慌が返ってくる』も14年に文庫になっており、そこでの解説者略歴だと、「ツイッターのフォロワーは9万人」である。
いま2019年現在、フォロワーは16万人半ばである。ツイッターのことはよく知らぬが、テレビにしょっちゅう顔を出すタレントでもないのにこの数は、かなり多いほうだろう。
なぜそんなに読まれてるかは、じっさいにツイッターをみれば瞭然だ。
5月25日時点だと、こんな具合である(時系列順に編集)。
みんなが思い描くキラキラのホワイトカラーって、有名大学の平均的な学生の卒論ぐらいのワークを会食とかがポンポン入ったりする環境で、毎週涼しい顔してやってくぐらいの情報処理量とアウトプットなんよ。マジで。こんな仕事みんなが目指すべきものなんかな、という気がする。
年収が高いキラキラのホワイトカラーって、まあ、有名大学の平均的な学生の2倍とか3倍ではなく、10倍オーダーの知的生産性で、はじめて平社員みたいな感じなんよね。これが。
日本でも有名大学のトップ1%ぐらいの学生の知的生産性は、同じ大学の平均的な学生の知的生産性の20~30倍ぐらいはあるな。
それで、なぜこうなってるかというと、何か意味のあるアウトプットをすることを、たとえばボールを壁の向こうに投げるゲームに例えると、その壁の高さがちょうどトップ1%ぐらいの人が必死で投げるとたまに超えるぐらいになってるんよ。平均的な人だと1000回投げても1つも壁を超えないのよ。
僕がサラリーマン時代に嫌だったことのひとつは複数の仕事を同時にやらないといけないことだった。研究者気質だったんでひとつの仕事に集中して片付けて次に行くほうが効率いいだろう、とずっと思っていた。しかし自営業になって誰からも指図されなくなってからも常に2つ3つの仕事を同時にやってる。
世界は自分を中心に回っていないので仕事は自分が一つずつ集中できるようにタイミングを合わせてやってきてくれない。で、サラリーマン時代に培った、マルチタスクでも質を落とさずやっていくスキルは、大変に役に立っている。
最近は親も学校の先生も会社の上司も厳しいことを言わなくなった。結果、多くの若者は、何も言われないまま、次の声がかからない、という穏当な方法でビジネス社会から見限られ、底辺に落ちていき、そこで暮らしていくことになる。
おもしろい。
これは藤沢さんではなく、「藤沢さんのようなタイプの人たち」として、あくまでも一般論としていうのだが、このような方々は端的にいって「成功者」であり、いまを存分に謳歌している。もし仮に安倍内閣がとんでもない失政をして、日本の国益を損なったとする。おおかたの大衆はまるで気づかず、一部の聡い人たちだけが気づく。もちろん「成功者」たちは「聡い人たち」でもあるから即座に気づく。
ただ、こういう方々は気がつきはしても批判などしない。するはずもない。批判などしても一文の得にもならず、むしろ損になるからだが、もっと大きな理由がある。
それは「ビジネスチャンス」に他ならないからだ。日本の国益が損なわれるということは、そのぶん誰かが儲けるということである。であれば、何食わぬ顔でその「儲ける人たち」の中に加わればよい。それで今回のゲームの勝者になれる。
それでこの国の将来がめちゃくちゃになったら? もちろん、そんなことは構いやしない。潤沢な資金を蓄えて、海外の住みよい国へ移住すればいいだけのことだ。
念のため繰り返すが、これは特定の方をさして述べているのではなく、いまどきの「成功者」たちの心性ってものを、ぼくが勝手に邪推して書いてるだけなので誤解なきよう。
『世紀の空売り』『ブーメラン 欧州から恐慌が返ってくる』を読んでから、藤沢さんの一連のツイッターを拝見してたら、そんな妄想というか、邪念のようなものが黒雲のごとく脳裏にわきあがってきた。失礼の段はご容赦ください。
ただ、ひとつだけかなりの確実性をもっていえるのは、藤沢さんも、その16万人超のフォロワーの方々も、きっと『若き日の詩人たちの肖像』も『迷路』も『野火』も読んでおられぬだろうな、ということだ。
話を戻そう。「小説の主人公がますます卑小になっていく」ことは、社会学のレベルでいえば、「モダン(近代)の終焉」「知識人の解体」と軌を一にしている。
「目指すべき理想の社会(未来)」とか、それに伴う「目指すべき理想の人格」ってものが霧消してしまった、なくなっちゃった、ということだ。
だから「内面」もなければ「省察」も「思想」もない。必要ない。むしろ邪魔かもしれない。
いまは「なんでもいいからカネをいっぱい儲けた奴が勝ち」という社会で、それはまあ、世の中なんていつの時代でも、どこの地域でも蓋を開けてみりゃそうなんだけど、ただ、それでも昔はどこかに遠慮というか恥じらいがあって、ここまで露骨に、傍若無人にオモテに出すことは慎んだもんである。
マイケル・ルイスの『世紀の空売り』(映画『マネー・ショート』の原作。文春文庫)は面白くてタメになる一冊で、ほんとうに優秀な高校生ならば、上に挙げた「純文学」より先にこちらを読むべきなのかもしれないが、この解説を藤沢数希さんが書いている。
文庫版が出たのは2013年で、「解説者略歴」には、「ツイッターのフォロワー7万人超」とある。
その続編の『ブーメラン 欧州から恐慌が返ってくる』も14年に文庫になっており、そこでの解説者略歴だと、「ツイッターのフォロワーは9万人」である。
いま2019年現在、フォロワーは16万人半ばである。ツイッターのことはよく知らぬが、テレビにしょっちゅう顔を出すタレントでもないのにこの数は、かなり多いほうだろう。
なぜそんなに読まれてるかは、じっさいにツイッターをみれば瞭然だ。
5月25日時点だと、こんな具合である(時系列順に編集)。
みんなが思い描くキラキラのホワイトカラーって、有名大学の平均的な学生の卒論ぐらいのワークを会食とかがポンポン入ったりする環境で、毎週涼しい顔してやってくぐらいの情報処理量とアウトプットなんよ。マジで。こんな仕事みんなが目指すべきものなんかな、という気がする。
年収が高いキラキラのホワイトカラーって、まあ、有名大学の平均的な学生の2倍とか3倍ではなく、10倍オーダーの知的生産性で、はじめて平社員みたいな感じなんよね。これが。
日本でも有名大学のトップ1%ぐらいの学生の知的生産性は、同じ大学の平均的な学生の知的生産性の20~30倍ぐらいはあるな。
それで、なぜこうなってるかというと、何か意味のあるアウトプットをすることを、たとえばボールを壁の向こうに投げるゲームに例えると、その壁の高さがちょうどトップ1%ぐらいの人が必死で投げるとたまに超えるぐらいになってるんよ。平均的な人だと1000回投げても1つも壁を超えないのよ。
僕がサラリーマン時代に嫌だったことのひとつは複数の仕事を同時にやらないといけないことだった。研究者気質だったんでひとつの仕事に集中して片付けて次に行くほうが効率いいだろう、とずっと思っていた。しかし自営業になって誰からも指図されなくなってからも常に2つ3つの仕事を同時にやってる。
世界は自分を中心に回っていないので仕事は自分が一つずつ集中できるようにタイミングを合わせてやってきてくれない。で、サラリーマン時代に培った、マルチタスクでも質を落とさずやっていくスキルは、大変に役に立っている。
最近は親も学校の先生も会社の上司も厳しいことを言わなくなった。結果、多くの若者は、何も言われないまま、次の声がかからない、という穏当な方法でビジネス社会から見限られ、底辺に落ちていき、そこで暮らしていくことになる。
おもしろい。
これは藤沢さんではなく、「藤沢さんのようなタイプの人たち」として、あくまでも一般論としていうのだが、このような方々は端的にいって「成功者」であり、いまを存分に謳歌している。もし仮に安倍内閣がとんでもない失政をして、日本の国益を損なったとする。おおかたの大衆はまるで気づかず、一部の聡い人たちだけが気づく。もちろん「成功者」たちは「聡い人たち」でもあるから即座に気づく。
ただ、こういう方々は気がつきはしても批判などしない。するはずもない。批判などしても一文の得にもならず、むしろ損になるからだが、もっと大きな理由がある。
それは「ビジネスチャンス」に他ならないからだ。日本の国益が損なわれるということは、そのぶん誰かが儲けるということである。であれば、何食わぬ顔でその「儲ける人たち」の中に加わればよい。それで今回のゲームの勝者になれる。
それでこの国の将来がめちゃくちゃになったら? もちろん、そんなことは構いやしない。潤沢な資金を蓄えて、海外の住みよい国へ移住すればいいだけのことだ。
念のため繰り返すが、これは特定の方をさして述べているのではなく、いまどきの「成功者」たちの心性ってものを、ぼくが勝手に邪推して書いてるだけなので誤解なきよう。
『世紀の空売り』『ブーメラン 欧州から恐慌が返ってくる』を読んでから、藤沢さんの一連のツイッターを拝見してたら、そんな妄想というか、邪念のようなものが黒雲のごとく脳裏にわきあがってきた。失礼の段はご容赦ください。
ただ、ひとつだけかなりの確実性をもっていえるのは、藤沢さんも、その16万人超のフォロワーの方々も、きっと『若き日の詩人たちの肖像』も『迷路』も『野火』も読んでおられぬだろうな、ということだ。
むろん、やっかみ半分でいうのだが、少なくともその点に関しては、ぼくはそんな人生はイヤである。