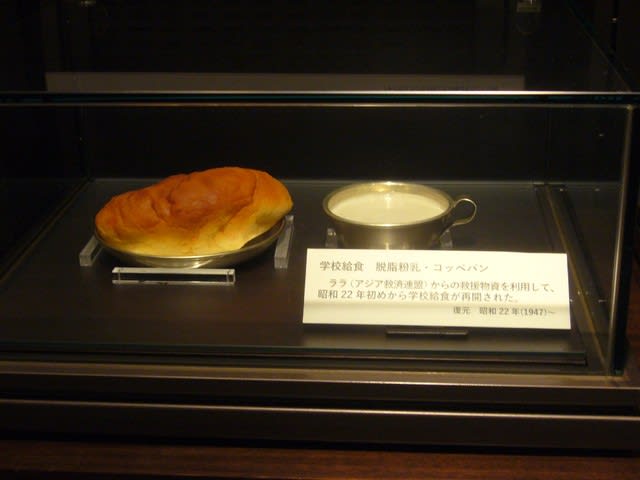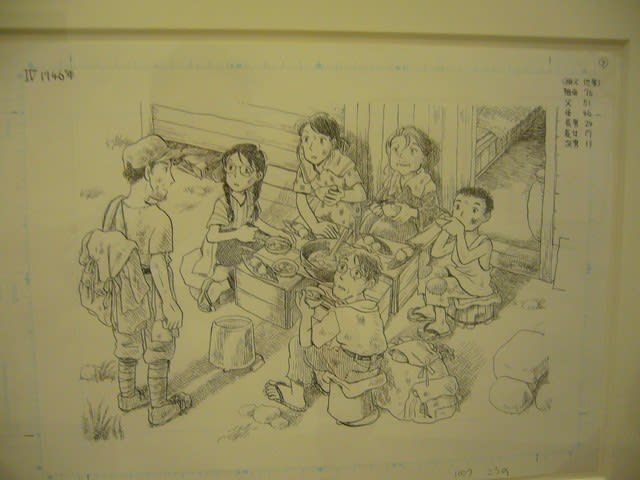ああ、憧れのハワイ航路
旧横浜港駅跡


航空旅客機がなかったころは、この駅から多くの人々が外国へ向けて旅立っていった。
見送る人旅立つ人、今よりよほど重い別れのドラマがあった。

恒例の防災フェア(赤レンガ)

最新の機器は一見の価値あり。


非常時の横浜の態勢は大丈夫なのか。
避難できる大きな公園が人口のわりに少ない気もする。
ところで今日は、例のIR誘致(カジノ法)に横浜が名乗りを上げてしまったことで、今一度港の様子を見に来た。

カジノによいイメージはない。
横浜のあたりでも江戸の終わりから明治始めにかけて博徒が横行した。
我が家では博徒を毛嫌いしてきた。
今でも暗黙に博打は家訓で法度となっている。
だからパチンコすらやらない。
第二次世界大戦勃発。風雲急を告げるヨーロッパ。
そんな時代の映画「カサブランカ」
映画の主要なシーンであったリックの店は、
粋な生演奏を聴かせるバーとカジノを併設した店だった。
アメリカへの渡航費用が不足した若い夫婦を
リック(ハンフリーボガート)が、ルーレット賭博でわざと負け、若い夫に勝たせる名場面。
アメリカへ無事渡ることが出来るきるのか。
映画では、カジノが効果的にとりあげられていた。
イチかバチかのカサブランカ
ところが今の横浜は、イチかバチかの世界でもない。
カジノも今ではシステマチック、
林市長は、圧力に屈したか。
都市造りは百年の計である。

横浜市民として、私は浜のドンに賛同する。
旧横浜港駅跡


航空旅客機がなかったころは、この駅から多くの人々が外国へ向けて旅立っていった。
見送る人旅立つ人、今よりよほど重い別れのドラマがあった。

恒例の防災フェア(赤レンガ)

最新の機器は一見の価値あり。


非常時の横浜の態勢は大丈夫なのか。
避難できる大きな公園が人口のわりに少ない気もする。
ところで今日は、例のIR誘致(カジノ法)に横浜が名乗りを上げてしまったことで、今一度港の様子を見に来た。

カジノによいイメージはない。
横浜のあたりでも江戸の終わりから明治始めにかけて博徒が横行した。
我が家では博徒を毛嫌いしてきた。
今でも暗黙に博打は家訓で法度となっている。
だからパチンコすらやらない。
第二次世界大戦勃発。風雲急を告げるヨーロッパ。
そんな時代の映画「カサブランカ」
映画の主要なシーンであったリックの店は、
粋な生演奏を聴かせるバーとカジノを併設した店だった。
アメリカへの渡航費用が不足した若い夫婦を
リック(ハンフリーボガート)が、ルーレット賭博でわざと負け、若い夫に勝たせる名場面。
アメリカへ無事渡ることが出来るきるのか。
映画では、カジノが効果的にとりあげられていた。
イチかバチかのカサブランカ
ところが今の横浜は、イチかバチかの世界でもない。
カジノも今ではシステマチック、
林市長は、圧力に屈したか。
都市造りは百年の計である。

横浜市民として、私は浜のドンに賛同する。