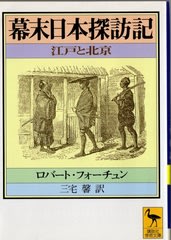茅ヶ崎城は横浜の北部、都筑区にある城跡である。
今では数少ない戦国時代の小さなお城が、ほぼ完全な姿で残っている。
もちろん石垣があったり、建物が残っているようなお城ではない。
港北ニュータウンの工事が始まり、どうなることかとハラハラしていたのだが、
一時はお城の周りのあまりの変貌ぶりに、茅ヶ崎城がどこだったか、
位置すらよくわからなくなっていた。
近年公園として整備されたので、あらためて訪れたのである。

とにかくコンパクトに、よくまとまっているお城である。
無駄のない縄張りは実戦ではどうだったのかは知らないが、見た目はすばらしい。
この空堀の風格はたいしたもの、

要所、要所にある解説文も、懇切丁寧である。
これが本丸(中郭)

北郭から中郭を見る

大きなお城のミニチュアといった感じで、
このままスケールを大きくすれば、国持ち大名のお城のようになりそうな気がする。
東郭と中郭を結ぶ土橋

城跡より北の方向を望む

本来のイメージの茅ヶ崎城。田んぼのなかに佇むさりげない姿がよかった。

もっとも当時はごらんのように樹木が生い茂り、郭の平らなところが畑になっていた。
空掘り等は当時からしっかり確認できたが、現在の方がより全体が見渡せるようになり、わかりやすい。
郷土の誇りである。
追伸
茅ヶ崎城には黄金伝説がある
「黄金千貫、二千貫、朝日輝る 夕日かがやく所にぞ ある」
がヒントの歌だそうだが
発掘調査でそれらしいものは、見つかったのだろうか
黄金伝説が紹介されていた本

神奈川の城 朝日新聞横浜支局編 昭和47年
今では数少ない戦国時代の小さなお城が、ほぼ完全な姿で残っている。
もちろん石垣があったり、建物が残っているようなお城ではない。
港北ニュータウンの工事が始まり、どうなることかとハラハラしていたのだが、
一時はお城の周りのあまりの変貌ぶりに、茅ヶ崎城がどこだったか、
位置すらよくわからなくなっていた。
近年公園として整備されたので、あらためて訪れたのである。

とにかくコンパクトに、よくまとまっているお城である。
無駄のない縄張りは実戦ではどうだったのかは知らないが、見た目はすばらしい。
この空堀の風格はたいしたもの、

要所、要所にある解説文も、懇切丁寧である。
これが本丸(中郭)

北郭から中郭を見る

大きなお城のミニチュアといった感じで、
このままスケールを大きくすれば、国持ち大名のお城のようになりそうな気がする。
東郭と中郭を結ぶ土橋

城跡より北の方向を望む

本来のイメージの茅ヶ崎城。田んぼのなかに佇むさりげない姿がよかった。

もっとも当時はごらんのように樹木が生い茂り、郭の平らなところが畑になっていた。
空掘り等は当時からしっかり確認できたが、現在の方がより全体が見渡せるようになり、わかりやすい。
郷土の誇りである。
追伸
茅ヶ崎城には黄金伝説がある
「黄金千貫、二千貫、朝日輝る 夕日かがやく所にぞ ある」
がヒントの歌だそうだが
発掘調査でそれらしいものは、見つかったのだろうか
黄金伝説が紹介されていた本

神奈川の城 朝日新聞横浜支局編 昭和47年