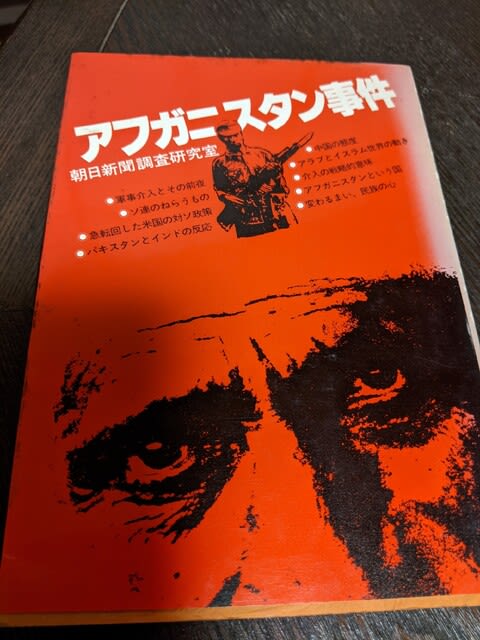タレントの不祥事問題は、企業のガバナンスの問題へと移ろうとしているようだ。
内向きな企業統治(企業文化)を原因とする不祥事は、近年多発している。
特定の役員が権力を握り、まわりをイエスマンで固めるやり方は、長い社歴のある多くの企業で陥りやすい問題だ。
今回の経緯を他山の石とすることも多いと思う。
- 人事権を持つ最高権力者の存在。(長期政権による思考の硬直化)
- 役員の高齢化(後任者の育成計画の不在)
- 外部からの視点を持たない社内の内向きな経営判断
これまでも番組作成の過程でプライバシー侵害の問題が多発していたようだが(ネット情報による)、改善できないまま今回の不祥事の発生となったようなので、会社組織が機能不全に陥っていたことは確かなようだ。
本来コンプライアンスに関する問題は、近年の企業経営の中で最重要視される問題であり、必ず社内に専門部署も設置されていたはずだ。
ということは、某テレビ局ではまったく機能していなかったということだ。
近年のテレビ離れは深刻なようだが、たまに見る民放番組は、報道番組の他はグルメ番組や知性を感じさせない浅薄な番組ばかりで、見るに堪えない。
予算の問題もあるだろうが、視聴率ばかりでなく、スポンサーを納得させるような視聴者へ意義のある情報を提供できる番組作りをしてもらいたいと思う。
(某テレビ局は不動産や有価証券の収益がかなりの部分を占めているようだが、その収益を番組制作へ回せないものなのだろうか?)
遠藤龍之介さんは、お若いころからお父さんのエッセイにたびたび登場していたので、以前から知っているようで妙な親近感がある。
某局の社長を経て民放連の会長になっていたんですね。
ひいき目かもしれないが、記者会見も誠実に答えられていて好感がもてた。
それだけに今回のことは残念だ。