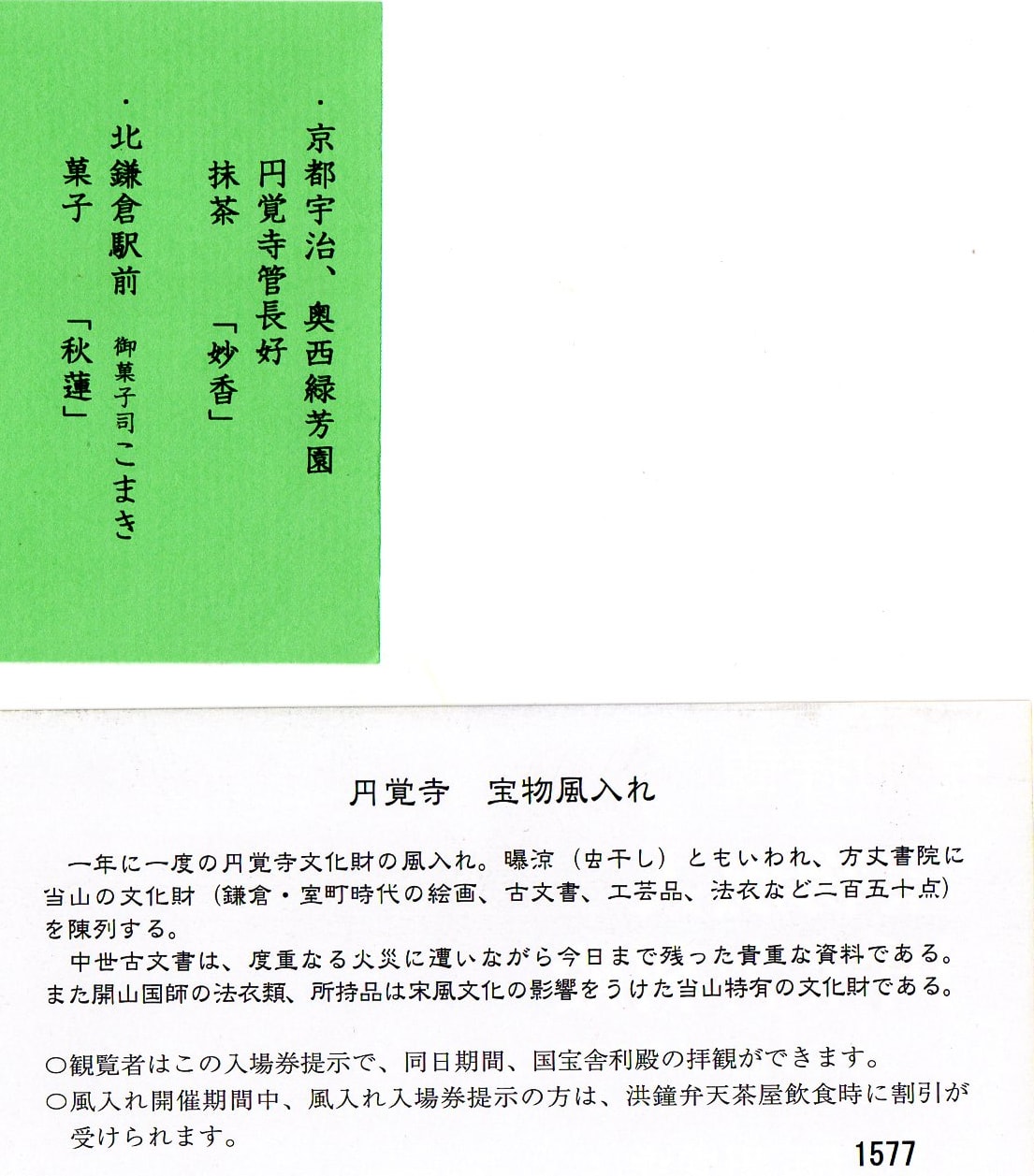ダリダリダリだー
ダリダリダリだー
(ビリーバンバン琥珀色の日々の曲で)
というわけでダリ展だ。
いまごろになって行ってきたが、
ネットで見たら、入るのに30分待ちになることもあるらしい。
少しビビったが、今日は娘の宿題のお付き合いなので出かけた。
待ち時間は11時時点で10分だった。
混んでいることには閉口したが、初期の作品から晩年の作品まで、映像、写真、関連本など多方面からダリの芸術にアプローチしていて飽きさせない。
必ずしも著名な作品が数多く揃っているわけでもないが、作家のトータルな部分がコンパクトに掴めるような内容だった。
特に晩年の大作「テトゥンの大会戦」は圧巻
調子に乗って、図録やグッズまで買ってしまった。


ダリダリダリだー
(ビリーバンバン琥珀色の日々の曲で)
というわけでダリ展だ。
いまごろになって行ってきたが、
ネットで見たら、入るのに30分待ちになることもあるらしい。
少しビビったが、今日は娘の宿題のお付き合いなので出かけた。
待ち時間は11時時点で10分だった。
混んでいることには閉口したが、初期の作品から晩年の作品まで、映像、写真、関連本など多方面からダリの芸術にアプローチしていて飽きさせない。
必ずしも著名な作品が数多く揃っているわけでもないが、作家のトータルな部分がコンパクトに掴めるような内容だった。
特に晩年の大作「テトゥンの大会戦」は圧巻
調子に乗って、図録やグッズまで買ってしまった。