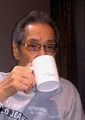|
日本財政 転換の指針 (岩波新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |
励みになります、応援よろしく
人気ブログランキング
経済のグローバル化はボーダレスな合従連衡を加速 取り残される国家と国民
今日25日は「生活の党」の党大会である。小沢一郎を代表とする方針が固まったようだが順当な人事と言えるだろう。筆者としては、“百術は一誠にしかず”を最後まで貫き通して欲しかったわけだが、昨年の選挙直前の術に溺れた選択には、支持しながらも、釈然としない自分がいたことを思い出す。小沢の政治理念を変える必要はないのだが、具体的政策論に落とし込む場合は、より懇切丁寧な説明を加えるリーダーになって貰いたいと念じている。国民の多くは陣営の議員と違い、直に小沢の薫陶を受けているわけではないし、忖度の意識もない。くどくどと説明するのが嫌いなようだが、有権者には、そのくどくどが必要なのである。自分で考えろと言われても、そのような訓練を国民が受けていない事実も認識して貰いたい。まぁ、寒さ厳しい折の船出だが、一歩一歩前進して貰うことを期待している。
さて本題だが、日経新聞に以下のような記事が載っていた。あまり話題にはなっていないが、グローバルな世界視野で事業を展開する産業界では、国を跨いだ合従連衡が加速している。この記事自体も多くのことを示唆しているし、世界的な発電産業のすう勢を占うことも可能だ。重電業界は、原子力発電より、天然ガスを燃料とするガスタービンコンバインドサイクル(GTCC)が主流になると読んでいるようだ。また、重電業界に関わらず、製薬メーカーの合従連衡も激しいものだし、自動車業界もかなりなもである。あらゆる業界の合従連衡はボーダレスな結びつきで生き残りに懸けている。
如何に経済がグローバルな規模で行われているかと云う典型的事例だが、国家のナショナリズムや民族間の諍いや宗教上の違いなどには、経済業界が持っている“マネー”と云う共通認識がない点が問題なのだとよく判る。一時は、社会主義と資本主義と云うブロックの共通認識があったのだが、多くの国が資本主義を採用するに至って、その共通認識が「人モノ金」から「人」が抜け“モノとマネー”に収斂された観がある。マネーに収斂された共通認識は、資本に集約され現在に至っているのだろう。その結果、企業の社会的役割などは葬られ、マネーの奴隷にならざるを得なくなったのだろう。
その意味で、企業は株主のものであると云う認識に疑いをかけるのは、かなり難しい状況になっている。日本の大企業の株主を眺めて思うことだが、SONY、PANASONIC、NISSANが純然たる日本の会社と言い切れる人は居ないような時代になっている。このような実態が、我々が正体不明の勢力のように語る“世界金融資本”と云う表現になるのだろう。いずれにせよ、彼らは“マネー”株主利益の為に企業経営を行うしか手立てがないのだから、経済界に国益を考えろと言っても詮無いことなのかもしれない。彼らは万国共通の“マネー”と云う共通言語で生きているのだと、つくづく感じる。
それに比べ、国家とか、民族とか、宗教とか、共通の認識がないのだから、厄介だ。それでいて、その国家なら、国家の財政事情では、企業収益の好不調が強く影響すると云うのだから皮肉なものである。経済界が、生き残りの為、共通言語である“マネー”を軸に、ボーダレスな世界を築くのだが、国家などはナショナリズムと云う価値を捨てることも出来ず、経済から取り残される。その遅れを取りもどうそうと云う動きが経済のブロック化なのだろう。ユーロ圏はその典型だが、TPPも同じ類だろう。まぁTPPの場合は、主たる参加国に問題があるので、ブロック化と云うのは言い過ぎかもしれない(笑)。
こういう情報に触れると、株式を公開した企業はすべからくグローバルマネーの洗礼を受ける可能性を持っている事になる。逆に、グローバルマネーに相手にされる企業でないと、生き残るのが大変なのかもしれない。ただ、同じグローバルな展開をしている公開企業でも、ソフトバンク、ユニクロ、トヨタ、日本電産、楽天など、オーナ企業が素早い展開をしているのは、やはりオーナー社長の心意気によるものだろうか。筆者の想像だが、オーナー企業の場合、その企業には“マネー”ではない共通言語を、オーナー社長を通じて共有しているのかもしれない。明確には判らないが、ボケボケの頭でそのように感じた。
≪ 重電業界、原発含め合従連衡が一段と加速
東芝と米ゼネラル・エレクトリック(GE)が火力発電設備で合弁会社を設立するのは、最大の成長が見込めるガス火力分野で主導権を握るためだ。三菱重工業と日立製作所もこの分野を狙って事業統合を決断。これに続き東芝とGEが踏み込んだ提携に動いたことで、世界の重電業界では原発を含めた合従連衡が一段と加速しそうだ。
天然ガスを燃料とする火力発電所が発電設備市場の主役とされるのは「シェールガス革命」の恩恵でガス価格が中長期的に低い水準にとどまる可能性が出てきたからだ。特に高効率のガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた「ガスタービンコンバインドサイクル(GTCC)」と呼ばれる火力設備の導入が急増する見通しだ。
OECD(経済協力開発機構)の予想では2035年までに合計850兆円程度の投資が発電設備に振り向けられる。巨大市場の欧米では老朽化した石炭火力の代替電源としてガス火力が増える。出力100万キロワット級の原子力発電所は1基4000億円前後かかるが、同じ出力のGTCCは数百億円規模と割安。米国では原発の建設が始まったのは4基だけ。米電力大手エクセロンはテキサス州での原発新設計画を撤回、ガス火力にシフトしている。
日本では東京電力の原発事故後、中部電力がGTCC新設を計画するなど30以上の火力発電所の新増設計画がある。石炭火力比率の高い東南アジアやインドのほか、ガスの埋蔵量の豊富な南米やアフリカでもガス火力の需要が増えそうだ。
大型ガスタービンは製造が難しく市場の参入障壁が高いため、GE、独シーメンス、三菱重工業の3社で世界シェア9割を握る。三菱重工業と日立製作所による火力事業の統合、GE―東芝連合の誕生を受けて今後はシーメンスと4位の仏アルストムも動き、中国やインドなどの重電メーカーを巻き込んだ業界再編が進みそうだ。
ガス火力を巡る重電業界での合従連衡の動きは原発分野に波及する可能性がある。発電コストが割安なガス火力が世界各地で増えれば、原発の新設が欧米を中心に低迷、新たな提携策が必要になるからだ。
焦点となるのが三菱重工と日立の提携関係の行方だ。日立はGEと原発事業を統合し、三菱重工は仏アレバと提携しているが、三菱重工、日立両社の首脳は原発分野でも協力関係を探ることを明言している。国内での原発新設の遅れなどで経営環境がさらに厳しくなれば、次世代技術の共同開発などでメリットのある両社が本格的な提携に動く可能性もある。長期的にはGEの動向が注目される。≫ (日経新聞)
 |
金融緩和で日本は破綻する |
| クリエーター情報なし | |
| ダイヤモンド社 |
励みになります、応援よろしく
人気ブログランキング












 https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif
https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif