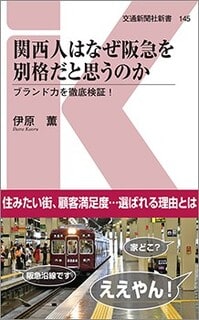
伊原薫さんの「関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか」を読みました。
内容紹介です。
交通新聞社から出ている新書なので、「阪急電車」がメインではありますが、内容紹介にもある「阪急ブランド」全体を取り上げています。ワタシの大好きな阪急百貨店もでてまいりました。2019年全国百貨店店舗別売上ランキング表が掲載されていましたが、1位は新宿伊勢丹、2位は梅田阪急でした。伊勢丹は2888億円、阪急は2507億円、3位の池袋西武が1840億円なので、上位2店舗の圧倒的な強さが際立っています。ちなみに大阪では大阪高島屋が1472億円で5位、あべの近鉄が1245億円で9位にランクインしていました。梅田阪急とあべの近鉄の売り場面積はほぼ同じにもかかわらず、売り上げは2倍となっていて、ブランド力の違いを見せつけています。
関西ローカルのテレビ番組で「魔法のレストラン」という番組があるのですが、その番組で以前「梅田阪急vs あべの近鉄」というタイトルで対決させたことがありました(これが評判だったのか、それ以降もいろいろな関西の百貨店を対決させていました。これ、結構面白いです)。テレビ番組なので、ちゃんとどちらにも“花”を持たせるように良いところをいろいろピックアップされていました。面白かったのは、どちらの百貨店にも同じフルーツ大福を売るお店が入っていてその「客単価」が、阪急は600円台、近鉄は400円台ぐらいでした(正確な金額は忘れましたが、とにかく結構な差があったんです)。近鉄の店員さんは「阪急さんはお遣い物にされるお客様が多いから」と理由をおっしゃっていましたが、百貨店愛好家のワタシは「ちゃう、ちゃう、百貨店の格の違いやん、沿線住民の違いやん」とテレビの前でツッコミを入れておりました。いくら高級フルーツが入ってても、大福は大福、お遣い物って感じではないような気がするのですが…。
阪急といえば小林一三なので、「逸翁自伝」と絡ませたお話もずいぶんと出てきました。ワタシ、昔に「逸翁自伝」そのものか、それを基にした小林一三の伝記なのか忘れましたが、小林一三さんについて書かれたものを読んだことがあるので、阪急電車の苦労した時代って読んでいます。阪急神戸線ってかなりの難工事で、その時にかかわったのが大林組でした。阪急百貨店の建て替えの時、最初は違う大手ゼネコンだったのですが、土地が軟弱か何かで途中で「できない」と言い出し、その後を大林組が引きうけたと新聞で読みました。「阪急と大林組は切っても切れない仲なんやんね~」と思った記憶があります。
線路を作ってから電車に乗ってくれるお客さんを作るために宅地開発したとか、集客のために終点の宝塚に動物園や遊園地、宝塚歌劇団を作ったとか、ターミナルに百貨店を作ったのは日本初だとか、そういうよく知られたエピソードに加え、もちろん、鉄道の本ですので、電車(車両)のことも書いてあります。車両の内外に対する美意識がすごいです。電車に乗るのは好きだけど「車両が云々」というほど鉄オタではないのですが、読みながら、大学時代、阪急電車に乗ってた頃に漠然と感じていた「他の私鉄とは違うよね」っていうのを何度も再認識しました。
本の帯の「家どこ?」「阪急沿線です」「ええやん!」っていう会話、わかります。ワタシ、これまでの人生で大学のたった4年間しか阪急電車(神戸線)に乗ってないくせに、「阪急電車で大学に通ってた」というプチ自慢?がまだありますから。
この本、よく売れているみたいです。8月に第1刷が出て、9月に第2刷になっています。それだけ「別格」だと思う人が多いんでしょうね。
内容紹介です。
阪急といえば、個性派ぞろいの関西私鉄各社のなかでも「高級」「美しい」といったイメージが強い。
さらに顧客満足度日本一の企業にも選ばれ続け、信頼のブランドを築いている。
ブランディングという概念のない時代から、いかにしてそのブランドをつくりあげ、守ってきたのか?
関西をはじめ全国の鉄道に明るい著者が、さまざまな視点から阪急の個性に注目。
わかりやすいエピソードを交えながら、ビジネス書とはちょっと違うテイストで、「阪急ブランド」が強固である理由を浮かび上がらせる。
さらに顧客満足度日本一の企業にも選ばれ続け、信頼のブランドを築いている。
ブランディングという概念のない時代から、いかにしてそのブランドをつくりあげ、守ってきたのか?
関西をはじめ全国の鉄道に明るい著者が、さまざまな視点から阪急の個性に注目。
わかりやすいエピソードを交えながら、ビジネス書とはちょっと違うテイストで、「阪急ブランド」が強固である理由を浮かび上がらせる。
交通新聞社から出ている新書なので、「阪急電車」がメインではありますが、内容紹介にもある「阪急ブランド」全体を取り上げています。ワタシの大好きな阪急百貨店もでてまいりました。2019年全国百貨店店舗別売上ランキング表が掲載されていましたが、1位は新宿伊勢丹、2位は梅田阪急でした。伊勢丹は2888億円、阪急は2507億円、3位の池袋西武が1840億円なので、上位2店舗の圧倒的な強さが際立っています。ちなみに大阪では大阪高島屋が1472億円で5位、あべの近鉄が1245億円で9位にランクインしていました。梅田阪急とあべの近鉄の売り場面積はほぼ同じにもかかわらず、売り上げは2倍となっていて、ブランド力の違いを見せつけています。
関西ローカルのテレビ番組で「魔法のレストラン」という番組があるのですが、その番組で以前「梅田阪急vs あべの近鉄」というタイトルで対決させたことがありました(これが評判だったのか、それ以降もいろいろな関西の百貨店を対決させていました。これ、結構面白いです)。テレビ番組なので、ちゃんとどちらにも“花”を持たせるように良いところをいろいろピックアップされていました。面白かったのは、どちらの百貨店にも同じフルーツ大福を売るお店が入っていてその「客単価」が、阪急は600円台、近鉄は400円台ぐらいでした(正確な金額は忘れましたが、とにかく結構な差があったんです)。近鉄の店員さんは「阪急さんはお遣い物にされるお客様が多いから」と理由をおっしゃっていましたが、百貨店愛好家のワタシは「ちゃう、ちゃう、百貨店の格の違いやん、沿線住民の違いやん」とテレビの前でツッコミを入れておりました。いくら高級フルーツが入ってても、大福は大福、お遣い物って感じではないような気がするのですが…。
阪急といえば小林一三なので、「逸翁自伝」と絡ませたお話もずいぶんと出てきました。ワタシ、昔に「逸翁自伝」そのものか、それを基にした小林一三の伝記なのか忘れましたが、小林一三さんについて書かれたものを読んだことがあるので、阪急電車の苦労した時代って読んでいます。阪急神戸線ってかなりの難工事で、その時にかかわったのが大林組でした。阪急百貨店の建て替えの時、最初は違う大手ゼネコンだったのですが、土地が軟弱か何かで途中で「できない」と言い出し、その後を大林組が引きうけたと新聞で読みました。「阪急と大林組は切っても切れない仲なんやんね~」と思った記憶があります。
線路を作ってから電車に乗ってくれるお客さんを作るために宅地開発したとか、集客のために終点の宝塚に動物園や遊園地、宝塚歌劇団を作ったとか、ターミナルに百貨店を作ったのは日本初だとか、そういうよく知られたエピソードに加え、もちろん、鉄道の本ですので、電車(車両)のことも書いてあります。車両の内外に対する美意識がすごいです。電車に乗るのは好きだけど「車両が云々」というほど鉄オタではないのですが、読みながら、大学時代、阪急電車に乗ってた頃に漠然と感じていた「他の私鉄とは違うよね」っていうのを何度も再認識しました。
本の帯の「家どこ?」「阪急沿線です」「ええやん!」っていう会話、わかります。ワタシ、これまでの人生で大学のたった4年間しか阪急電車(神戸線)に乗ってないくせに、「阪急電車で大学に通ってた」というプチ自慢?がまだありますから。
この本、よく売れているみたいです。8月に第1刷が出て、9月に第2刷になっています。それだけ「別格」だと思う人が多いんでしょうね。
















