桜井市の脇本遺跡の新発見について、更に続けます。
先ずは、泊瀬朝倉宮伝承地とされる白山神社について、


写真は、泊瀬朝倉宮伝承地とされる白山神社及び同神社境内。
白山神社は、今回第18次調査で発見された池状遺構・石積み遺構現場から、三輪山南麓沿いに東方面に向かった山麓段丘地帯。
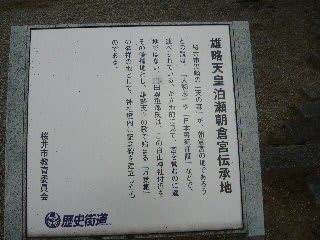

写真は、泊瀬朝倉宮伝承地とされる同神社境内の看板及び万葉集発祥の地記念碑。
泊瀬朝倉宮の伝承地としては、桜井市黒崎の白山神社境内に「雄略天皇泊瀬朝倉宮伝承地」の碑が建立されている。
一方で前述の通り、1984年に、同市脇本にある脇本遺跡で、5世紀後半のものと推定される掘立柱建物の柱穴が発見されており、考古学的見地から朝倉宮の有力な候補地とされている。
いずれにしても、泊瀬朝倉宮はこの桜井市黒崎の白山神社から脇本付近までの段丘地にあったのではないかと推定されている。
写真の通り、万葉集発祥の地として、雄略天皇泊瀬朝倉宮伝承地の記念看板と共に残る。
「籠(こ)もよ み籠持(こも)ち・・・・・・家をも名をも」で知られる、この求婚の歌は雄略天皇作で、万葉集の巻頭に選ばれたことで有名。
万葉集の編纂に深く関係したとされる大伴家持が、政治的に華々しかった時代が5世紀であることから、雄略天皇の歌が選ばれたのではと云われている。
雄略天皇は古墳時代の5世紀後半に在位した21代天皇で、ヤマト王権の勢力拡大を進めたとされる。
脇本遺跡では、古墳時代の初めの銅鐸の破片などが出土しており、奈良盆地から東国に抜ける伊勢街道の起点であり、大和朝廷の成立以降、列島経営のための関所のような機能を果たしてきたのではと考えられている。
5世紀後半~6世紀初頭の時期と思われる大型掘立柱建物や石溝・柵列など宮殿跡も既に発掘されている。
今回見つかった池状遺構の底面は、南北の高さがほぼ水平で、水がたまった形跡はなかった。堆積物がたまらないように管理されていたか、そもそも水が無かったかは不明という。

写真は、脇本遺跡北側の三輪山南麓方面光景。
京都教育大の和田萃名誉教授は「周囲を囲む大溝という印象。景観や防御の要素もあるのではないか。東国へ行ける初瀬街道がある三輪山南麓の谷口に堀を巡らせ、威容を誇る王宮だったと想像できる」と話している。
雄略天皇の桜井市泊瀬朝倉宮のように、歴代天皇宮都の所在地のほとんどは大和盆地だが、河内王朝初代の第15代応神天皇、仁徳天皇、履中天皇そして4代目の第18代反正天皇までは、宮都が大和-河内-大和-河内と交互に入れ替わっている。この事実をどう理解したら良いのであろうか?
次に雄略天皇の陵墓について、見てみよう。

写真は、藤井寺市の第14代仲哀天皇陵前方部全景。近鉄南大阪線藤井寺駅南の商店街を抜けた所に所在するが、これこそが考古学的には真の雄略天皇陵と目されている。
全長約242m・後円部径約148m・高さ19.5m・前方部幅約182m・高さ約16m・周濠幅約50mの三段構築の大型前方後円墳で、古市古墳群では4番目の大きさ。
別名“岡ミサンザイ古墳”とも呼ばれ、羽曳野丘陵の北東部外縁に位置している。
横穴式石室を採用している可能性があること、また出土した円筒埴輪などから、5世紀後半の築造と考えられている。
このことからこの古墳こそ、前方後円墳が造営年代的にも、雄略天皇陵ではないかと云われている。
第14代仲哀天皇(在位:192~200年)陵にしては、余りに年代のずれがあり、かけ離れていると云える。
先ずは、泊瀬朝倉宮伝承地とされる白山神社について、


写真は、泊瀬朝倉宮伝承地とされる白山神社及び同神社境内。
白山神社は、今回第18次調査で発見された池状遺構・石積み遺構現場から、三輪山南麓沿いに東方面に向かった山麓段丘地帯。
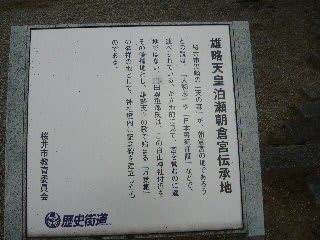

写真は、泊瀬朝倉宮伝承地とされる同神社境内の看板及び万葉集発祥の地記念碑。
泊瀬朝倉宮の伝承地としては、桜井市黒崎の白山神社境内に「雄略天皇泊瀬朝倉宮伝承地」の碑が建立されている。
一方で前述の通り、1984年に、同市脇本にある脇本遺跡で、5世紀後半のものと推定される掘立柱建物の柱穴が発見されており、考古学的見地から朝倉宮の有力な候補地とされている。

いずれにしても、泊瀬朝倉宮はこの桜井市黒崎の白山神社から脇本付近までの段丘地にあったのではないかと推定されている。
写真の通り、万葉集発祥の地として、雄略天皇泊瀬朝倉宮伝承地の記念看板と共に残る。
「籠(こ)もよ み籠持(こも)ち・・・・・・家をも名をも」で知られる、この求婚の歌は雄略天皇作で、万葉集の巻頭に選ばれたことで有名。
万葉集の編纂に深く関係したとされる大伴家持が、政治的に華々しかった時代が5世紀であることから、雄略天皇の歌が選ばれたのではと云われている。

雄略天皇は古墳時代の5世紀後半に在位した21代天皇で、ヤマト王権の勢力拡大を進めたとされる。
脇本遺跡では、古墳時代の初めの銅鐸の破片などが出土しており、奈良盆地から東国に抜ける伊勢街道の起点であり、大和朝廷の成立以降、列島経営のための関所のような機能を果たしてきたのではと考えられている。
5世紀後半~6世紀初頭の時期と思われる大型掘立柱建物や石溝・柵列など宮殿跡も既に発掘されている。
今回見つかった池状遺構の底面は、南北の高さがほぼ水平で、水がたまった形跡はなかった。堆積物がたまらないように管理されていたか、そもそも水が無かったかは不明という。

写真は、脇本遺跡北側の三輪山南麓方面光景。
京都教育大の和田萃名誉教授は「周囲を囲む大溝という印象。景観や防御の要素もあるのではないか。東国へ行ける初瀬街道がある三輪山南麓の谷口に堀を巡らせ、威容を誇る王宮だったと想像できる」と話している。
雄略天皇の桜井市泊瀬朝倉宮のように、歴代天皇宮都の所在地のほとんどは大和盆地だが、河内王朝初代の第15代応神天皇、仁徳天皇、履中天皇そして4代目の第18代反正天皇までは、宮都が大和-河内-大和-河内と交互に入れ替わっている。この事実をどう理解したら良いのであろうか?

次に雄略天皇の陵墓について、見てみよう。

写真は、藤井寺市の第14代仲哀天皇陵前方部全景。近鉄南大阪線藤井寺駅南の商店街を抜けた所に所在するが、これこそが考古学的には真の雄略天皇陵と目されている。
全長約242m・後円部径約148m・高さ19.5m・前方部幅約182m・高さ約16m・周濠幅約50mの三段構築の大型前方後円墳で、古市古墳群では4番目の大きさ。
別名“岡ミサンザイ古墳”とも呼ばれ、羽曳野丘陵の北東部外縁に位置している。
横穴式石室を採用している可能性があること、また出土した円筒埴輪などから、5世紀後半の築造と考えられている。
このことからこの古墳こそ、前方後円墳が造営年代的にも、雄略天皇陵ではないかと云われている。

第14代仲哀天皇(在位:192~200年)陵にしては、余りに年代のずれがあり、かけ離れていると云える。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます