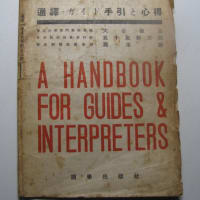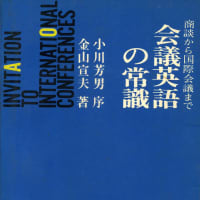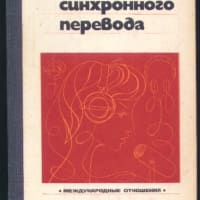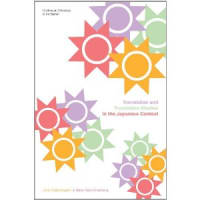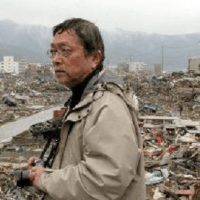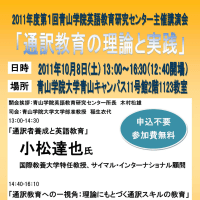■森田思軒は「翻訳の心得」(明治20)の中で、「原文に心に印す」とあらば直ちに「心に印す」と翻訳し度し。其事恰も「肝に銘ず」と相符すればとて「肝に銘ず」とは翻訳す可らず」と書いた。「翻訳の心得」は数ページの短い文章だが、一応翻訳論と言っていいだろう。二葉亭四迷の有名な「余が翻訳の標準」も短い文章だ。
最近、高橋五郎という人が明治41年に『英文訳解法』という本の中で、かなり長い翻訳論を書いているのを見つけた。その「第3章 英文訳解の忠実兼正確なり得べき事」は40ページほどあり、後続の章を合わせて考えれば、昭和初期の野上豊一郎の『翻訳論』に先立つ、比較的充実した翻訳論であると言っていいと思う。高橋五郎は明治・大正期の評論家、英語学者で、聖書や「ブルタルク英雄伝」「カーライル仏国革命史」などの翻訳がある。彼の翻訳論の要は直訳擁護だ。
「按ずるに翻訳の最大要件は先づ原文の精神を深く究め且其一般の口調及び特殊の観念を写し出し且つ此方の文法を傷つけざる限りは及ぶだけ原本の文体を紙上に再現するに在るが如し、若し果たして然りとせば翻訳は此等三種(逐字訳、直訳、意訳のこと)中の第二、即ち直訳literal translationを以て最上乗なる者と為さざる可らず、」
しかし面白いことに、高橋は森田思軒とは違い、idiomaticな表現はそれに対応する表現に転換することを薦めている。たとえば、The child is father to the man.は、「之を善き意味にすれば「栴檀は二葉より馨はし」と為すべく、叉之を悪き意味にしては「三歳児(みつご)の魂百までも」と為すべし」と言う。
翻訳はかくあるべしという規範は、翻訳者や文学者の翻訳についての発言だけでなく、『英文訳解法』のような語学学習書を通じても形作られていったのではないだろうか。
最近、高橋五郎という人が明治41年に『英文訳解法』という本の中で、かなり長い翻訳論を書いているのを見つけた。その「第3章 英文訳解の忠実兼正確なり得べき事」は40ページほどあり、後続の章を合わせて考えれば、昭和初期の野上豊一郎の『翻訳論』に先立つ、比較的充実した翻訳論であると言っていいと思う。高橋五郎は明治・大正期の評論家、英語学者で、聖書や「ブルタルク英雄伝」「カーライル仏国革命史」などの翻訳がある。彼の翻訳論の要は直訳擁護だ。
「按ずるに翻訳の最大要件は先づ原文の精神を深く究め且其一般の口調及び特殊の観念を写し出し且つ此方の文法を傷つけざる限りは及ぶだけ原本の文体を紙上に再現するに在るが如し、若し果たして然りとせば翻訳は此等三種(逐字訳、直訳、意訳のこと)中の第二、即ち直訳literal translationを以て最上乗なる者と為さざる可らず、」
しかし面白いことに、高橋は森田思軒とは違い、idiomaticな表現はそれに対応する表現に転換することを薦めている。たとえば、The child is father to the man.は、「之を善き意味にすれば「栴檀は二葉より馨はし」と為すべく、叉之を悪き意味にしては「三歳児(みつご)の魂百までも」と為すべし」と言う。
翻訳はかくあるべしという規範は、翻訳者や文学者の翻訳についての発言だけでなく、『英文訳解法』のような語学学習書を通じても形作られていったのではないだろうか。