第2章はルネサンス時代のフィレンツェに話が跳ぶ。11世紀から13世紀にかけて行われた十字軍遠征に協力した結果、イタリアの都市は大いなる繁栄を手にすることができ、裕福な市民階級が台頭してくる。裕福になると、人間は神頼みを止めて人生を謳歌するようになる。そこで、同じように人間中心だったギリシャ・ローマ時代に興味を持つに至る。結果、こ難しい宗教絵画よりも、愛と美を愛でるギリシャ・ローマ時代の美術や学問が再生(リナーシタ)してくる。このムーブメントが「ルネサンス(文芸復興主義)」と後々の世で呼ばれることになるが、当時の人たちはあくまでもキリスト教徒であることから抜け出せないために、「キリスト教人文主義」という範囲で古代の文明・文化を再生していた。
キリスト教人文主義を象徴する作品の一つとして、ボッティチェリの『プリマヴェーラ(春)』なる作品が取り上げられる。ここに登場するのはキリスト教とは関係のない異端の神々のオンパレードでとても美しいのだが、キリスト人文主義的には、左端のヘルメス(伝達の神)が伝令の杖で頭上の雲を払っている仕草が「人間の愛なんて神様の愛に比べらたらこの程度さ」とイエス様の愛を讃えた絵画となっているのだと木村氏は言う。そうなのかもしれないが、私としては当時に時代を「マンジャーレ、カンターレ、アモーレ」として愉しんでいた人たちが、うるさいお上に表面的に従う素振りを見せるために考え出したエクスキューズとして宗教画に込められた象徴を逆利用していたとしか思えないのです。
そして究極の言い訳が「ギリシャ・ローマの時代は、イエス様がお生まれになる前に時代なので、仕方がないよね。でも偉大な文化のルーツであることには変わりがないよね」という考え方であろう。これを地で言ったのが、人文主義者で政治家だったレオナルド・プルーニさん。この人のお墓『レオナルド・プルーニの墓』には、当時には例がない詩が書かれている他、ギリシャ・ローマの異端の女神や天使が書かれているとか。
特にフィレンツェは商人と職人が多く、父親が家の近くで仕事をしていたために、家族という意識も強くなり、聖家族という画として現れてきた。それまではイエスの父親のヨセフは軽んじられていたが、きちんと聖家族として描かれるようになったんだとか。良かったね、ヨセフのお父さん。ミケランジェロの『聖家族』が有名だが、背景については上段のようなエクスキューズがあるらしい。つまり、後方の裸体男性は異端の時代を表し、画面を横切る溝のような線によって異端の時代からキリストの時代に移行している時代を表現しているという説があるとのこと。命と引き換えに芸術に身を捧げた人たちが、精一杯考えた言い訳が涙ぐましい。
この時代に、かの有名はミケランジェロやダ・ビンチ、ラファエロなどが登場することで、芸術価値はうなぎ上りに上がっていった訳だが、その結果として以前はたんなる画家だった人たちがゲージツ家として認められ、作品を制作するのではなくクリエイトするようにお成り遊ばした。自尊心や自意識が高まることで、肖像画という絵画ジャンルが誕生し、裕福な中産階級の人々の間にも広まっていくことで、絵画のマーケットが拡大していくことに貢献したのがルネサンスの影響の一つなのだそうだ。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
第3章では、ルネサンスの影響が飛び火したネーデルランドでの絵画の発展のお話が繰り広げられる。時代を追いながら、欧州各地を廻って美術の変化・変容を説明してくれているところは、一種の絵巻物のようでもある。各国でのムーブメントがばらばらにではなく、連携してお互いに影響を与えながら変化・発展している様は、とても分かりやすく、しかも頭が良くなった感じがする。木村さん、ありがとう。
力をつけたネーデルランドの中産階級の人たちが、美術界マーケットに新市場を作り出していく過程で、王侯貴族のような古典教養、キリスト教知識がない彼らは自分たちが理解できるような美術を求めるようになる。「お客様は神様」を地で行くようなニーズ汲み取り型マーケティングとでも言うべきか。彼らが理解できるように、この世のあらゆる事物のディテールを写実的に描く絵画が、油絵の具の使用法の進化とともに誕生したのがこの時代。もちろん、キリスト教会が絶対の力を持っていた時代なので、様々なものに意味を持たせる=象徴を用いて、世俗的な空間を聖なる空間に仕立て上げると言う、隠されたシンポリズム(象徴主義)というテクニックが使われた。例えば、『メロードの祭壇画』なる作品に描かれている空間は市民階級(画の発注者であり、お客であり=神様だったわけ)の家の一室なのだが、このことを「不埒な輩め」と言わさないように、卓上の白百合はマリア様の純潔を、消えたばかりの蝋燭は神がマリア様の胎内に移ったことを、描かれている花はマリア様の純潔だったり慈愛だったりを現すなど、色々な象徴を込める工夫が込められているのだそうだ。「一般ピープルのお家に聖なる家族を描く」ことが不謹慎にならないように工夫する必要があるなんて、なんとメンドくさい時代だったんだ。
ディテールが緻密に描かれるようになったもう一つの理由は、すべては神様の創造物であるという考え方。文盲が多かった庶民に対して、キリストの教えを伝える手段として祭壇画や宗教画に描かれた世界が使われたわけ。つまりは、絵画や教会建築は伝道のためのメディアだったんだね。
時代が進んで16世紀になると、宗教革命が始まる。聖書と対話することのみを通して人間は救済されると説くプロテスタントは、聖書に権威をもたせるべくカトリック的な聖像崇拝や絵画に対して批判的であった。そのため、ルターの宗教改革が力を持ったドイツでは絵画が発展せずに、音楽に芸術パワーが向けられたのだそうだ。
ネーデルランドといえばカルヴィン。ルターと並んで世界史にも登場する宗教改革の西横綱によるプロテスタントが浸透していくことで、宗教美術が破壊され、画家たちが向かった先に、風俗画や風景画、静物画といったジャンルが生まれてきた。当初は支配階級だったカトリックの面々の顔も立てつつ、聖書の物語が描かれていると解釈できるような工夫がなされていたらしい。『肉屋の店先』という作品は、文字通りに肉屋店頭を描いた静物画であるとともに、放蕩息子の帰還やエジプトへの逃避といった聖書の物語をとおして聖書的な道徳教訓が示されているのだそうだ。描き手のピーテル・アールツセンさん、よほど頭を捻りながらこの画を描いたに違いない。
こうした時代を経て、富と力を得た一般市民が美術のパトロンになり、絵画が一般人の家庭の中に入り込んでいった。一般市民はプロテスタントなので、質素ではあるが満ち足りた豊かな生活を写す鏡という立ち位置に絵画が変貌していったのがこの時代。代表的のものが静物画であり、特にオランダではカルヴィアン主義の影響により、人生の儚さや脆さ、現世の快楽や贅沢にたいする節度や勤勉を説いた”ヴァニスタ”という象徴性の強い絵画が誕生したのだそうだ。ヤン・デ・へーム作の『花瓶の花』を題材に、この画に描かれた人生の儚さを木村氏は解説してくれるが、得てして絵図らが暗~くなってしまうこの手の説教臭い美術は苦手だな。人間、正直に分相応に生きていればお天道様がしっかり見ていてくださる、といった江戸時代の長屋を舞台にした人情落語は好きだが、ヴァニスタという説教臭い画は好きになれない。何しろ、辛気臭すぎて愉しめない。
ここまでが第2章と第3章。続いて第4章の肖像画の発展の歴史に繋がるのだが、今日は疲れたのでこの辺りでお仕舞い。
キリスト教人文主義を象徴する作品の一つとして、ボッティチェリの『プリマヴェーラ(春)』なる作品が取り上げられる。ここに登場するのはキリスト教とは関係のない異端の神々のオンパレードでとても美しいのだが、キリスト人文主義的には、左端のヘルメス(伝達の神)が伝令の杖で頭上の雲を払っている仕草が「人間の愛なんて神様の愛に比べらたらこの程度さ」とイエス様の愛を讃えた絵画となっているのだと木村氏は言う。そうなのかもしれないが、私としては当時に時代を「マンジャーレ、カンターレ、アモーレ」として愉しんでいた人たちが、うるさいお上に表面的に従う素振りを見せるために考え出したエクスキューズとして宗教画に込められた象徴を逆利用していたとしか思えないのです。
そして究極の言い訳が「ギリシャ・ローマの時代は、イエス様がお生まれになる前に時代なので、仕方がないよね。でも偉大な文化のルーツであることには変わりがないよね」という考え方であろう。これを地で言ったのが、人文主義者で政治家だったレオナルド・プルーニさん。この人のお墓『レオナルド・プルーニの墓』には、当時には例がない詩が書かれている他、ギリシャ・ローマの異端の女神や天使が書かれているとか。
特にフィレンツェは商人と職人が多く、父親が家の近くで仕事をしていたために、家族という意識も強くなり、聖家族という画として現れてきた。それまではイエスの父親のヨセフは軽んじられていたが、きちんと聖家族として描かれるようになったんだとか。良かったね、ヨセフのお父さん。ミケランジェロの『聖家族』が有名だが、背景については上段のようなエクスキューズがあるらしい。つまり、後方の裸体男性は異端の時代を表し、画面を横切る溝のような線によって異端の時代からキリストの時代に移行している時代を表現しているという説があるとのこと。命と引き換えに芸術に身を捧げた人たちが、精一杯考えた言い訳が涙ぐましい。
この時代に、かの有名はミケランジェロやダ・ビンチ、ラファエロなどが登場することで、芸術価値はうなぎ上りに上がっていった訳だが、その結果として以前はたんなる画家だった人たちがゲージツ家として認められ、作品を制作するのではなくクリエイトするようにお成り遊ばした。自尊心や自意識が高まることで、肖像画という絵画ジャンルが誕生し、裕福な中産階級の人々の間にも広まっていくことで、絵画のマーケットが拡大していくことに貢献したのがルネサンスの影響の一つなのだそうだ。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
第3章では、ルネサンスの影響が飛び火したネーデルランドでの絵画の発展のお話が繰り広げられる。時代を追いながら、欧州各地を廻って美術の変化・変容を説明してくれているところは、一種の絵巻物のようでもある。各国でのムーブメントがばらばらにではなく、連携してお互いに影響を与えながら変化・発展している様は、とても分かりやすく、しかも頭が良くなった感じがする。木村さん、ありがとう。
力をつけたネーデルランドの中産階級の人たちが、美術界マーケットに新市場を作り出していく過程で、王侯貴族のような古典教養、キリスト教知識がない彼らは自分たちが理解できるような美術を求めるようになる。「お客様は神様」を地で行くようなニーズ汲み取り型マーケティングとでも言うべきか。彼らが理解できるように、この世のあらゆる事物のディテールを写実的に描く絵画が、油絵の具の使用法の進化とともに誕生したのがこの時代。もちろん、キリスト教会が絶対の力を持っていた時代なので、様々なものに意味を持たせる=象徴を用いて、世俗的な空間を聖なる空間に仕立て上げると言う、隠されたシンポリズム(象徴主義)というテクニックが使われた。例えば、『メロードの祭壇画』なる作品に描かれている空間は市民階級(画の発注者であり、お客であり=神様だったわけ)の家の一室なのだが、このことを「不埒な輩め」と言わさないように、卓上の白百合はマリア様の純潔を、消えたばかりの蝋燭は神がマリア様の胎内に移ったことを、描かれている花はマリア様の純潔だったり慈愛だったりを現すなど、色々な象徴を込める工夫が込められているのだそうだ。「一般ピープルのお家に聖なる家族を描く」ことが不謹慎にならないように工夫する必要があるなんて、なんとメンドくさい時代だったんだ。
ディテールが緻密に描かれるようになったもう一つの理由は、すべては神様の創造物であるという考え方。文盲が多かった庶民に対して、キリストの教えを伝える手段として祭壇画や宗教画に描かれた世界が使われたわけ。つまりは、絵画や教会建築は伝道のためのメディアだったんだね。
時代が進んで16世紀になると、宗教革命が始まる。聖書と対話することのみを通して人間は救済されると説くプロテスタントは、聖書に権威をもたせるべくカトリック的な聖像崇拝や絵画に対して批判的であった。そのため、ルターの宗教改革が力を持ったドイツでは絵画が発展せずに、音楽に芸術パワーが向けられたのだそうだ。
ネーデルランドといえばカルヴィン。ルターと並んで世界史にも登場する宗教改革の西横綱によるプロテスタントが浸透していくことで、宗教美術が破壊され、画家たちが向かった先に、風俗画や風景画、静物画といったジャンルが生まれてきた。当初は支配階級だったカトリックの面々の顔も立てつつ、聖書の物語が描かれていると解釈できるような工夫がなされていたらしい。『肉屋の店先』という作品は、文字通りに肉屋店頭を描いた静物画であるとともに、放蕩息子の帰還やエジプトへの逃避といった聖書の物語をとおして聖書的な道徳教訓が示されているのだそうだ。描き手のピーテル・アールツセンさん、よほど頭を捻りながらこの画を描いたに違いない。
こうした時代を経て、富と力を得た一般市民が美術のパトロンになり、絵画が一般人の家庭の中に入り込んでいった。一般市民はプロテスタントなので、質素ではあるが満ち足りた豊かな生活を写す鏡という立ち位置に絵画が変貌していったのがこの時代。代表的のものが静物画であり、特にオランダではカルヴィアン主義の影響により、人生の儚さや脆さ、現世の快楽や贅沢にたいする節度や勤勉を説いた”ヴァニスタ”という象徴性の強い絵画が誕生したのだそうだ。ヤン・デ・へーム作の『花瓶の花』を題材に、この画に描かれた人生の儚さを木村氏は解説してくれるが、得てして絵図らが暗~くなってしまうこの手の説教臭い美術は苦手だな。人間、正直に分相応に生きていればお天道様がしっかり見ていてくださる、といった江戸時代の長屋を舞台にした人情落語は好きだが、ヴァニスタという説教臭い画は好きになれない。何しろ、辛気臭すぎて愉しめない。
ここまでが第2章と第3章。続いて第4章の肖像画の発展の歴史に繋がるのだが、今日は疲れたのでこの辺りでお仕舞い。











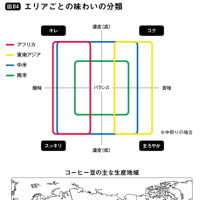













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます