塩野七生ほど、"女史"という称号が似合う方はおられないと思う。凛々しく、厳しく、スッパリと物事を切っていきながら、温かい目線と愛情が文章の根底に感じられる。『日本人へ』と題されたエッセイ集は何冊かあるが、その中の『国家と歴史篇』を手にとってみた。
古代ローマ、中世イタリアなどの歴史モノを著わした方なので、悠然たる時の流れの中での現代日本の姿に対するコメントは容赦がないにも拘わらず、心地が良い。決して、Mではないつもりだが、厳しいコメントであるはずなのに、「言ってくれてありがとう」と心の底で言ってしまうのは、著者の心底にある温かさと愛情が見え隠れしているからなのだろう。
それにしても、文章は鋭い。切れ実の鋭い刃物のように縦横無尽に切って捨てる硬質で男性的な文章には無駄が無く、優れた議論を聞いているかのよう。物事を言い切る術、そして他の言葉でふんわりとした単語や用語を定義しなおす術に非常に長けておられる。説得力とは、こんなところに現るのだろうことが良く理解できた。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
政治とは、感性に訴えて獲得した権力を理性に基づいて行使していくもの。
"感性"と"理性"という対比する単語を使いながら、"政治"の本質を彼女なりに切り取ってみた台詞がこれだが、「そうかも!」と唸ってしまう。
「夢」や「ゆとり」や「美しい」とかは、個人の性格や好みによるから同一ではない。このように客観的な基準を決めることが不可能は事柄は宗教家や詩人の分野のことであって、政治家や官僚が口をはさむことではない。政治家や官僚は、現実的で具体的な問題の解決に専念すべきであると思う。
これは、常々私が会社のビジョンや戦略目標が目に入るたびに思う感想と全く同じものだ。ビジョンや戦略目標が単なるスローガン、しかも誰もが反対できないような美辞麗句を並べただけで、具体的な姿が不明なキャッチコピー化したものが多すぎる。作った経営者自体が、心から自分の組織のビジョンや戦略目標の重要性を理解せずに、下の者が作って上げて来たものに対して評論批判する経営をしているから、誰もが否定できないが何を表しているのかが不明な美辞麗句のオンパレードになってしまうのだと思う。
優雅であることの意味がよくわかった。大胆で官能的であると同時に絶対に下品であってはならないのが、エレガントの必要不可欠な条件であることだ。言い換えれば、大胆と官能的と品位は、虚実皮膜の関係にあるということか。優雅と静かな緊張は、表裏一体にあるのかもしれない。
これが塩野七生女史の凄いところ。"優雅"を自分なりに定義しなおしている。ありふれた言葉をそのまま使うのではなく、自分の頭で考えて再定義することで、著者のモノの考え方や感じ方が理解できる。「ヴァレンティノのドレスは優雅」というよりも、このような再定義をする行為こそが、何よりも自分の考えや感じたことを伝える力があることが理解できた。塩野さん、ありがとう。
日本人は、ここの分野では優れているのである。だが、それらを統合してある種の化学反応を起こさせることで、ここの分野であげていた実績以上の実績に変貌させる才能では、昔から得意ではなかったように思える。
もしも外国人の誰かがこの日本の歴史を書くとしたら、ここの分野では才能ある人に恵まれながらそれらを全体として活かすことを知らなかった民族、と書くのではないだろうか。ほんとは、それこそが政治の役割なのだが。
似たような文章が二回出ていた。外国で長く暮らし、しかも古代と中世において大国であった国々の歴史を研究し、庶民に理解させるだけではなく、歴史の裏にある人間社会の真理に切り込んできた著者ならではの"日本批判"である。"批判"と書いたが、決して悪口ではなく、愛情の裏返しのコメントだ。私には、このコメントは現代日本の企業経営における無能さを著した的確な批判だと思ったね。経営者としてやるべきことをせずに、優秀な部下たちを鞭で叩くことが"経営"だと勘違いしている安楽に堕した日本の経営者(すべてとは言わない)そのものだよ。例えば、倒産寸前だったシャープが外資の門下に下った途端に、なぜ元気になるの?日産自動車もそうだった。これって日本の経営者の無能さを表している何よりの証拠じゃないだろうか? このことはエディー・ジョンズの著作を読んだ時にも感じた。
これら以外にも、今の私にササッたコメントがあった。
文化を共有しない外国との交渉は、相手側が思わず苦笑して、ヤラレタネ、と思ったときからスタートすべきなのである。理で対して行くのは、その後なのだ。
偏差値教育が大勢を見極める能力のない指導者を育てたのと同じに、点数至上主義は、スポーツの醍醐味を味わわせてくれる選手を、競技の場から排除していくようになるだろう。ポイント主義は単に勝者を決める手段であったはずである。だが、それのみが偏重されるようになると、手段の目的化になってしまう。
古代ローマ、中世イタリアなどの歴史モノを著わした方なので、悠然たる時の流れの中での現代日本の姿に対するコメントは容赦がないにも拘わらず、心地が良い。決して、Mではないつもりだが、厳しいコメントであるはずなのに、「言ってくれてありがとう」と心の底で言ってしまうのは、著者の心底にある温かさと愛情が見え隠れしているからなのだろう。
それにしても、文章は鋭い。切れ実の鋭い刃物のように縦横無尽に切って捨てる硬質で男性的な文章には無駄が無く、優れた議論を聞いているかのよう。物事を言い切る術、そして他の言葉でふんわりとした単語や用語を定義しなおす術に非常に長けておられる。説得力とは、こんなところに現るのだろうことが良く理解できた。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
政治とは、感性に訴えて獲得した権力を理性に基づいて行使していくもの。
"感性"と"理性"という対比する単語を使いながら、"政治"の本質を彼女なりに切り取ってみた台詞がこれだが、「そうかも!」と唸ってしまう。
「夢」や「ゆとり」や「美しい」とかは、個人の性格や好みによるから同一ではない。このように客観的な基準を決めることが不可能は事柄は宗教家や詩人の分野のことであって、政治家や官僚が口をはさむことではない。政治家や官僚は、現実的で具体的な問題の解決に専念すべきであると思う。
これは、常々私が会社のビジョンや戦略目標が目に入るたびに思う感想と全く同じものだ。ビジョンや戦略目標が単なるスローガン、しかも誰もが反対できないような美辞麗句を並べただけで、具体的な姿が不明なキャッチコピー化したものが多すぎる。作った経営者自体が、心から自分の組織のビジョンや戦略目標の重要性を理解せずに、下の者が作って上げて来たものに対して評論批判する経営をしているから、誰もが否定できないが何を表しているのかが不明な美辞麗句のオンパレードになってしまうのだと思う。
優雅であることの意味がよくわかった。大胆で官能的であると同時に絶対に下品であってはならないのが、エレガントの必要不可欠な条件であることだ。言い換えれば、大胆と官能的と品位は、虚実皮膜の関係にあるということか。優雅と静かな緊張は、表裏一体にあるのかもしれない。
これが塩野七生女史の凄いところ。"優雅"を自分なりに定義しなおしている。ありふれた言葉をそのまま使うのではなく、自分の頭で考えて再定義することで、著者のモノの考え方や感じ方が理解できる。「ヴァレンティノのドレスは優雅」というよりも、このような再定義をする行為こそが、何よりも自分の考えや感じたことを伝える力があることが理解できた。塩野さん、ありがとう。
日本人は、ここの分野では優れているのである。だが、それらを統合してある種の化学反応を起こさせることで、ここの分野であげていた実績以上の実績に変貌させる才能では、昔から得意ではなかったように思える。
もしも外国人の誰かがこの日本の歴史を書くとしたら、ここの分野では才能ある人に恵まれながらそれらを全体として活かすことを知らなかった民族、と書くのではないだろうか。ほんとは、それこそが政治の役割なのだが。
似たような文章が二回出ていた。外国で長く暮らし、しかも古代と中世において大国であった国々の歴史を研究し、庶民に理解させるだけではなく、歴史の裏にある人間社会の真理に切り込んできた著者ならではの"日本批判"である。"批判"と書いたが、決して悪口ではなく、愛情の裏返しのコメントだ。私には、このコメントは現代日本の企業経営における無能さを著した的確な批判だと思ったね。経営者としてやるべきことをせずに、優秀な部下たちを鞭で叩くことが"経営"だと勘違いしている安楽に堕した日本の経営者(すべてとは言わない)そのものだよ。例えば、倒産寸前だったシャープが外資の門下に下った途端に、なぜ元気になるの?日産自動車もそうだった。これって日本の経営者の無能さを表している何よりの証拠じゃないだろうか? このことはエディー・ジョンズの著作を読んだ時にも感じた。
これら以外にも、今の私にササッたコメントがあった。
文化を共有しない外国との交渉は、相手側が思わず苦笑して、ヤラレタネ、と思ったときからスタートすべきなのである。理で対して行くのは、その後なのだ。
偏差値教育が大勢を見極める能力のない指導者を育てたのと同じに、点数至上主義は、スポーツの醍醐味を味わわせてくれる選手を、競技の場から排除していくようになるだろう。ポイント主義は単に勝者を決める手段であったはずである。だが、それのみが偏重されるようになると、手段の目的化になってしまう。










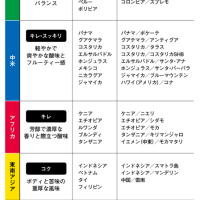
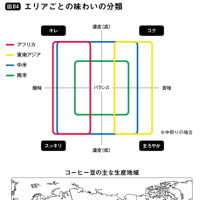













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます