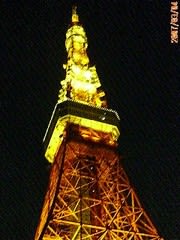「ミスター円」と言われた元財務官の榊原英資さんは、外交交渉の合間に相当美味しいものを食べ歩いたに違いない。そして、その経験と食に対する思いがこの著書の根底にあることは想像に難くない。
食を「資源」として捉える国々と「文化」として捉える国々とがある、と著者は言う。前者はイギリスやアメリカなどのアングロサクソン系、後者はフランス、イタリアなどのラテン系や中国。日本はもちろん後者のグループに属する。
食を「文化」として捉える国であっても、フランスや中国とは異なり日本の食文化の特色は「季節感」と「非効率」と言う。「季節感」はよく指摘される。旬を大事にして、季節の折々に採れる食材の持ち味を活かして調理する。バターやクリームで濃厚に味付けすることによって、素材の味が分からなってしまうフランス料理とは明らかに異なる料理法を発展・進化させた国であることは我々は気づいている。そして、この独自の料理感はフランス料理にも取り入れられ「ヌーベル・キュイジーヌ」という潮流になっていく。別の人から聞いた話だが、フランスの高級料理店では日本人シェフがいないと困るらしい。日本人シェフの持つ料理センスと繊細な盛り付け技能がミシュランの星取りに不可欠だからだとのこと。そして、榊原氏は訪れた北京の高級ホテル、グランドハイアットのバー内に寿司バーが設置され、流行を追う地元の若者たちで混んでいたことを見て驚いている。「もし、無人島で暮らすことになったとしたら、何料理のコックを連れて行きたい?」という他愛もない質問が昔あり、多くの人が「中国料理」と答えていたのに対して納得していた記憶がある私として、あれだけの調理法とメニュー、レシピがある中国の最先端のバーでsushiが人気になっているとは想像だにしなかった。
生魚を切っただけ、と言われ勝ちな料理ではあるが、「活け締め」の技術がなければ新鮮な魚を愉しめる寿司や刺身が可能にならず、ほとんどの国々で採られた魚は市場に来るときにはすでに痛んでいると言う。だからこそ、香辛料が貿易で求められたのだろうし、新鮮でない食材を美味しく食べるための技術として濃厚ソースが生まれる必要があった。それはそれで美味しい料理に発展したのであろうが、素材自体が持つ絶妙な味わいを愉しむ食文化には進化することはなかった。
食材にこだわることと一汁十菜といわれるような多品種の食材を使用する日本食は、規格大量生産が出来ないために効率とは対極にある、とも指摘している。食を「資源」と捉えるアングロサクソン系では、物事をシステムとして捉えて効率化した結果、植民地時代のプランテーション経営により英国は世界を制覇でき、今ではアメリカが大量の資本投下とオートメーションによる経済効率の追求の結果として世界経済を支配できているのだと指摘している。マクドナルドの世界進出もこの論理の線上で語ることができるのでしょうね。
しかし、ファーストフードに代表される「食の工業化」によって、肥満や糖尿病の蔓延、狂牛病の発正(この本は2006年に出されている)という恐ろしい結果がもたらされている現状を見ると、効率化を追求する食文化から古来の日本が持っていた食のあり方に回帰すべきであると榊原氏は考えている。「リ・オリエント」と氏が呼ぶムーブメントは、効率化と安さから健康や環境という「自然への回帰」を根底に持っている。スローフードのムーブメントもその一環であろう。「豊かさ」が表わすものは、安価ですぐに入手できるということではなくなり、例えば時間をかけてお茶を淹れるという非効率ではあるがお茶がはいるまでの時間を愉しんだり大量生産された規格品では望めないお茶本来の味わいを愉しむといったことににシフトしてきている、またそう考えて生活を愉しむべきだ、というのが著者の意見である。(もちろん、そんなことが許されるのは効率化によって金銭的に豊かになった国ならではの特権ではあろうが。)
この考え方には同意できるね。単に夕食を作るという義務としての「作業」ではなく、美味しく食べてくれる子供たちの笑顔を思い浮かべながら、クッキング自体を愉しむのが最近の週末の営みになっている私には、「そうそう」と思い、いいねボタンを押したくなる、そんな本でした。
著書の中にあったことで知らなかったこととして、
● 縄文遺跡の発掘によって縄文人がどんぐりを発行させて造った縄文みそとでも呼べる調味料を食べていたこと(へぇ、大陸から伝わったものばかりではなかったんだ)
● 17世紀後半の江戸時代には料理屋が生まれて18世紀半には外食文化が浸透していたこと(パリでレストランが広まったのも18世紀半ばというから、ほぼ同時期だったんだ。へぇ×へぇ)
● 産業革命の前段には農業革命が必要で、江戸時代の各藩では干拓を努める他にも、砂糖や生糸などの商品作物生産を奨励したり、陶磁器や紙、蠟といった特産品の育成といった殖産興業を進めた結果、農村の生産性が高まり農業革命が起こっていたこと(へぇ×へぇへぇ)
は知識の小ネタになった反面、「ブランド化」という観点ではフランス料理やイタリア料理、中国料理に比べて今イチ劣っていると感じられるのはなぜなのだろうか??という疑問が残りました。
この疑問は日本食・料理に限ったことだけではなく、優れた技術や技能を持っている日本の生産品、下町の工場が持つ「ここでしか造れない」製品や、日本古来の職人が織り成す産物がなぜブランドと成りえていないのか、と同じ疑問です。一例では、オニヅカのスニーカーから生まれたNIKEが世界的なブランドになっているのに、元のオニヅカのブランド力は何なのか、その違いはどこから生まれているのか?といったら理解してもらえるのかと思います。決してCMのクリエイティブだけではないはずで、ブランドになれたものとなれなかったものの違いはどこにあるのか??という疑問を想起させてくれた本でした。
食を「資源」として捉える国々と「文化」として捉える国々とがある、と著者は言う。前者はイギリスやアメリカなどのアングロサクソン系、後者はフランス、イタリアなどのラテン系や中国。日本はもちろん後者のグループに属する。
食を「文化」として捉える国であっても、フランスや中国とは異なり日本の食文化の特色は「季節感」と「非効率」と言う。「季節感」はよく指摘される。旬を大事にして、季節の折々に採れる食材の持ち味を活かして調理する。バターやクリームで濃厚に味付けすることによって、素材の味が分からなってしまうフランス料理とは明らかに異なる料理法を発展・進化させた国であることは我々は気づいている。そして、この独自の料理感はフランス料理にも取り入れられ「ヌーベル・キュイジーヌ」という潮流になっていく。別の人から聞いた話だが、フランスの高級料理店では日本人シェフがいないと困るらしい。日本人シェフの持つ料理センスと繊細な盛り付け技能がミシュランの星取りに不可欠だからだとのこと。そして、榊原氏は訪れた北京の高級ホテル、グランドハイアットのバー内に寿司バーが設置され、流行を追う地元の若者たちで混んでいたことを見て驚いている。「もし、無人島で暮らすことになったとしたら、何料理のコックを連れて行きたい?」という他愛もない質問が昔あり、多くの人が「中国料理」と答えていたのに対して納得していた記憶がある私として、あれだけの調理法とメニュー、レシピがある中国の最先端のバーでsushiが人気になっているとは想像だにしなかった。
生魚を切っただけ、と言われ勝ちな料理ではあるが、「活け締め」の技術がなければ新鮮な魚を愉しめる寿司や刺身が可能にならず、ほとんどの国々で採られた魚は市場に来るときにはすでに痛んでいると言う。だからこそ、香辛料が貿易で求められたのだろうし、新鮮でない食材を美味しく食べるための技術として濃厚ソースが生まれる必要があった。それはそれで美味しい料理に発展したのであろうが、素材自体が持つ絶妙な味わいを愉しむ食文化には進化することはなかった。
食材にこだわることと一汁十菜といわれるような多品種の食材を使用する日本食は、規格大量生産が出来ないために効率とは対極にある、とも指摘している。食を「資源」と捉えるアングロサクソン系では、物事をシステムとして捉えて効率化した結果、植民地時代のプランテーション経営により英国は世界を制覇でき、今ではアメリカが大量の資本投下とオートメーションによる経済効率の追求の結果として世界経済を支配できているのだと指摘している。マクドナルドの世界進出もこの論理の線上で語ることができるのでしょうね。
しかし、ファーストフードに代表される「食の工業化」によって、肥満や糖尿病の蔓延、狂牛病の発正(この本は2006年に出されている)という恐ろしい結果がもたらされている現状を見ると、効率化を追求する食文化から古来の日本が持っていた食のあり方に回帰すべきであると榊原氏は考えている。「リ・オリエント」と氏が呼ぶムーブメントは、効率化と安さから健康や環境という「自然への回帰」を根底に持っている。スローフードのムーブメントもその一環であろう。「豊かさ」が表わすものは、安価ですぐに入手できるということではなくなり、例えば時間をかけてお茶を淹れるという非効率ではあるがお茶がはいるまでの時間を愉しんだり大量生産された規格品では望めないお茶本来の味わいを愉しむといったことににシフトしてきている、またそう考えて生活を愉しむべきだ、というのが著者の意見である。(もちろん、そんなことが許されるのは効率化によって金銭的に豊かになった国ならではの特権ではあろうが。)
この考え方には同意できるね。単に夕食を作るという義務としての「作業」ではなく、美味しく食べてくれる子供たちの笑顔を思い浮かべながら、クッキング自体を愉しむのが最近の週末の営みになっている私には、「そうそう」と思い、いいねボタンを押したくなる、そんな本でした。
著書の中にあったことで知らなかったこととして、
● 縄文遺跡の発掘によって縄文人がどんぐりを発行させて造った縄文みそとでも呼べる調味料を食べていたこと(へぇ、大陸から伝わったものばかりではなかったんだ)
● 17世紀後半の江戸時代には料理屋が生まれて18世紀半には外食文化が浸透していたこと(パリでレストランが広まったのも18世紀半ばというから、ほぼ同時期だったんだ。へぇ×へぇ)
● 産業革命の前段には農業革命が必要で、江戸時代の各藩では干拓を努める他にも、砂糖や生糸などの商品作物生産を奨励したり、陶磁器や紙、蠟といった特産品の育成といった殖産興業を進めた結果、農村の生産性が高まり農業革命が起こっていたこと(へぇ×へぇへぇ)
は知識の小ネタになった反面、「ブランド化」という観点ではフランス料理やイタリア料理、中国料理に比べて今イチ劣っていると感じられるのはなぜなのだろうか??という疑問が残りました。
この疑問は日本食・料理に限ったことだけではなく、優れた技術や技能を持っている日本の生産品、下町の工場が持つ「ここでしか造れない」製品や、日本古来の職人が織り成す産物がなぜブランドと成りえていないのか、と同じ疑問です。一例では、オニヅカのスニーカーから生まれたNIKEが世界的なブランドになっているのに、元のオニヅカのブランド力は何なのか、その違いはどこから生まれているのか?といったら理解してもらえるのかと思います。決してCMのクリエイティブだけではないはずで、ブランドになれたものとなれなかったものの違いはどこにあるのか??という疑問を想起させてくれた本でした。