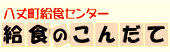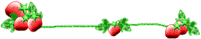

昨年の節分は快晴でした。
節分の朝に、屋上で八丈富士を眺めながら恵方巻を食べました。
そちらの方角が恵方だったからです。
今年はあいにくの雨時化模様ですね。南風でしょうか?
温かく湿った風がビュービューと吹きつけています。
今年の恵方は、南南東ですよ。
今年は二階の窓から海を眺めながら恵方巻を食べました。
お天気がいいと南の方角には青ヶ島が見えます。
青ヶ島には、ブログのお友だちaura*ちゃんがいます。
いつもこのブログを見て、
「八丈島にはいろんなものが売っていて、いいな」
といってくれるaura*ちゃん。
青ヶ島には恵方巻は売っているでしょうか?
そんなことを考えながら、「あさぬま」の恵方巻を食べました。
aura*ちゃんのことだから、おいしい恵方巻を巻いていることでしょう。

「あさぬまの恵方巻」
あさぬまの恵方巻は、ほんとにおいしいですよ。おすすめです。
昨年の節分には、朝に「あさぬま」の恵方巻をいただき、
夜には自分で巻いた恵方巻をいただきましたが、
今年はちょっと忙しいので、「あさぬま」のだけです。
これで充分満足です。



あいにくのお天気にもかかわらず、「あさぬま」駐車場は、
朝から車でいっぱいでした。ありがとうございます。

恵方巻の写真を撮ろうと思ったら、次から次に手が伸びてきて‥
みるみる恵方巻きの山が崩れていきます。
恵方巻をいただく習慣も一般的になりましたね。
お惣菜部が早朝より気合いを入れて恵方巻を巻いております


どんどんお買い求めくださいね。よろしくお願いいたします。
 節分
節分  クリック
クリック
節分とは読んで字のごとし、季節を分けるの意味です。
立春・立夏・立秋・立冬の前日を「節分」といいます。
明日が立春なので、今日が節分なんですね。
現代では節分に「鬼は外!福は内!」と豆をまきますが、これは
平安時代に宮中で行われていた鬼払いの儀式が発展したようです。
また、節分の夕方には、柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を刺したものを
戸口に立てておいたりします。
縄に柊やイワシの頭を付けた物を門に掛けたりする地方もあります。
昔から季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられていて、
それを追い払うためのおまじないですね。
八丈島の節分の儀式で忘れてならないのは「厄落とし」です。
家族に厄年の人がいる家庭では、今日は「厄落とし」をする日です。
家に人を招いてご馳走をし、みんなに少しずつ厄を分けるんですよ。
そんな風習が八丈島では現在も続いています。
わたしもこれに何度かおよばれしましたが、大変なご馳走です。

たぶん島外の方々がご覧になったら「なにごと!?」と驚くはず。
こうして大御馳走と引き換えに厄を少しだけお持ち帰りして、
厄年の人をみんなで守るわけなんですね。
気持ちの温かくなる風習ですね。

そして、厄年の人は道辻にも厄を落としに行きます。
女性は櫛やお裁縫道具なんかを早朝に道の角に落としてきます。
これはお年寄りが拾っていきます。
もう厄を拾ってもかまわないよ、というお年寄りが、
若い人たちの厄を引き受けてくださるわけです。
これも心温まる話です。

おねいさんが子どもの頃には、学校へ行く道でこれを見かけました。
今でも続いているでしょうか?
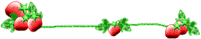


 節分祭の特売チラシは、こちらです。
節分祭の特売チラシは、こちらです。
 さがほのかリカちゃんオリジナル・プレゼント!は、こちら。
さがほのかリカちゃんオリジナル・プレゼント!は、こちら。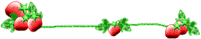












 そして、知らないかたはごめんなさい、
そして、知らないかたはごめんなさい、 ◎
◎