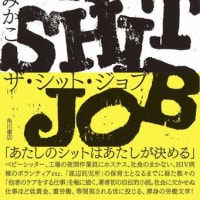2015年に読んだ本のベスト5
 今年もベスト5を挙げる日が来た。今年は52冊の本を読んだ。小説がめっきり少なくなっている。映画と同じで、読んでみたけれど(映画館に見に行ったけれど)つまらなかったという経験をしたくないので、ついついよく売れている小説に向かう。すると図書館では長い間待たなければ順番が回ってこない。そのうちどうでもよくなってきて、ついつい興味深いタイトルの評論系に行ってしまう。それと小説の作品世界に入るのがだんだん面倒になってきている。作品世界にすーと入り込めないのだ。作品のせいにしているが、本当のところはどうなのだろうか。
今年もベスト5を挙げる日が来た。今年は52冊の本を読んだ。小説がめっきり少なくなっている。映画と同じで、読んでみたけれど(映画館に見に行ったけれど)つまらなかったという経験をしたくないので、ついついよく売れている小説に向かう。すると図書館では長い間待たなければ順番が回ってこない。そのうちどうでもよくなってきて、ついつい興味深いタイトルの評論系に行ってしまう。それと小説の作品世界に入るのがだんだん面倒になってきている。作品世界にすーと入り込めないのだ。作品のせいにしているが、本当のところはどうなのだろうか。
1.白井聡『永続敗戦論』(太田出版、2013年)
戦後日本の根本的な異常さ―アメリカの従属国―をえぐりだし、読者に突きつけてくる衝撃の本。この現実を直視して、真の独立国となることから再出発しなければ、日本の将来はない。
2.須田桃子『捏造の科学者』(文藝春秋、2014年)
2014年を騒がせたSTAP細胞事件を詳細にまとめたジャーナリストの本。この事件のもう一人の渦中の人であった理研の笠井氏や若山氏ともメールをやり取りをする間柄だったジャーナリストだけに、当事者たちが公の場では言えないことをメールから読み取るなど、心の裏まで読み込んだ本だが、それでもまた小保方さんと笠井氏の心は闇の中だ。
3.呉善花『韓国併合への道』(中公新書、2006年)
いま「朝鮮ガンマン」という韓国ドラマを見ているが、その舞台はまさにこの本で扱われている開国前夜の朝鮮である。まだ開国派の人たちが、すでに明治維新によって近代化に歩みだした日本を手本として見習って、開明派の25代国王高宗を中心にして改革を行おうとしている矢先である。その朝鮮の朝廷内部がどんなふうになっていたか、どうやって開明派が潰されていったかを詳細にまとめた本である。
4.菊地成孔+大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校』(河出文庫、2010年)
なんだか誤解を受けそうなタイトルの本だが、バークリー・メソッドと呼ばれる音楽教育システムを解説しながら、音楽を分析するにはどうやってするのかを、バークリー・メソッドの原点にある12等分平均律が確立されるまでの平均律の歴史をおさらいしながら、実践的に説明している、実に興味深い本である。
5.松本薫『天の蛍』(江府町観光協会、2015)
米子で高校の国語教師をしながら、米子周辺を舞台にした小説を書いている松本薫さんの新作で、江尾という城下町を舞台にして、毛利元就が中国の覇者となるべく尼子氏と最後の戦いをしていた時代に生きた少女を中心として、当時の城主であった蜂塚氏の城下の人々を描き、この時代から現在にまで続く江尾の夏の風物詩である「十七夜」という夏祭りをモチーフにした時代劇である。
 今年もベスト5を挙げる日が来た。今年は52冊の本を読んだ。小説がめっきり少なくなっている。映画と同じで、読んでみたけれど(映画館に見に行ったけれど)つまらなかったという経験をしたくないので、ついついよく売れている小説に向かう。すると図書館では長い間待たなければ順番が回ってこない。そのうちどうでもよくなってきて、ついつい興味深いタイトルの評論系に行ってしまう。それと小説の作品世界に入るのがだんだん面倒になってきている。作品世界にすーと入り込めないのだ。作品のせいにしているが、本当のところはどうなのだろうか。
今年もベスト5を挙げる日が来た。今年は52冊の本を読んだ。小説がめっきり少なくなっている。映画と同じで、読んでみたけれど(映画館に見に行ったけれど)つまらなかったという経験をしたくないので、ついついよく売れている小説に向かう。すると図書館では長い間待たなければ順番が回ってこない。そのうちどうでもよくなってきて、ついつい興味深いタイトルの評論系に行ってしまう。それと小説の作品世界に入るのがだんだん面倒になってきている。作品世界にすーと入り込めないのだ。作品のせいにしているが、本当のところはどうなのだろうか。1.白井聡『永続敗戦論』(太田出版、2013年)
戦後日本の根本的な異常さ―アメリカの従属国―をえぐりだし、読者に突きつけてくる衝撃の本。この現実を直視して、真の独立国となることから再出発しなければ、日本の将来はない。
2.須田桃子『捏造の科学者』(文藝春秋、2014年)
2014年を騒がせたSTAP細胞事件を詳細にまとめたジャーナリストの本。この事件のもう一人の渦中の人であった理研の笠井氏や若山氏ともメールをやり取りをする間柄だったジャーナリストだけに、当事者たちが公の場では言えないことをメールから読み取るなど、心の裏まで読み込んだ本だが、それでもまた小保方さんと笠井氏の心は闇の中だ。
3.呉善花『韓国併合への道』(中公新書、2006年)
いま「朝鮮ガンマン」という韓国ドラマを見ているが、その舞台はまさにこの本で扱われている開国前夜の朝鮮である。まだ開国派の人たちが、すでに明治維新によって近代化に歩みだした日本を手本として見習って、開明派の25代国王高宗を中心にして改革を行おうとしている矢先である。その朝鮮の朝廷内部がどんなふうになっていたか、どうやって開明派が潰されていったかを詳細にまとめた本である。
4.菊地成孔+大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校』(河出文庫、2010年)
なんだか誤解を受けそうなタイトルの本だが、バークリー・メソッドと呼ばれる音楽教育システムを解説しながら、音楽を分析するにはどうやってするのかを、バークリー・メソッドの原点にある12等分平均律が確立されるまでの平均律の歴史をおさらいしながら、実践的に説明している、実に興味深い本である。
5.松本薫『天の蛍』(江府町観光協会、2015)
米子で高校の国語教師をしながら、米子周辺を舞台にした小説を書いている松本薫さんの新作で、江尾という城下町を舞台にして、毛利元就が中国の覇者となるべく尼子氏と最後の戦いをしていた時代に生きた少女を中心として、当時の城主であった蜂塚氏の城下の人々を描き、この時代から現在にまで続く江尾の夏の風物詩である「十七夜」という夏祭りをモチーフにした時代劇である。