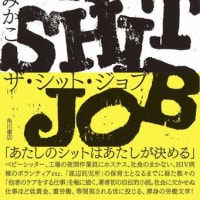須田桃子『捏造の科学者』(文藝春秋、2014年)
 2014年2月から8月まで世間を騒がせたSTAP細胞事件を毎日新聞の科学部の記者がまとめた本である。図書館の順番待ちが100近くあって、完全に事件の熱も冷めて、小保方さんて誰と言われそうな時期にやっと読めるようになったが、私の関心は衰えておらず、一気に読みきった。
2014年2月から8月まで世間を騒がせたSTAP細胞事件を毎日新聞の科学部の記者がまとめた本である。図書館の順番待ちが100近くあって、完全に事件の熱も冷めて、小保方さんて誰と言われそうな時期にやっと読めるようになったが、私の関心は衰えておらず、一気に読みきった。
いろんなことが頭をよぎって、どうまとめたらいいのか分からない。昨日も電車のなかでどう書こうかあれこれ考えたのだが、結局まとまらなかった。だからまとまりのないものになりそう。
事件が起きたときから私も強い関心をもってテレビを見ていた。弱酸性の刺激を与えるだけで何にでも変化する万能性をもった細胞になるって本当だろうか、もし本当だとしたら、すごい発見だ。しかも若干30才でそんなことを発見するなんてという驚きだった。
もちろん発表の時に脇を固めていた笠井・若山両氏がそれぞれの専門分野でどれほど世界的な権威なのかも知らなかったが、すごい人達なんだろうなと思いながらテレビを見ていた。私でさえも、あのips細胞なんか霞んで見えるような時期があったくらいだから、相当なフィーバーぶりだったことが思い出される。
そして一週間も経たないうちに次々と論文の問題点が報じられて、あっという間に火だるまになった。私はかなり遅い時期まで小保方さんを支持していた。私が4月に書いたブログはこちら。この本でも笠井氏が自殺する少し前に無念のように語っていたということだが、小保方さんに再現実験をやらせてみたらいいじゃないかと思っていたからだ。論より証拠だ。論文の画像が修正してあったり、過去のものが使ってあったり、文章がコピペであっても、肝心のSTAP細胞発生を実験で実際にやって見せたら、そんな議論は吹っ飛んでしまうだろう、と思ったのだが、理研はなかなかそれをさせなかった。結局どうなったのだろうか。
このあたりが素人と専門家では違うようだ。この本でも繰り返し、論文が体をなさないことが暴露されたのだから、もうSTAP細胞の再現実験など問題外だということが出てくる。そこが人文系と自然科学系の論文の違いのような気が素人にはするのだが。だって上にも書いたように、実際にやって見せたら、それが最大の証拠ではないかと思うからだ。
それにしても、一番可能性が高いのはES細胞が混ざったということらしいが、最初は偶然だったとしても、何度も成功したという小保方さんはどこかで意図的にES細胞を入れるようになったのだろう。小保方さんの研究室の冷蔵庫にはES細胞もあったということなので、意図的に使った可能性が高い。結局最後に思うのは、どんな精神状態でそうしたのだろうか、ということだ。しかし会見を見るかぎりでは、本当に信じ込んでいるように見えた。そんな風に自分を信じこませるしかなかったということだろうか。
そういえば考古学でも石器を自分で埋めて、発掘したかのように発表していた人もいたな。これも長い間専門家でさえも騙されていたのだ。結局、どんな専門家でも、きちんとした手順を踏まないと騙されるということなのだろう。
きっと最初に彼女の話を聞いた専門家が、疑問を抱いて、それを彼女に確認させていたら、こんなことにはならなかったのだろうなと思う。
 2014年2月から8月まで世間を騒がせたSTAP細胞事件を毎日新聞の科学部の記者がまとめた本である。図書館の順番待ちが100近くあって、完全に事件の熱も冷めて、小保方さんて誰と言われそうな時期にやっと読めるようになったが、私の関心は衰えておらず、一気に読みきった。
2014年2月から8月まで世間を騒がせたSTAP細胞事件を毎日新聞の科学部の記者がまとめた本である。図書館の順番待ちが100近くあって、完全に事件の熱も冷めて、小保方さんて誰と言われそうな時期にやっと読めるようになったが、私の関心は衰えておらず、一気に読みきった。いろんなことが頭をよぎって、どうまとめたらいいのか分からない。昨日も電車のなかでどう書こうかあれこれ考えたのだが、結局まとまらなかった。だからまとまりのないものになりそう。
事件が起きたときから私も強い関心をもってテレビを見ていた。弱酸性の刺激を与えるだけで何にでも変化する万能性をもった細胞になるって本当だろうか、もし本当だとしたら、すごい発見だ。しかも若干30才でそんなことを発見するなんてという驚きだった。
もちろん発表の時に脇を固めていた笠井・若山両氏がそれぞれの専門分野でどれほど世界的な権威なのかも知らなかったが、すごい人達なんだろうなと思いながらテレビを見ていた。私でさえも、あのips細胞なんか霞んで見えるような時期があったくらいだから、相当なフィーバーぶりだったことが思い出される。
そして一週間も経たないうちに次々と論文の問題点が報じられて、あっという間に火だるまになった。私はかなり遅い時期まで小保方さんを支持していた。私が4月に書いたブログはこちら。この本でも笠井氏が自殺する少し前に無念のように語っていたということだが、小保方さんに再現実験をやらせてみたらいいじゃないかと思っていたからだ。論より証拠だ。論文の画像が修正してあったり、過去のものが使ってあったり、文章がコピペであっても、肝心のSTAP細胞発生を実験で実際にやって見せたら、そんな議論は吹っ飛んでしまうだろう、と思ったのだが、理研はなかなかそれをさせなかった。結局どうなったのだろうか。
このあたりが素人と専門家では違うようだ。この本でも繰り返し、論文が体をなさないことが暴露されたのだから、もうSTAP細胞の再現実験など問題外だということが出てくる。そこが人文系と自然科学系の論文の違いのような気が素人にはするのだが。だって上にも書いたように、実際にやって見せたら、それが最大の証拠ではないかと思うからだ。
それにしても、一番可能性が高いのはES細胞が混ざったということらしいが、最初は偶然だったとしても、何度も成功したという小保方さんはどこかで意図的にES細胞を入れるようになったのだろう。小保方さんの研究室の冷蔵庫にはES細胞もあったということなので、意図的に使った可能性が高い。結局最後に思うのは、どんな精神状態でそうしたのだろうか、ということだ。しかし会見を見るかぎりでは、本当に信じ込んでいるように見えた。そんな風に自分を信じこませるしかなかったということだろうか。
そういえば考古学でも石器を自分で埋めて、発掘したかのように発表していた人もいたな。これも長い間専門家でさえも騙されていたのだ。結局、どんな専門家でも、きちんとした手順を踏まないと騙されるということなのだろう。
きっと最初に彼女の話を聞いた専門家が、疑問を抱いて、それを彼女に確認させていたら、こんなことにはならなかったのだろうなと思う。