今日(2024.6.28)の『読売新聞』「言の葉 巡り」に“「右」どうやって説明?編集委員 伊藤剛寛“、が掲載されていました。以下転載します。
ホームセンターの園芸コーナーでアサガオの苗を買った。つるが支柱に巻き付きながら育ってていく。方向はアサガオならどれも同じ。これは、左巻きなのか、右巻きなのか。
上から見ると左巻き、下から見ると右巻き。左右は、上下と違って相対的だ。
日本植物生理学会のサイトによると、アサガオのつるは長い間、左巻きと呼ばれていたそうだ。しかし、現在は、時計回りに伸びていく場合を 「右巻き」と定義し、アサガオはこれに当たるという。ひもをイラストの方向に棒に巻き、下(根元側)から見て確認したが、少々混乱した。
右と左の関係はややこしい。「円の右半分」と言えば向かって右側だが、円に両目を描くと、右目は向かって左。自動車や電車の左右は進行方向が基準となり、向かって左に見えても右ハンドルと言う。鏡に映った姿は「左右が反転している」とされるが、右手を挙げると、鏡の中でも右側の手が挙だっている。反転はしていないとも言えそうだ。
「右」の説明は難しく、国語辞典の語釈がバラエティーに富んでいることはよく知られる。「南を向いた時、西にあたる方」(広辞苑)、「『一』の字では、書き終わりのほう。
『リ』の字では、線の長いほう」(三省堂国語辞典)、「人体を対称線に沿って二分したとき、心臓のない方」 (明鏡国語辞典)などだ。今年刊行された「三省堂現代新国語辞典第七版」は、「視線の方向で引いた基準線」という考えを用い、例えば「松」の「公」に当たる部分だと新たな説明を試みている。
辞書編集部を舞台にしたベストセラー「舟を編む」 (三浦しをん著、光文社)は、今年放映されたドラマ版(NHK)もすばらしかった。女性編集部員が自分なりの右を考えるよう勧められる。「朝日を見ながら泣いたとき、暖かい風に吹かれて、先に涙が乾く側のほっぺた」。失恋し、海辺に立った際の体験が、詩的な右になった。当方に浮かんだのは、「『アサヒ』を見て、『スーパー』ではなく『ドライ』の文字がある側」という即物的な右。
さて、皆さんにとっての 「右」は? (月I回掲載)
ホームセンターの園芸コーナーでアサガオの苗を買った。つるが支柱に巻き付きながら育ってていく。方向はアサガオならどれも同じ。これは、左巻きなのか、右巻きなのか。
上から見ると左巻き、下から見ると右巻き。左右は、上下と違って相対的だ。
日本植物生理学会のサイトによると、アサガオのつるは長い間、左巻きと呼ばれていたそうだ。しかし、現在は、時計回りに伸びていく場合を 「右巻き」と定義し、アサガオはこれに当たるという。ひもをイラストの方向に棒に巻き、下(根元側)から見て確認したが、少々混乱した。
右と左の関係はややこしい。「円の右半分」と言えば向かって右側だが、円に両目を描くと、右目は向かって左。自動車や電車の左右は進行方向が基準となり、向かって左に見えても右ハンドルと言う。鏡に映った姿は「左右が反転している」とされるが、右手を挙げると、鏡の中でも右側の手が挙だっている。反転はしていないとも言えそうだ。
「右」の説明は難しく、国語辞典の語釈がバラエティーに富んでいることはよく知られる。「南を向いた時、西にあたる方」(広辞苑)、「『一』の字では、書き終わりのほう。
『リ』の字では、線の長いほう」(三省堂国語辞典)、「人体を対称線に沿って二分したとき、心臓のない方」 (明鏡国語辞典)などだ。今年刊行された「三省堂現代新国語辞典第七版」は、「視線の方向で引いた基準線」という考えを用い、例えば「松」の「公」に当たる部分だと新たな説明を試みている。
辞書編集部を舞台にしたベストセラー「舟を編む」 (三浦しをん著、光文社)は、今年放映されたドラマ版(NHK)もすばらしかった。女性編集部員が自分なりの右を考えるよう勧められる。「朝日を見ながら泣いたとき、暖かい風に吹かれて、先に涙が乾く側のほっぺた」。失恋し、海辺に立った際の体験が、詩的な右になった。当方に浮かんだのは、「『アサヒ』を見て、『スーパー』ではなく『ドライ』の文字がある側」という即物的な右。
さて、皆さんにとっての 「右」は? (月I回掲載)













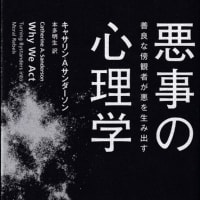
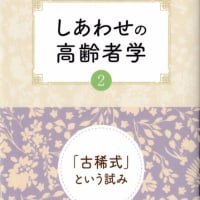


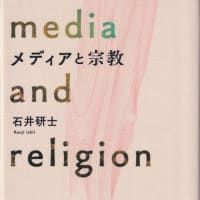

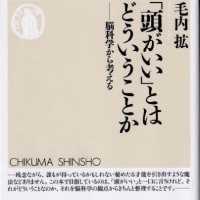
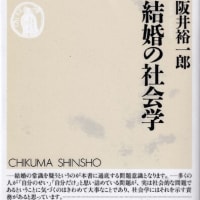
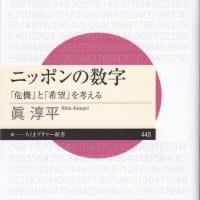






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます