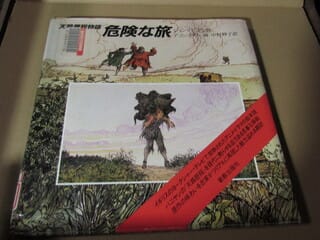昨年の今頃「バングラデシュの衣料工場で働く若い女工たち」という映画を見てから、ずっと見たいと思っていた映画「ザ・トゥルー・コスト」をやっと見ることができました。映画「バングラデシュの衣料工場で働く若い女工たち」 - アンティマキのいいかげん田舎暮らし (goo.ne.jp)
「バングラデシュの衣料工場で働く若い女工たち」は、ファストファッションを支える中進国、後進国の現場の女工さんたちの実態を描いたものですが、「ザ・トゥルー・コスト」は、ファストファッションをつくりだす欧米のアパレルメーカーをはじめとする先進国の巨大企業のあり方、そして先進国の消費者たちに焦点を当てて、ファストファッション業界全体の不気味に思えるようなシステムを鋭くえぐっています。
クラウドファンディングで実現した映画だそうですが、編集が素晴らしく、そうとう高度の技術と知性が駆使されてできた映画だなと思いました。

さて、ファストファッションという言葉を知ったのは10年くらい前。ちょっとしゃれたスカートやパンツが、何千円かで買えてしまい、上から下までコーディネイトして占めて1万円以内、とかいうのを競うテレビ番組もあった気がします。その頃はすでに田舎に移住していて、都会で仕事をしていた時に必要だったスーツやスカートジャケットなどが全くいらなくなったので、さほど興味は持たなかったのですが、たまに見かける衣類の安さには驚いていました。
「安い衣類の製造が可能になったのは、世界がグローバル化したため」と映画でははっきり言っています。30年ほど前、少し安い衣類が出回り始めたころは中国製が主でした。でもその中国の人件費が上がり始めると、タイやベトナム、バングラデシュなどに生産の拠点が移されました。
原材料が同じで、より安い衣類を作るには、製造コストを下げるしかない。メーカーはより安い製造場所を求めて、わたりあるきます。第三世界の国々にある小企業では、その大手の圧力に抗することはできません。バングラデシュのある縫製工場主は、「5ドルを4ドルに、さらに3ドルに下げろといわれたら従うしかない。注文が欲しいから」といいます。しわ寄せは当然、女工さんたちに来ます。
「バングラデシュの・・・」にも出てきた、ラナ・プラザ事件は2013年に起きました。8階建てのビルがある日突然崩壊し、死者1100人以上、行方不明者500人という大惨事をもたらしました。このビルには縫製工場も多数入っていて、工員たちは前々から工場主に建物の不備を指摘していました。当日も変な音がすると訴えていたのです。にもかかわらず工場主は仕事をいつも通り続けるよう命令しました。そして事件が起きたのです。
この映画は、ラナ・プラザ事件をきっかけにファストファッションの舞台裏を追及するために作られました。
ファストファッションの大手メーカーの広報担当者たち何人かにインタビューするシーンがあります。彼らが異口同音にいうことは、「現地で働く女性たちは、ほかよりましな仕事場を与えられている。もしあの職場がなかったら、さらに苦しいはずだ」つまり、自分たちは無罪で、むしろ働く場所を与えてやっているからいいのだ、と自分たちの立場を擁護します。少し目が泳ぎ、言い淀んでいるように見えましたが。
映画の中盤でナレーターはこんなことを語ります。
「世界の人々はみんな貧しくなった。高い商品~車や家は手が届かない。でも、安い服なら買える。ファストファッション業界は毎週のように新製品を売り出し、人々は買いあさる」
高いものを買うだけのお金の余裕のない憂さを、一枚のちょっと変わったデザインの新しいTシャツを買うことで晴らすのでしょう。でも、その憂さ晴らしは長く続きません。だからまた、翌週別の服を買う。こうしてクローゼットのなかは、いっぱいになります。心底好きになって買った服ではないので、満足感は得られません。そんな服ばかりがたまると、惜しげもなく捨ててしまいます。好きではないので、簡単に捨てられるのです。
まるで捨てるための服を買うようなものです。こういう感覚自体、すでにおかしい。
こうした先進国の人々のとめどない消費の欲求が、中進国、後進国の産業を変えてしまいました。ただし、この欲求は大企業によってつくられたもの。ファストファッションに振り回される消費者も、いわば大企業の被害者と言えると思います。
インドでは、土地に合わない綿花を育てるために、大量の化学肥料や農薬を必要とする農業に従事している人がほとんど。彼らは、農薬や化学肥料、仕方なく買わされる遺伝子組み換えの種子を手に入れるために借金をする。そして返済ができないため、自殺者が後を絶たないといいます。
皮革製品も、昔に比べたら驚くほどの安値で売られています。こういった商品も、やはり東南アジアなどの中進国で作られています。皮加工に使う六価クロムは劇薬。その劇薬を川に流すので、あたりの水田地帯は汚染され、飲料水も危険な状態になっているとか。皮膚病や手足のまひに悩む人が増えているのに、改善はなされていません。
「大地に敬意を払っていない」映画に登場するある人物がいったことばです。このことばで、涙があふれてきました。
服や靴のコストにかかる人件費を削り、必死に安く仕上げ、大企業は莫大な利益をあげてはいるのだけれど、大地や川を汚し、人々の健康を害して、ものすごい被害を与えています。彼らは、自然界、人間界へのストレスをものともせずに経済活動に邁進していますが、敬意を払われていない大地や人々にたいするリスクを計算したら、当然のことながら、1枚ののTシャツは500円や1000円などで買えるはずがないのです。
****
映画を見た数日後、豊田市内のフェアトレードショップ、アナムanam fair trade&natural (アナム フェアトレード&ナチュラル) | フェアトレードを初めとした、人や環境にやさしいエシカルな商品を取り扱うセレクトショップ (anam-jp.com)を訪ねました。店主の稲熊なつみさんは、昨年9月まで豊田松坂屋に店を持っていましたが、松坂屋の閉館のあと、もともとのお店にもどり、再出発なさいました。
彼女と、この映画の話をしました。彼女がアナムを始めたきっかけは、彼女自身が洋服が好きで、販売の仕事をしていたとき、始終安売りがつづき、ひどいときは75%オフになることもあるのを知って、「いったい元の原価はどうなっているんだろう」と疑問に思ったことだったそう。そののち、フェアトレードの存在を知るようになり、正当な金額を支払って作られた品々の良さに魅力を感じ、自らお店を持つことに決めたということです。
店内には、彼女が選んだ、健全なやりとりの上で発注縫製しているメーカーの洋服が並んでいます。現地で縫製している人たちの生活が成り立つというだけでなく、彼らの文化や伝統的な技術を生かすようデザインがくふうされています。
ただいまスプリングフェアの開催中。このところちゃんとした服などほぼ買ったことがなかったので、久しぶりに気に入った服があったらほしいなと思ってでかけたのですが、試着したもののうち、気に入ったのは2枚。1枚くらいなら買おうと思ってやってきたのに、どちらか1枚選ぶのが難しくなりました。
メーカーはどちらも京都にあるシサム工房です。工房では、現地の団体にあらかじめ布代を払いすべて買い取り。先方の負担が少なくて済むように配慮しています。そして小売店であるなつみさんたちも、1年前に商品の買取予約をし、生産者側のリスクが少ないように配慮するシステムになっています。「1年先の商品を買取予約するのは、小売店にとってはリスクが高いのですが、みんなが少しずつわけもって負担し、誰も苦しい思いをしないようにしているのです」となつみさん。
フェアトレードの品はときどき購入し、服も主にピープルツリーのものをセール時にネットで買うことはあるのですが、いちどきにそこそこの値段の服を2枚も買うなんて、ここ数年したことのないこと。そもそも古いけれど捨てられない服がたくさんあるし、友人のお古やお古とは言えないほぼ新品の衣類もたくさんもらっています。有り余るほどあるのにさらに一遍に2枚も買うの?としばし自問自答。しばらく迷いましたが、なつみさんの話を聞いているうちに、フェアな取引をして、持続可能の仕事を作っている人たちの輪に自分も入りたくなり、思い切って購入。夏服2枚新調です。
ところで、なつみさんからとても悲惨な話を聞きました。店内にかかっていた美しい白生地のエプロンにまつわる話です。
そのエプロンの生地は「カディ」とよばれるもので、手で紡いで手で織ったインドの昔ながらの極上の木綿生地だそう。インドがイギリスの植民地だったころ、イギリスは、いい綿花の採れるインドで綿花を作らせ、イギリスに輸出してイギリスの工場で織物にし、インドの市場でさばく、ということを強制していました。もともとインドにはすぐれた紡織の技術があるのに、禁止したのです。インドだけであまりにいい生地ができると、商売の邪魔になると考えたイギリス人は、インドのカディの職人の両手を切り落した、というのです。
ガンジーはこうしたイギリスの植民地政策に抵抗して、手紬ぎの道具を手で持って紡ぎながら無抵抗の行進を続けました。彼の有名な塩の行進の際、人々が着ていたのはこのカディで作った着物だそうです。
息が詰まりそうなひどい話です。弱小国が強国に蹂躙された時代の話ですが、いまは、大企業によって弱小国の人々は翻弄されています。でも、じつは翻弄されているのは中進国、後進国の人だけではないかもしれません。先進国の人々も、好きでもないのに消費するのが美徳とされ、流行に翻弄されているという点では、立場は同じかもしれません。
フェアトレードの活動は、世界全体の経済活動の中ではほんのわずかな部分しか占めていませんが、せめて自分の関われる範囲では、健全に作られた食べ物や衣類を選びたいものだなとおもったことでした。私が選んだにしては鮮やかな色の服2枚を抱えて、ささやかだけれど、健全な消費行動をわたしはきょうしたのだわ、といささか誇らしいような気持ちで帰路につきました。
ところで、アナムの稲熊なつみさんと田中真美子さん主催の「やさしいマルシェ」が、今週末の日曜日24日に、豊田市駅前のとよしばで開かれます。アンティマキも出店します。ぜひお越しください。