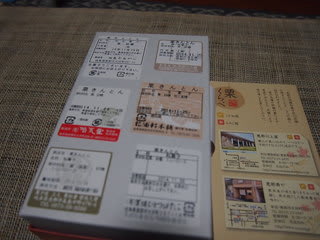確か昨年から実施されていた「食べるのこと 考える10の問い」という名のトークイベント。ほぼ毎月、種々の調味料を取り上げ、それぞれの専門家の話を聞き、製造所の見学をし、ちゃんと作られた調味料を味わって、その調味料を生かした料理に舌鼓を打つ、といった企画です。前から参加したいと思っていたのですが、いけずじまい。先週の日曜日、やっと念願かなって参加しました。
場所は、西尾市一色町の近々オープン予定のsubaco というカフェ。稲武からは2時間強の道のりでした。
今回のテーマは、塩。お話しくださったのは、三重県松本農園の松本清さん。自家農園の、みごとな南高梅を持参。まるであんずのようです。彼は、梅農家でもあり、梅干の作り手でもあります。そして、ソルトコーディネーターの肩書きもおもちです。

以下、彼と、イベントのコーディネーターの方の話をかいつまんで書きます。
「1905年に始まった塩の専売制度は、2005年まで続いた。専売制度は、単に自由な塩の販売ができなかっただけでなく、数回にわたる塩業整備のため、ナトリウム塩(塩化ナトリウムが95%だった会場含まれている塩のこと)しか塩と認められなくなった。そのため、全国各地にあった塩田がほぼ消滅した。1997年、ナトリウム塩以外の塩の流通がようやく認められ、その前から徐々に流通していた、ナトリウムの含有量が80%~90&以下の自然塩(おもに、輸入した天日塩を日本の海水に戻し、再結晶させた塩)が正式に販売できるようになった」
1905年に専売法が施行されたのには、食料難と衛生面での配慮という二つの大きな理由があったとのこと。ナトリウムの少ない塩は腐りやすいし、塩田で少量ずつ生産される塩は値段が高くなる。ナトリウム塩なら、大量生産が可能で、安価に供給できるというわけです。
でも、食料事情がよくなってもなお、この専売法が改正されないまま続行。わたしが「海の精」の存在を知った1980年代中頃、あの塩は普通の販売はできずに、研究会の会員を募ってその会員たちに渡すという形で、届けられていました。
「現在は、道の駅に行けば、必ずどこか地元の塩見つけることができるほど、塩の製造は自由化された。これらはいずれも、微量栄養素のマグネシウムやカルシウムが、ナトリウム塩(100年続いた専売公社の塩)よりかなり豊富にふくまれている」
「とはいえ、日本の塩の自給率は15%。飼料用、加工用はほとんど輸入品に頼っている」
松本さんが持参した塩のなめくらべは、たのしかった。ヌチマースは沖縄産。海の成分がそのまま濃縮され、結晶化した塩だそうで、いささか苦みが。奥能登揚浜の塩は、人力で海水をくみ上げ、塩田で乾燥させたもの。ナトリウム分は、ヌチマースより高め。
驚いたのは、ナトリウム分をどの程度にして塩の製造を進めるかは、職人のこだわりにかかっているということ。同じ塩でも、成分の表示が何%から何%と開きがあるところがあるのは、海水濃度の変化にもよるし、その濃度に合わせる職人の勘にもよるのだそう。

ところで、塩は人間の体にとても影響を与えるもの。暑い時出る汗の中身は、多くは水分。体は、塩分濃度を下げると危険なので、水分だけ出してしまうのだそう。熱中症の症状として、脱水症状があげられるのは、そのせい。冬でも、体が冷えると血液の塩分濃度を上げ、体温を上げようとするため、トイレに行く回数がふえるというわけです。
高血圧の人に医者がかならずといっていいほど勧める減塩。これがじつは、効果のない場合が結構あることを、今回初めて知りました。
「高血圧には、一次性高血圧と二次性高血圧がある。高血圧症の人のうち、一次性は約80%、二次性は約20%。二次性のほうは、複合的老化や遺伝によるものが多く、減塩によって血圧が左右されることは少ない」
「一次性高血圧の人は、食塩感受性といわれる体質の人が約4割を占めている。こちらは、少しの塩気で生きられ、塩をとりすぎると血圧が上がり、ナトリウムが体内に蓄積しやすい。そのため、彼らには減塩は効き目がある」
「しかし、残りの6割は、食塩抵抗性といわれる体質の人。塩を食べ過ぎても血圧は上がらず、減塩しても意味がない。減塩しても1割以下の変化しかなかったら、こちらの体質と判断される」
また、減塩による弊害も最近ではいろいろわかってきたそうで、高齢者が急激な減塩によって、認知症の症状が増すことがあるとも。
減塩するかわりに、化学調味料などの添加物を増やして、体にはかえってマイナスの要因になることもあるとの話には、おおいに納得。
自然塩の微量栄養素、それがおいしいだけでなく体にもいいとわたしは思っていましたが、松本さんに言わせれば、それは極めて些細な量だから、塩の違いでからだにいい悪いは判断できない、とのこと。
それより大事なのは、「食べ物との相関」。「マグネシウムの多い塩は、苦みが多い野菜に合うとか、岩塩は塩からいので脂身の多い肉を焼くときに使うといいとか、カリウムは酸味があるので、焼き魚に合うとか、料理や食材による使い分けをして、豊かな食事を彩ってほしい」

塩の話の後は、梅干の話。松本さんの農園では、南高梅をはじめ数種の梅を栽培しています。この日、持ってきてくださった梅干しは8種。5分搗きのおかゆに彼の付けた梅干を載せていただきました。外国産の塩で漬けた3種のほか、国産の塩3種、それと、3年物の梅干に、1年物のシソ入り梅干。
塩気が立っているように感じたのは、外国産の塩のような気がしますが、とりあえず、どれもおいしかった。
わたしはほとんどシソをいれてつけていましたが、入れないのも純粋に梅の味がわかって、なかなかいい。彼の梅干は、塩分濃度20%。大きい梅だと、23%にすることもあるとか。
わたしも、つける場合は、いつも20%の塩にしていますが、近頃は甘い梅干がいいという人が多いようです。その甘い梅干、調味梅干というのだそうですが、最初から塩気を控えて漬けるのでなく、普通に塩漬けした梅を水につけて塩気を抜き、それから蜂蜜とか甘味を加えて仕上げるのだとか。当然、腐りやすくやすくなるので、長期保存するとなると、防腐剤そのほかいろいろ添加物が必要になってきそう。
天日干しは、夏だと2日半ほど、秋だと4,5日。夏に天日干しができなかったら、秋に持ち越せばいいとはおもわなかった。いつもなんとか夏に干さないといけないと思って、あせっていましたが、ゆっくりかまえればいいようです。

梅干の効能は、食中毒予防のほかに、「血液の浄化作用があり、血液を中和して流れをよくする。胃の中のピロリ菌や虫歯菌をおさえる。肩こりをなおす。疲労回復。血糖値を押さえる。バニリンという梅にしか含まれていない成分が、肝臓の機能の向上に寄与する」など、すばらしいものがあることを、いろいろ知りました。
Subacoの料理は、おかゆのほか、ニンジンのフライタルタルソースかけ、梅酢の柴漬けなど、梅や梅酢を使った料理がいろいろ。みんないい味でした。
塩の話も梅干の話も、知らないことがいっぱいでした。2時間かけて運転していった甲斐がありました。
これまで、梅漬けというと、家の庭で採った斑点だらけの梅か、よそでもらった梅で漬けるばかりでしたが、今回、南高梅の梅干のおいしさを知り、今年はこの梅で漬けてみたくなりました。たまたま、友人から新城の梅農家で南高梅を分けてもらえるという話をきいたので、さっそく頼むことにしました。
最後の写真は、お土産にもらった昨年収穫したしら梅干しと4年物のしら梅干。それと、購入した3年物のしら梅干です。今年は、私もシソを入れないしら梅干にしようと思います。
場所は、西尾市一色町の近々オープン予定のsubaco というカフェ。稲武からは2時間強の道のりでした。
今回のテーマは、塩。お話しくださったのは、三重県松本農園の松本清さん。自家農園の、みごとな南高梅を持参。まるであんずのようです。彼は、梅農家でもあり、梅干の作り手でもあります。そして、ソルトコーディネーターの肩書きもおもちです。

以下、彼と、イベントのコーディネーターの方の話をかいつまんで書きます。
「1905年に始まった塩の専売制度は、2005年まで続いた。専売制度は、単に自由な塩の販売ができなかっただけでなく、数回にわたる塩業整備のため、ナトリウム塩(塩化ナトリウムが95%だった会場含まれている塩のこと)しか塩と認められなくなった。そのため、全国各地にあった塩田がほぼ消滅した。1997年、ナトリウム塩以外の塩の流通がようやく認められ、その前から徐々に流通していた、ナトリウムの含有量が80%~90&以下の自然塩(おもに、輸入した天日塩を日本の海水に戻し、再結晶させた塩)が正式に販売できるようになった」
1905年に専売法が施行されたのには、食料難と衛生面での配慮という二つの大きな理由があったとのこと。ナトリウムの少ない塩は腐りやすいし、塩田で少量ずつ生産される塩は値段が高くなる。ナトリウム塩なら、大量生産が可能で、安価に供給できるというわけです。
でも、食料事情がよくなってもなお、この専売法が改正されないまま続行。わたしが「海の精」の存在を知った1980年代中頃、あの塩は普通の販売はできずに、研究会の会員を募ってその会員たちに渡すという形で、届けられていました。
「現在は、道の駅に行けば、必ずどこか地元の塩見つけることができるほど、塩の製造は自由化された。これらはいずれも、微量栄養素のマグネシウムやカルシウムが、ナトリウム塩(100年続いた専売公社の塩)よりかなり豊富にふくまれている」
「とはいえ、日本の塩の自給率は15%。飼料用、加工用はほとんど輸入品に頼っている」
松本さんが持参した塩のなめくらべは、たのしかった。ヌチマースは沖縄産。海の成分がそのまま濃縮され、結晶化した塩だそうで、いささか苦みが。奥能登揚浜の塩は、人力で海水をくみ上げ、塩田で乾燥させたもの。ナトリウム分は、ヌチマースより高め。
驚いたのは、ナトリウム分をどの程度にして塩の製造を進めるかは、職人のこだわりにかかっているということ。同じ塩でも、成分の表示が何%から何%と開きがあるところがあるのは、海水濃度の変化にもよるし、その濃度に合わせる職人の勘にもよるのだそう。

ところで、塩は人間の体にとても影響を与えるもの。暑い時出る汗の中身は、多くは水分。体は、塩分濃度を下げると危険なので、水分だけ出してしまうのだそう。熱中症の症状として、脱水症状があげられるのは、そのせい。冬でも、体が冷えると血液の塩分濃度を上げ、体温を上げようとするため、トイレに行く回数がふえるというわけです。
高血圧の人に医者がかならずといっていいほど勧める減塩。これがじつは、効果のない場合が結構あることを、今回初めて知りました。
「高血圧には、一次性高血圧と二次性高血圧がある。高血圧症の人のうち、一次性は約80%、二次性は約20%。二次性のほうは、複合的老化や遺伝によるものが多く、減塩によって血圧が左右されることは少ない」
「一次性高血圧の人は、食塩感受性といわれる体質の人が約4割を占めている。こちらは、少しの塩気で生きられ、塩をとりすぎると血圧が上がり、ナトリウムが体内に蓄積しやすい。そのため、彼らには減塩は効き目がある」
「しかし、残りの6割は、食塩抵抗性といわれる体質の人。塩を食べ過ぎても血圧は上がらず、減塩しても意味がない。減塩しても1割以下の変化しかなかったら、こちらの体質と判断される」
また、減塩による弊害も最近ではいろいろわかってきたそうで、高齢者が急激な減塩によって、認知症の症状が増すことがあるとも。
減塩するかわりに、化学調味料などの添加物を増やして、体にはかえってマイナスの要因になることもあるとの話には、おおいに納得。
自然塩の微量栄養素、それがおいしいだけでなく体にもいいとわたしは思っていましたが、松本さんに言わせれば、それは極めて些細な量だから、塩の違いでからだにいい悪いは判断できない、とのこと。
それより大事なのは、「食べ物との相関」。「マグネシウムの多い塩は、苦みが多い野菜に合うとか、岩塩は塩からいので脂身の多い肉を焼くときに使うといいとか、カリウムは酸味があるので、焼き魚に合うとか、料理や食材による使い分けをして、豊かな食事を彩ってほしい」

塩の話の後は、梅干の話。松本さんの農園では、南高梅をはじめ数種の梅を栽培しています。この日、持ってきてくださった梅干しは8種。5分搗きのおかゆに彼の付けた梅干を載せていただきました。外国産の塩で漬けた3種のほか、国産の塩3種、それと、3年物の梅干に、1年物のシソ入り梅干。
塩気が立っているように感じたのは、外国産の塩のような気がしますが、とりあえず、どれもおいしかった。
わたしはほとんどシソをいれてつけていましたが、入れないのも純粋に梅の味がわかって、なかなかいい。彼の梅干は、塩分濃度20%。大きい梅だと、23%にすることもあるとか。
わたしも、つける場合は、いつも20%の塩にしていますが、近頃は甘い梅干がいいという人が多いようです。その甘い梅干、調味梅干というのだそうですが、最初から塩気を控えて漬けるのでなく、普通に塩漬けした梅を水につけて塩気を抜き、それから蜂蜜とか甘味を加えて仕上げるのだとか。当然、腐りやすくやすくなるので、長期保存するとなると、防腐剤そのほかいろいろ添加物が必要になってきそう。
天日干しは、夏だと2日半ほど、秋だと4,5日。夏に天日干しができなかったら、秋に持ち越せばいいとはおもわなかった。いつもなんとか夏に干さないといけないと思って、あせっていましたが、ゆっくりかまえればいいようです。

梅干の効能は、食中毒予防のほかに、「血液の浄化作用があり、血液を中和して流れをよくする。胃の中のピロリ菌や虫歯菌をおさえる。肩こりをなおす。疲労回復。血糖値を押さえる。バニリンという梅にしか含まれていない成分が、肝臓の機能の向上に寄与する」など、すばらしいものがあることを、いろいろ知りました。
Subacoの料理は、おかゆのほか、ニンジンのフライタルタルソースかけ、梅酢の柴漬けなど、梅や梅酢を使った料理がいろいろ。みんないい味でした。
塩の話も梅干の話も、知らないことがいっぱいでした。2時間かけて運転していった甲斐がありました。
これまで、梅漬けというと、家の庭で採った斑点だらけの梅か、よそでもらった梅で漬けるばかりでしたが、今回、南高梅の梅干のおいしさを知り、今年はこの梅で漬けてみたくなりました。たまたま、友人から新城の梅農家で南高梅を分けてもらえるという話をきいたので、さっそく頼むことにしました。
最後の写真は、お土産にもらった昨年収穫したしら梅干しと4年物のしら梅干。それと、購入した3年物のしら梅干です。今年は、私もシソを入れないしら梅干にしようと思います。