我が国は男女共同参画が今頃さけばれているように、女性の社会進出が遅く、妊娠・出産・育児に関わる面での女性が働くための社会環境の整備が大幅に遅れ、いろいろハンディを負っている。その影響をもろに受けているのが看護師や女性医師などの医療関係者である。
最近、女性医師が急速に増加しつつある。
医師は業務上、立場上かなりの義務を負っている。場合によっては私的生活に支障が出ることも少なくない。そのために女性医師は家庭、育児と業務の両立が困難で、離職したり、パート医として働くケースが増加しており、医師不足を加速している、と言われている。
厚労省は女性医師の実労働時間をイギリスを参考に0.7としているらしい。実際には更に低いとの意見もある。女性医師が増加した分、相対的に医師不足になっているから大学入学者数を増やすべし、との意見もあるほどである。
本当に女性医師の状況はそんなものなのだろうか。今回改めて秋田県が昨年11月に行った県のアンケート結果を改めて見直してみた。
県では県内の女性医師314人に質間票を送付し、135人(43.0%)から回答があった。その結果から一部の項目を引用してみる。
育児休暇取得についての質問では、子どもが「いる」と回答した69人のうち、休暇取得は15人(21.7%)で、取得しなかったのは52人(75.4%)であった。
育児休暇を取得しなかった理由は、「取れる雰囲気でなかった」(20人、38.5%)、「休むと同僚に迷惑が掛かる」(16人、30.8%)、「代わりの人がいない」(13人、25.0%)の順で、「休むと辞めなければならなかった」「医局から取らないよう要求された」との回答もあった。
さらに、子どもが病気になったときの対応についての質問には、「子どもを預けて働く」(37人、53.6%)と半数を超え、「休暇を取る」(10人、14.5%)を大きく引き離した。
要するに、「育児休暇」、「子どもが病気になったときの対応」で見る限り、秋田県内で働く女性医師は一般的に言われている以上に頑張っている、と言う実態が明らかになっている。
最近、女性医師が急速に増加しつつある。
医師は業務上、立場上かなりの義務を負っている。場合によっては私的生活に支障が出ることも少なくない。そのために女性医師は家庭、育児と業務の両立が困難で、離職したり、パート医として働くケースが増加しており、医師不足を加速している、と言われている。
厚労省は女性医師の実労働時間をイギリスを参考に0.7としているらしい。実際には更に低いとの意見もある。女性医師が増加した分、相対的に医師不足になっているから大学入学者数を増やすべし、との意見もあるほどである。
本当に女性医師の状況はそんなものなのだろうか。今回改めて秋田県が昨年11月に行った県のアンケート結果を改めて見直してみた。
県では県内の女性医師314人に質間票を送付し、135人(43.0%)から回答があった。その結果から一部の項目を引用してみる。
育児休暇取得についての質問では、子どもが「いる」と回答した69人のうち、休暇取得は15人(21.7%)で、取得しなかったのは52人(75.4%)であった。
育児休暇を取得しなかった理由は、「取れる雰囲気でなかった」(20人、38.5%)、「休むと同僚に迷惑が掛かる」(16人、30.8%)、「代わりの人がいない」(13人、25.0%)の順で、「休むと辞めなければならなかった」「医局から取らないよう要求された」との回答もあった。
さらに、子どもが病気になったときの対応についての質問には、「子どもを預けて働く」(37人、53.6%)と半数を超え、「休暇を取る」(10人、14.5%)を大きく引き離した。
要するに、「育児休暇」、「子どもが病気になったときの対応」で見る限り、秋田県内で働く女性医師は一般的に言われている以上に頑張っている、と言う実態が明らかになっている。

















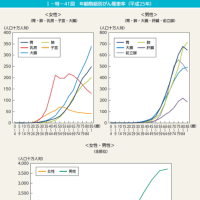


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます