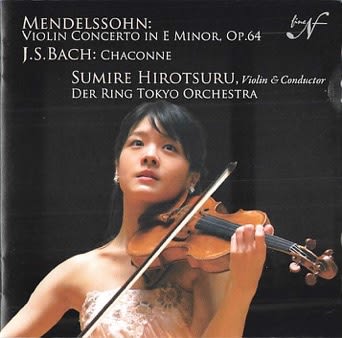私は音楽が好きである。いわゆるクラシックと言われる分野が中心であるが、民謡、浪曲、ポップス等を含め広く、あまりジャンルを問わない。ただ、ジャズはちょっと遠い。
この2-3年はクラシック分野で特に頻度が高いのはブルックナー、マーラーの曲が中心。近代の作品はあまり聞かなくなった。ブルックナーの交響曲は、特にチェリビダケ指揮ミュンヘンフィルの演奏に集中して聴いている。私にとってブルックナーの曲は総じて宗教音楽に近く、聴く度に敬虔な気持ちになる。
私はもともと歌謡曲が大好きである。特に昭和時代の歌謡曲が好き。
昭和の歌謡曲は好んで聴いてはきたが、2013-15年は特別集中的に聴いた。その理由は、録りためた録音のデータベース化、インデックス作りをしたからである。
私は2008年からFM放送のラジオ深夜便の午前1時、午前3時、午前4時から各1時間、計3時間分を連日ハードディスクに録音している。これらの録音は適宜iPod等に落として通勤途上などで聴いてきた。
歌謡曲は2013年時点で5.000曲ほど蓄積したので全曲をデータ化した。データ化しないと曲を探し出すことは不可能だから100%無為な録音になってしまう。だから私にとって大変だったけれどもインデックス作りは楽しい作業となった。検索をかけると一発で探し出すことが出来る。これは宝である。その後も蓄積は継続しているので今の時点では約15000曲に達している。
午前1時、午前4時からは各界の著名人(?) が登場し貴重なお話が聞けるが、これも全てインデックスを作成、いつでも呼び出せる様にしてある。加えて連日の新聞スクラップ、電子化した蔵書もいつでも呼び出せる状況にある。
私の人生は各種のデータの収集とそれらのデータベース化に充てられている。これらは、ほぼ連日何らかの形で役立っているから無駄ではなく、楽しい作業である。
この2年ほど再び歌謡曲を聴き始めた。
その理由はインターネットラジオの普及であった。インターネットラジオはほとんど雑音がなく音質は極めて良好、FM放送の音質を十分凌いでいる。しかも、NHKの場合、1週間ほど「聞き逃しサービス」を利用できるので私にとって都合がいい。今はこちらの録音蓄積も始めておりデータベース化している。
歌謡曲は昭和7年にNHKによって命名されたという。それまでは「流行歌」と呼ばれていたが、流行という言葉をNHKが嫌ったからだとされている。「流行歌」とは「歌詞・曲・歌い手」をセットとしてヒットを狙って売り出される商業的歌曲のこと(なかにし礼)であるが、それが昭和初期から歌謡曲と呼ばれることとなった。
私は戦後時代に育ったが、「流行歌」は昭和の時代・世相を濃厚に反映している。