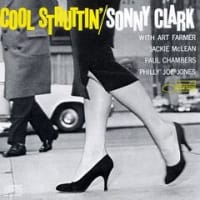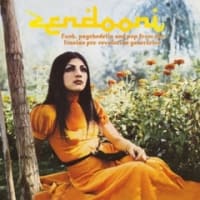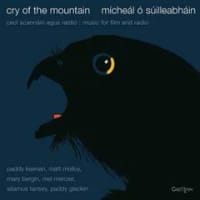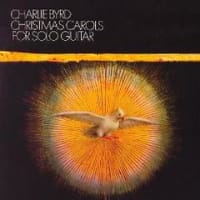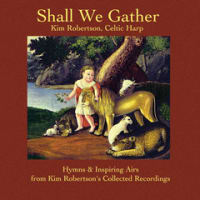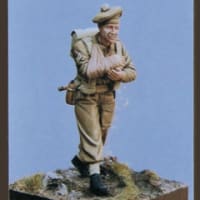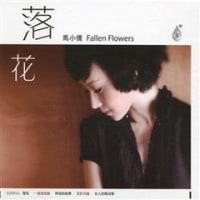”The Ballad Of Ira Hayes ”by PETER LAFARGE
昨日書いたと同じ”第2次世界大戦に米軍兵士として参加するアメリカ先住民”ネタとして思い出さずにはいられなかったのが、60年代、ピーター・ラファージというシンガー・ソングライターが創唱した、”アイラ・ヘイズのバラッド”だった。
戦場で武勲を立て勲章を得てヒーローとなる、アメリカ先住民の兵士、アイラ・ヘイズ。
だが、戦争が終わり故郷へ帰ると、彼はそれ以前と同じ、アメリカ社会では疎外された少数民族の一人でしかなかった。望んだような職も得られず、いつしか酒におぼれて現世を忘れようと努めるようになる。
そしてある朝、泥酔した挙句にアイラ・ヘイズは溝にはまって息絶えていた、そんな歌である。
現実はそのようなものだろう。昨夜、論じた映画、「ウインドトーカーズ」に出てくるような”不思議な魔法を操る、愛すべき、妖精のごときアメリカ先住民”なんて扱いが絵空事であること、考えなくとも想像は付く。
ピーター・ラファージのアルバムは昔々、シンガー・ソングライターの音楽が興味の中心だった頃に手に入れ、聞いてみたことがある。が、アメリカ先住民の血を引く歌手のアルバムというので、その民族色豊かな世界を期待していたのに、さほどその色は強くなく、60年代の平均的なアメリカの”フォークシンガー”としか感じられず、拍子抜けしてしまって、すぐに手放してしまったのだった。(ちなみにラファージは60年代、何枚かのアルバムを世に問うた後、その才能を期待されながらも事故で夭折している)
彼と同じく、アメリカ先住民の血を引くシンガー・ソングライターとしては、同じく60年代から70年代にかけて活躍した、パトリック・スカイなどという人も思い出される。彼もまた、60年代のグリニッジ・ヴィレッジ色というか、当時のアメリカン・フォークの土壌の中でその音楽を展開した人で、先住民色はまるで感じさせはしなかったものだ。
その一方で奇妙なビブラートを効かせた歌い振りで印象に残っている、バフィ・セントメリーなどという”先住民系シンガーソングライター”もいたのだが、こちらは逆にその音楽の神秘めかした手触りが私にはわざとらしく感じられてしまい、こちらも逆方向で好きになれなかったものだ。
その他、民俗音楽としてのアメリカ先住民の音楽という奴も、興味を持っていくつかを聴いてはみたのだが、どれもなんだか昔ながらのウエスタン映画に出てくる”アメリカ・インディアンの音楽”を想起させる神秘めかした感じの太鼓のリズムや笛の音などばかりで、あまり面白いものではなかった。私の選んだサンプルが悪かったのだと信じたいが。
先に挙げた”先住民系フォークシンガー”たちの仕事があまりはかばかしいものではなく、一方、民俗音楽系もまたそのような具合であること。これは、かのアメリカ合衆国の先住民たる彼らの蒙った社会的抑圧が彼らの文化をも押しつぶしてしまった結果とも思え、なんだか寒々しい気分になってくるのだが。この印象は私の、彼らの音楽に関しての無知ゆえから来ていると信じたいのだが・・・
付記。ちなみに、ラファージが歌にした「第2次世界大戦中にアイラ・ヘイズが立てた武勲」とは、現在クリント・イーストウッドの映画で話題になっている”硫黄島”でアメリカ国旗を戦勝の証に丘に突き立てた、あの兵士のうちの一人だったことであるそうな。