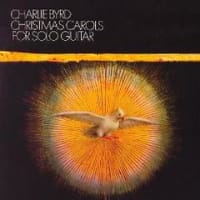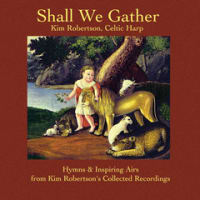”柳ケ瀬ブルース”by 美川憲一
ご存知、美川憲一の出世作となった、当時の表現で言えば「夜のムード演歌」であって、何を今更語るべき、みたいなものであるが。
先日、なんとなく演歌に関わるサイトを覗いていたら、この歌についてひとつの事実を知った。
もともとこの歌は、長岡の地でいわゆる「流し」をしていた宇佐英雄氏が自身の体験に基づいて作詞作曲した「長岡ブルース」であった。が、たまたま柳ケ瀬の街に遠征して歌っていたのをレコード会社のディレクターに見出され、柳ケ瀬の街に関わりのある新人、美川憲一のデビュー曲に登用されることとなり、タイトルも「柳ケ瀬ブルース」と変更され、レコードとして世に出ることとなった。
そんな記述が、何か心に残った。とたんに、ギター抱えた演歌師とともに流れる歌と心、のイメージが頭を離れなくなった。
酒に澱んだ盛り場の、川面に揺れるネオンのあかり、その狭間から自然現象として生まれてきたかのようにさえ思える昔気質の歌が、酒場女の溜息と共に、その路地に浮遊霊の如く染み付いて洗い流すすべもないかと思われた演歌が、裏町演歌師の稼業につれて簡単に流れる。舞台設定さえ変えてしまう。
それが、酒場歌をいくばくかのオカネに変えては生きて行く、流れの演歌師たちのある意味寄る辺なき、ある意味したたかなナリワイを生々しく感じさせたのだ。
「そうだ、この歌、この土地の歌に変えちゃいましょう。この土地の地名が入っていたほうが、お客さんも喜ぶよねえ、そりゃ」
”悶え身を焼く火の鳥”と歌われた、この歌に宿るタマシイは、見知らぬ土地でその名さえ変えられ、それでも忘れられぬあの人を想い、今夜も雨中に身を焼く。この歌は、宇佐英雄氏が現実に体験された悲恋に基づくものなのだそうだ。
裏町の歌い手たちの、そしてバンドマンたちの消息はすぐに知れなくなってしまう。ほんとうに雨に溶けるように彼らは姿を消し、そんな彼らの足跡をカラオケの登場は永遠に消した。歌はただ異郷に残り、歪められた名のまま、想いを辿り続ける。
何をわけのわからんウワゴトを言い出すのだと呆れておられる向きもあろうが、お許し願いたい。なにしろこちとら、温泉地の歓楽街に生まれ育ち、流しのお兄さんにギターを、キャバレーのバンドマンにサックスと音楽理論を学んだスジモノであって、夕暮れ迫る辻々に赤い灯青い灯が灯り、安い期待に胸ときめかせ街に繰り出す酔客たちの笑い声や、それを迎える女たちの嬌声などが醸し出す、ささやかな華やぎの一刻と、そんな世界の登場人物たちには、それなりの思い入れがあるのだ。
この3月、作者の宇佐英雄氏が亡くなったそうだ。妻子を北海道に残して単身滞在していた三島の街で客死された、とのこと。長岡の件といい、伊豆の地に肌の合うものを感じておられたのだろうか。
作家としては、「柳ケ瀬ブルース」はヒットしたものの、作曲と作詞をともに自身で行う独特のスタイルが分業制度の確立した当時の歌謡界には受け入れられず、不遇のうちに終わったようだ。