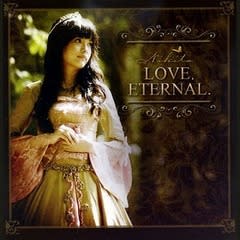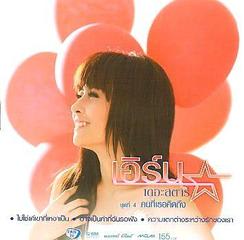”Love Eternal”by Nikita
とりあえず、このアルバムについて得られる知識があるならば知っておこうとアーティスト名とアルバム・タイトルを打ち込んで検索をおこなったら、エロ・ゲーム関連のサイトやらその他ポルノ情報がズラズラズラッと出てきたんで、頭を抱えてしまったのでした。偶然、共通する単語があったってことなんだろうが、そりゃあんまりだろうよ。
何しろこの盤、インドネシアのキリスト教ポップス、ロハニの新譜なのであります。歌われる歌は、どれも心洗われるような清浄な美しさを持つ讃美歌調のメロディであり、というか、いくつかは”アメイジング・グレイス”をはじめとして、私のような非クリスチャンもメロディをたどって一緒に歌えるような有名賛美歌そのものであったりする。
それを歌い上げる新人歌手ニキータちゃんも、リンと伸びる声を可憐に張って、心を込めて信仰への想いを歌い上げているのであります。伴奏なんかもなかなか豪華で、ストリングスやコーラス隊を含む分厚い音は、神の愛に包まれた約束の地の豊穣を描くが如きであったりするんであります。
でも・・・もしかして、このロハニなる音楽を成立せしめている要件の一側面を結構突いてきているんじゃないか、この偶然の符合は。なんて思ってみたりもするのでした。聖なる音楽のハザマに窺える、庶民の猥雑なる生へのエネルギー、などというものについて。
豪華カラー版の内ジャケでは、なんだか佐藤江梨子あたりを連想させる南方系美少女の歌手ニキータちゃんはお伽話のお姫様みたいな衣装に身を包み、森の中で艶然と佇み、ポーズをとっているのです。たまらんわ。萌えるわ。となります、信仰も何もない私にしてみれば。
ヨーロッパのどこぞの教会から聴こえて来ても不思議はないくらいの賛美歌ポップスのロハニではありますが、あくまでもインドネシアの音楽であり、インドネシア語で歌われております。その言霊からは、濃厚な”アジア”が香ります。
また、歌唱法の基本には、昔々にポルトガルが置き忘れていったラテンの情熱がほのかに漂います。
その、交錯する不思議な矛盾、違和感のファンキーな心地よさ。やっぱり奥深い、刺激的な音楽です、ロハニとは。やめられません、クリスチャンなんかでは全然ない私ではありますが。