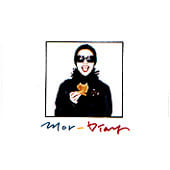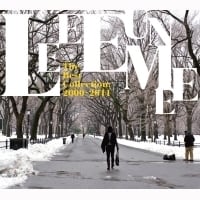”Diary”by Riaa
韓国の女性ボーカルものをあれこれ聴いているけれど、好きというより一番気になるのがこのコ、Riaa嬢なのであって。気になるというより、彼女を聞いているのが一番刺激的に感ぜられるというべきか。
それは韓国の人々にとっても同じだったようで、デビュー時、まだハタチそこそこの彼女の生涯を扱ったドキュメンタリー特番が制作され、テレビで流れた、なんて話もある。何がそんなに人々の関心を集めたかといえば、彼女が事情あってインドで幼少時代を過ごし、ティーンエイジャーになってから韓国に帰った、つまりちょっと変わった国からの帰国子女だったからで。
ほどなくロック歌手として世に出た彼女は、その特殊事情を正面に押したて、チベット風のファッションに身を包み、ダライラマの思想に影響を受けたユートピア・イメージを語り、自らの音楽のテーマともして、おおいに大韓の人々をケムに巻いたものであります。いや、彼女は本気でやっていたわけですが。
その他、元気はいいけど、ちょっと風変わり・・・くらいではすまない素っ頓狂なボーカルスタイル。気まぐれに発せられる裏声はそのままはるか天国に吸い込まれてゆくようで。また、これは韓国語がわからない身の上には想像するしかないが、ダライラマ影響下の歌詞も相当なものらしい。
そのへんの”異物”具合がなんとも同時代人としての私には爽快に感じられて、彼女が、かの隣国にいる、と思うだけで愉快になってしまうのであります。なんというのかな、韓国人という枠にとらわれない、というかはじめからそのような発想を持ち合わせない彼女のすっ飛び具合に拍手せずにはいられない気分なのであります。
という訳で、豪快にタイ焼き食って笑っているジャケの、これが1997年に発表されたRiaa嬢のデビュー・アルバム。こうして韓国人でありながら韓国では異邦人、という不思議少女アリスぶりの彼女の冒険行は、ここに幕を切って落とされたのでした。さて、この先のお話は、また機会がありましたら。