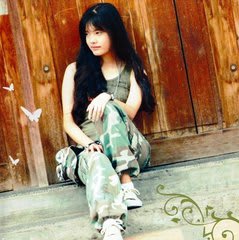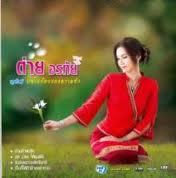”敗犬美魔女”by 丁國琳
今日の台湾の歌謡ポップス、ならびに巨乳界をリードする期待の新人、ティン・クオリン女史の本年度作品であります。それにしてもすごいタイトルで。いや、意味は分からないんですがね、なんとなく字面を見ただけでもサドマゾ入り乱れている感じで、セックスシンボルたる丁女史のヤバいキャラぶりがジワと伝わってくるような気がします。
どうやらこのアルバム、”中東っぽさ”がキイワードとなっているらしくて、冒頭のタイトルナンバーは、クールに打ち込まれるリズムに乗り、エキゾティックな歌謡メロディが歌い上げられ、それに絡むイスラミックな旋律とへんちくりんな掛け声、そのインチキくささと微妙に漂う淫猥な雰囲気、たまりませんねえ、大衆音楽の真実度、相当に高いです。
それ以外にも、収められているゲストの男性歌手とのデュエットによる演歌にシタールが絡んでみたり、結構清楚な仕上がりの台湾らしいフォーク歌謡なんかもあるんですが、それのバックに響くサックスがアラビアっぽい旋律を吹き鳴らして妙なことになっていたりする。
そもそもアラビアっぽいコンセプトとは言っても、彼女の巨乳キャラを活かすコンセプトをこのアルバムにおいてはそのように設定したというだけで、それほどアラビアっぽい曲が揃っているわけでもないのです。エキゾティックな装飾を剥ぎ取ってしまえば、結構台湾ポップスの王道をゆく内容であったりするのです。
彼女のヴォーカル自体も、落ち着いて聴けば意外に清楚な響きがあり、巨乳を売りにする表向きのキャラとはまた別の素顔が潜んでいるのでは、なんて憶測も生まれてこようというものです。
さらに、清楚っぽい素地に巨乳という彼女、実はその年齢、アラフォーくらいは行っている、という噂もあるんでして、ますます謎は深まる。いや、そのへんの怪しげな陰影も含めて芸能世界の面白さなんであって、ますます彼女に惹かれて行かざるをえない。
アルバムを覆う、コンセプトの見かけよりは意外にあっさり味のサウンド作りは、早朝、醒めかけの夢の中で遭遇した束の間の儚い性夢の幻にも似て、ますます微妙に悩ましい面影を形成する。
こんなことをグダグダ言いながら聴いているうちに、気が付けばすっかり美魔女のトリコとなっている、という筋書きであります。