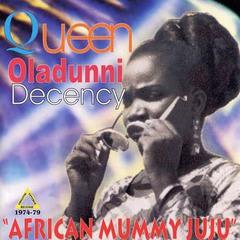” HAPPY DAY ”by Oluwe
この頃、なんとなく気になっているナイジェリアのヒップホップ。手に入る機会があったんで、その中で一番マイナーでローカル、というこのアルバムを買ってみた。ヨルバ語のラップをやるというんだが、人相も悪くていいじゃないか。
で、ほんとにマイナーな人らしくて、彼に関する情報を求めてネットの世界を探りまわったんだけど、記述一行、画像一枚、出てこなかった。無名の新人ってところなんだろうねえ。ちなみにこれ、2008年盤。
気になっているとは言っても、「ヒップホップ」と銘打っている以上、アメリカの黒人が、いや、いまや世界中の若者がやってるような、どこに参りましても変わり映えもせず同じような出来上がりの「レベルは~低いが~クラブじゃ~オシャレ~♪」みたいな音を聞かされる危険性は十分あるわけだから、恐る恐るCDを回転させてみたわけですよ。
まず聞こえてくるのはドッスンバッタンと重苦しくも性急な打ち込みのリズム。シンセがその裏で悲痛な響きの短調の和音を積み上げて行く。そいつに乗ってアルバムの主人公、OLUWEの野太い吠え声が響く。いかにもアフリカ風なもっこりとしたコーラスがコール&レスポンス状態で後に続く。
ラップ、とはいっても。それは確かにそうなんだけど、そこにはやっぱり濃厚にヨルバの血が息ずいている感じだ。フジやらジュジュやらの伝統的部族ポップスの語り口にかなり通ずるところのある、時にイスラミックなメリスマさえ聞こえる代物なのである。
見えない大蛇が通り過ぎて行くような、音楽の底に沈む深いコブシのうねりが伝わってくる、そんな歌いっぷりの”ラップ”なのである。
良かった。こいつ、”当たり”だよ。”アクセント言語”であるところのヨルバ語でラップを行なったがために言語の呪縛により、こんなことが起こっているのかなあ、などとも思ったのだが、まあ、確証はない。
その後、”むずかしいべ”とか”あとでブス”とか”サイコー”とか”虫歯”なんて空耳アワーを展開しつつOLUWEの”ラップ”は続いて行くのだが。うん、ほんとにこれ、いいんじゃないか?
私なんかが初対面した頃、80年代の、地の底から湧き上がって来るようなどす黒いリズムの蠕動や情感の迸りが、なんだか希薄になってしまった感も否めない昨今のナイジェリアのイスラム系音楽である。
そして、なぜか理由は知らないが、今日のフジ・ミュージックやアパラ・ミュージックが失ってしまった、そんなどす黒い音楽的衝動は、むしろこのようなラップを演ずるナイジェリア人に受け継がれているような気配がある。
いや、まだ2~3枚しかその種のアルバムを聞いてはいないのだがね、どうもそんな感じを受けるのだ。
まだ・・・実は一度見放しかけたナイジェリアの音楽だが、そうやらまだまだ捨てたものではなさそうだ、そんな風に信じてもいいような可能性を、私はこのアルバムに感じる。いけるよ、まだ。と思うよ。