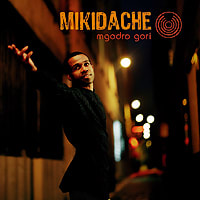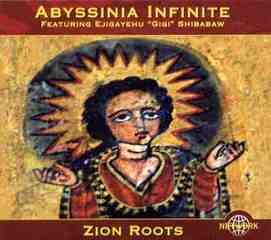下は、”2007年にリリースされた再発盤(リイシュー盤)の中から、 「これはスゴかった」「この再発には泣けたゼ」と思われるアルバムを 10枚選らんで下さい”とのアンケートに対する回答です。
ちとルールから外れた回答だけど、こんな表現しか思いつかなかった。AYINLA OMOWURAって、我が最愛の歌手なんだよな~。
それにしてもナイジェリア盤、ともかく手に入りにくいんだよ~。現地に行った人にも難しいってんだから弱ったものです。なんとかならんかの~。
~~~~~
☆ AYINLA OMOWURA AND HIS APALA GROUP/ CHALLENGE CUP 1974
☆ AYINLA OMOWURA AND HIS APALA GROUP/ OMI TUNTUN TIRU
☆ AYINLA OMOWURA AND HIS APALA GROUP/ ABODE MECCO
☆ AYINLA OMOWURA AND HIS APALA GROUP/ OWO TUTUN
☆ AYINLA OMOWURA AND HIS APALA GROUP/ AWA KISE OLODI WON
☆ HARUNA ISHOLA & HIS APALA GROUP / EGBE PARKERS
☆ HARUNA ISHOLA & HIS APALA GROUP / OGUN LONILE ARO
☆ HARUNA ISHOLA & HIS APALA GROUP / PALUDA
☆ YUSUFU OLATUNJI & HIS GROUP / BOLOWO BATE
☆ YUSUFU OLATUNJI & HIS GROUP / O'WOLE OLONGO
かっては実現の可能性もなさそうな、単なるジョークにしかならなかった、アフリカはナイジェリアのイスラム系ポップス、”アパラ”や”フジ”や”サカラ”の70~80年代(全盛期!)のアルバムのCD再発が、なんと現地において着々と進んでいた!これは嬉しいニュースでした。
もっとも、はるか彼方の、なおかつかなりワイルドな(?)リリース事情の国の事とて、現物の入手も困難を極めるのだけれど。
そんな訳で上に挙げたのはあくまでも順不同。入ってきたリリース情報をコピーしただけで、入手出来なかった盤もいくつか混じっています。日本のレコード会社は出して・・・くれるわけ無いかぁ。
~~~~~