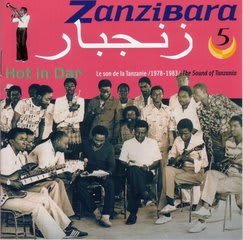”Lafrikindmada” by Lindigo
久々、アフリカはマダガスカル島の沖に浮ぶ島国、レユニオンから届いた島唄”マロヤ”の新作ヒットアルバムだ。
冒頭、無伴奏のコブシ入りの詠唱が始まったときは、そのニュアンスがまるでナイジェリアのアパラみたいに聴こえてドキリとさせられたのだが、リズムが入りコーラスが被さりしてみれば、そのノリはずっと軽やかで、どこかにほのかな潮の香りさえ漂う。
どちらもパーカッションとボーカルがメインの音楽でリードボーカルとコーラス隊のコール&レスポンスも多いという事情もあり、行き掛かりのついでで比べてしまえば、ナイジェリアのフジやアパラとこのマロヤでは、この涼やかさが決定的な違いだろう。地の底に引きずり込まれそうな重苦しさはマロヤにはなく、パーカッションのアンサンブルもむしろサンバなどに近い軽やかさ。
また、イスラム風に曲がりくねったコブシ入りのメロディがうねりつつ続くフジ等と比べ、このマロヤはよりシンプルな、メロディというよりは断片的なフレーズの繰り返しがメインであり、構造的には原始的な民俗音楽に近いものである。にもかかわらずマロヤのほうがずっとお洒落な都会調の響きがあるのはなぜだろう?これも旧宗主国、フランスの影響なんだろうか?そういえば一部、歌詞がフランス語だったりする。
ミュージシャン自身にしてもそうで、中ジャケの写真など、さっきシャワーを浴びてコロンを振ってきました、みたいな爽やかさが漂うリンディゴのメンバーである。
もう何枚もアルバムを聴いてきたのだが、このマロヤなる音楽、さっぱり正体がつかめない。マダガスカル沖ということで、アフリカのインド洋領域の音楽と捉えるべきとは分っているのだが、その先の見当が付かない。
見当をつけようとしても、この涼やかさ、軽やかさ、そしてどこかにふと漂う潮の香りと不思議な哀感に心をもって行かれてしまって、インド洋の果てに吹く風の感触など茫然と想っていたりする。この哀感漂うメロディはどこからどのような道を辿ってやって来たのだろう、なんて事をぼんやり考えていたりする。
アフリカン・ポップスといったってこのマロヤ、聴く側の感じで言えば、むしろ秋が似合う音楽なのだ。アルバムの終わり近く、アコーディオンが簡単なフレーズを何度も繰り返し、パーカッションのアンサンブルがそれに呼応してリズムの共演が行なわれても、演奏の場は熱狂に向うことなく、どこかにシンとした島の空気の存在を伝えるばかりだ。
そうこうするうちにアルバムの最終曲に至り、インド洋に沈む夕日のイメージを残しながら、パーカッションのアンサンブルはフェイド・アウトして行く・・・