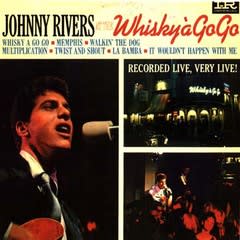”浅川マキの世界”by 浅川マキ
ネット仲間のプカさんからいただいたメッセージにあった浅川マキの曲、”前科者のクリスマス”が気になってきて、唯一持っているマキのCD、”浅川マキの世界”を引っ張り出し、聞き返してみる。
”今頃どこにいるだろな 同じ刑務所を出たあいつ
クリスマスに一人ぼっち 思い出せば雪が降る”
作詞・寺山修司、作曲・山木孝三郎。久しぶりに聴いてみたのだが、賛美歌調のハモンドオルガンのソロにファンクなリズムが忍び入る感じで打ち込まれて始まる、マイナー・キーのジャジーなナンバー。なかなか新鮮でかっこいいんではないか。クリスマスに浮かれる世情に倦んでいる身としては、その落ち込み気味のファンクなリズムが暗いなりに心地良く、救われた気分になったりもする。
これは浅川マキのデビューアルバムである。オリジナル盤は1970年の秋に発売されている。
アルバム全体としては、基本的にはジャズ系列のアレンジが成されているのだけれど、当時(海外で)流行していたブラスロック風のアレンジが強引に持ち込まれた曲があったりして、その頃の音楽の潮流というか、ロックやソウルに興味を示したジャズマンの血の騒ぎなんかが伝わる瞬間があり、その辺りから生々しい時代の空気が感じられる。
それに呼応して、こちらの心に眠っていた時代への思いが深いところで揺らぐような瞬間もあり、真正面から向き合っていると、なのやらドギマギしてみたりもする。
”俺も同じ一人ぼっち 酒場の隅のろくでなし
泣きぐせ女からかって あとは一人寝 橋の下”
ついでに、「これ、イマドキのクラブ方面で結構受けるんじゃないか」とか言ってみようか。
いやなに、イマドキの若者なんかに受けようと受けまいと、私としては知ったことじゃないんだけど、以前この場で言ったとおり、浅川マキが出して来た何枚ものアルバムはいまだ、そのほとんどがまともな形で復刻が成されていないのだ。
何をやっているんだレコード会社よ、という意味も込めて書いてみた。
寺山がこの世を去ってから、もう何年になるのだろう。夭折した寺山は、いったい今年でいくつ、私より”年下”になってしまったのだろう。彼が生きていた時代は、もうずいぶん遠いところに行ってしまったように思える。
”さよならだけの人生も しみじみ奴が懐かしい
賛美歌なんか歌っても 聞いてくれるのは雪ばかり”
今どき聞かない類の”無頼の面影”が、マキのレイジーな歌声とミディアム・テンポのファンク・サウンドに乗って流れて行く。面影は、空疎に淀む年の瀬の風の中で凍り付いている。