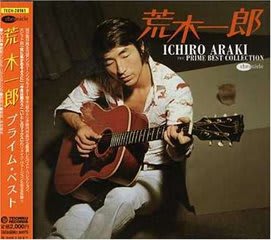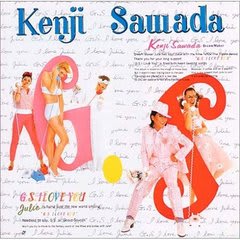”ジャニスを聴きながら”by 荒木一郎
深夜3時半なんて時間に寝起きだなんてのは私くらいのものか?別に仕事の都合とかじゃない、夜、テレビを見ながら寝転がっていたら、つい、本気で寝込んでしまった結果である。ああ、中途半端な気分だ。起き出すには早すぎるし、寝なおす気分じゃないし、酒を飲むわけにも行かないし。
所在なし、という状態でつけっ放しになっていたテレビをいじくり回していたら「あしたのジョー」のアニメをやっていた。私もこの辺の世代ではあるんだけど、特にファンでもなかったので、このアニメを見るのははじめてだ。いつ頃作られたのかも知らない。ストーリー全体のどのあたりのエピソードかも分らず。
画面に終始細かい雨が降っているかのような哀感が感じられたので、もうジョーの物語の終わり近くなのかなと思って見ていた。が、番組終わりの次回予告は”第8回”となっていたので、まだ物語は始まったばかりなのか。これが「ジョー」のタッチなのかも知れない。
同じ時代の歌手を歌ったもの、という連想なのか荒木一郎の「ジャニスを聴きながら」をふと聴きたくなり、CDを引っ張り出して聴いてみる。
同じ時代も何も実は、この歌で歌われている”ジャニス”が何者なのか長い事知らずにいた。まあジャニス・ジョプリンのことだろうと見当は付いていたのだが、歌のタッチがあまりにもフォークなので、誰か別の、私の知らないジャニスについて歌っているような気もしていた。
この歌の歌い出し、”街はコカコーラ”を聴くたび、東京へ出て暮らし始めた年の夏の最初の日、友人たちと渋谷の街に遊びにくり出した思い出が、何枚もの連続写真みたいにストップした場面の連続で蘇ってくる。あの頃はジャズ喫茶に行くのが大好きで、それ一杯で粘り過ぎたおかげで、溶け出した氷にすっかり薄味になってしまったコーラを前に、飽きることなくジャズを聴いていたものだった。
もっとも、ネットで検索してみるとこの部分、「街はロードレース」ともなっている。何かの事情で書き直されたのかもしれない。どちらがオリジナルか分らないが。当時あった、なにごとかの事件にちなむ歌詞なのだろうか。歌詞の他の部分、墨で消されて売られて行くプレイボーイ、というのは雑誌のグラビアでワイセツ事件でもあったのか?はっきり覚えていないけれども、そういうことがあったりした時代でもあった。オイルで汚れた引き潮、というのも、同じように現実の事件に関わるのか。
そんなこともあったんだろう。あれもこれも忘れてしまったのだけれども。グダグダしているうちにも、残酷な夜明けは忍び寄っている。朝が来て一日が動き出したらせねばならないつまらない仕事のいくつかが記憶に蘇り、そのうっとうしさに、ふとこのまま死んでやろうかな、などと思う。ほんとに死にはしないけれども。
”人生はつかの間のゲームであり、その幻の賭けに負けた時は”と、荒木一郎はCDラジカセから歌いかけてくる。いや、彼は私などに関心はなく、ただ勝手に歌っているだけなんだが。”それだけのことなのさ”と。