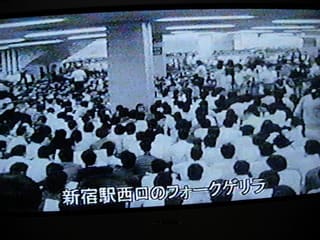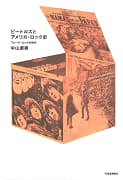”やけっぱちロック~やさぐれ歌謡最前線:ビクター編”
台風は来るんだか来ないんだか、降ったりやんだりする雨を見つめて一日が過ぎてしまった、昨日。
東電の原発を台風が直撃、炉が一つ、波にさらわれてどこ行ったか分からなくなっちゃいました、なんてことにはならないのかね。東電の説明担当者いわく、「まあ、どこかに流れていったとしても同じことですから」と説明する、なんてね。大スポンサーの東電の説明ゆえ、いつもの通り記者諸君、何も言わずに納得する、とかね。
このアルバムをどう説明したものか。あのやさぐれた60~70年代をやさぐれて生きたお姉さんたちがやさぐれて歌ったダルな昭和歌謡を集めたものだ。冒頭、池玲子、杉本美樹と、当時人気のあったポルノ女優の歌が2曲ずつ収められている。まあ、そういう時代だったわけだ。とはいえ、このアルバムで私は彼女らの歌をはじめてまともに聴いたわけだが、いや、こんなにヘッポコだったとはね。
私としては、このアルバムを聴いていると、70年代初めの頃の東京は新宿の裏通りの飲み屋とか、終電を乗り過ごして途方にくれている池袋駅前とか、当時のバンド仲間とか、そんなものを思い出すのだが、別種の思い出のある方もさまざまおられよう。
あの時代。人々は今よりずっと生臭くて愚かで喧嘩っ早くてギトギトの生を生きていた。などと言っても、いまさら意味はないが。いやなに、間抜けな話だったんだよ、何もかも。
ちなみにここにはヒット曲なんて一曲も収められていない。それが証拠に、今、You-tubeをさんざん探したが、収録曲はほとんど見つけられなかった。にもかかわらず、これはあの時代の音楽である。本当は中村晃子の「裸足のブルース」か内藤やす子の「ひとりぼっい」とか、張りたかったんだけどね。
あと、「ケリ」が収められている山川ユキがやっぱり良い。ほらあの「新宿ダダ」の。といったって分かる人はそうはいないか。この子のアルバム、出してくれないものかなあ。いや、ユキが残したレコーディング、全部集めてもアルバム一枚にもならないのかも知れないが。
ネオン花咲く新宿で、女の子が靴を投げ出し、一人歩いてくのだ。赤いドレスも車もなんにもいらなくなってしまったから。帰るはずのない男を一人待っていたり知らない町に電車で着いてしまったり、そこらあたりの腰抜けに私を口説けはしない、勇気と金のある人だけ私を口説いてごらんと立ち去ったり、二杯目のコーヒーは苦いがあなたはどうやら来ないらしかったり、あなたは死んでしまったり、でもあたしだったらどうにかなるわ、たかがおんなの人生じゃないのと自分で自分を抱きしめて口笛を吹くのだ、ぐれて流れて3年経って肌にゃ真っ赤なバラが咲くのだ。
下の曲、本当はこの盤には原田芳雄ではなく、安田南の歌で収められています。でも、こちらがオリジナルらしいし、この時期だから、ね。