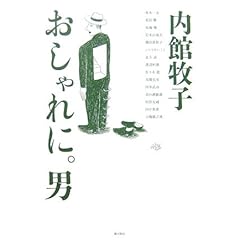ブログ・コンセプト② 「3つの読書リテラシー」
「読書リテラシー」という表題は大げさに聞こえるかもしれませんが、本を読むときに心がけていることがありますので、今回はそれをいくつか紹介します(ここで言う読書は仕事関係のそれでなく、文字通り、趣味としてのそれです。
ひとつは、必ず最初から最後まで読み通すことです。つまらなくても、難解でも、頭に入らなくとも、とにかく読み通します。と言うのは、途中でやめなくてよかったという本にたくさんであったからです。途中でやめてしまっていたら、宝物を発見できそこなやのではと思ったことはしばしばです。鉱脈に辿り着くには、苦労をともなうものなののです。
もっとも「必ず」と言っても、途中で投げ出した本が全くないわけではありません。ただし、それはほんの数冊しかありません。
2つ目は、読書は最初の部分が肝心なので、丁寧に、ゆっくりと読みます。最初を急ぐと、読みはあさくなります。書き手によって文体に個性がありこれになれることが必要ということもありますが、何をテーマとし、それにどのようにアプローチするかということはおおむね書き出しの部分におおむね出てきますので、それぞれの本の枠組みをつかむためでもあります。映画を観る場合にも最初はなかなか入っていけないことがありますが、最初をじっくり、丁寧にみると、映画の全体像の理解は比較的容易になります。もっとも映画は見る側のペースト無関係にどんどん進んでいきますが、読書の場合は読み手のペースの確保はできます。
3つ目は速読しないということです。ゆっくり吟味しながら読みます。たくさんのいい本があり、人生の時間は限られていると、早く読了して次の本へと進きたいとあせりがちになりますが、それはしません。読書の楽しみを犠牲にしてまで、多くの本を読んでも意味がないと考えるからです。仕事関係では、拾い読みしたり、斜めに読んで大意をつかんだりすることは始終ありますが、趣味の読書ではこれは禁じ手です。世の中には、速読の大家という人がいるようですし、1ページ分をあっというまに頭に焼き付ける速読法というのもあるらしいのですが、わたしは速読には関心がありません。
今日は、理屈っぽい話になってしまいました。恐縮です。