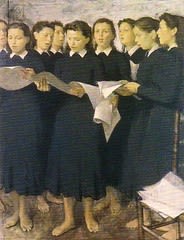馬鹿な、年甲斐もないことをしてしまった。瀬戸内国際芸術祭訪問1日目の晩、高松市内で酔ってこけ、足を痛めたのである。歩道と横断歩道の段差に酔って気づかなかったようである。不覚。この信号を渡れば、ホテルまでもう少しであったのに。
結局芸術祭は1日だけ、それも直島のベネッセ施設だけ廻るので終わってしまった。ベネッセの美術館なら芸術祭に関係なく訪れることができるのだが。なので、今回は国際芸術祭報告と言うより、ベネッセの3美術館、地中美術館、李禹煥(リー・ウーハン)美術館そしてベネッセハウスミユージアム訪問記である。
通常公立の美術館はまずハコありきで、そこに陳列できる大きさの作品しか展示することはできない。年に何回も企画展を開催するのが普通なので当然と言えば当然だ。しかし、ハコから造る私設の美術館では、企画展にとらわれることなく何を展示するかによってハコも設計することができる。その典型例、成功例が地中美術館である。
展示されている作家はわずか3人。モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリア。そしてハコを設計した安藤忠雄。ベネッセの会長福武總一郎が「「自然と人間との関係を考える場所」を追求した美術館」をつくりたいと、すでに蒐集していた自然を愛したモネの絵を展示、自然をモチーフにワイドな作品を発表していた現代美術家のタレル、空間芸術ですでに高い評価を得ていたデ・マリア、そして安藤を招請。安藤は兵庫県立美術館なども設計しているが、コンクリート打ちっ放しの武骨な幾何学形は、「自然」とは似つかわしくないようにも見える。しかし安藤は、阪神・淡路大震災で大きな打撃を受けた兵庫県で県立美術館のほかに、淡路夢舞台や六甲の集合住宅など自然の中に違和感なく生える制作もこなしている。そして今回、安藤が企図したのは小さな島の景観を損なわない、外からは異物の美術館があるとは分からない構造、そうすべて地中に建築することであった。
しかし、地中にあるからといって、外の世界と全く閉ざされたコンクリートのハコであっては単なる地下室である。そこで安藤は得意の光=陽光を取り入れる隙間と吹き抜けを大胆に配して、地中にあっても明るく、また外からは建物があるとは見えない空間を演出したのだ。
そして、空間芸術といえばデ・マリアの登場である。デ・マリアはもともとインスタレーションを得意とし、アルミニウムの他、大理石を使った簡明ながら大規模、圧倒的な迫力でミニマル・アートを牽引してきた。ミニマル・アートと自然?すぐには繋がらないようにも思えるが、そこは安藤のハコ。教会のようなおごそかな空間に大理石の大きな球体がぽつり。周囲にはキリストの磔刑を思わせる金色に彩色された木彫3本がいたるところに。ここでは何を意味するかではない、何を感じるかなのである。球体の上は空。
空は作品の一部である。そう認識させられたのがタレルの作品。実は「オープン・スカイ」と名付けられたものは本当の空ではなく人工的に作り出されたものであるそうだが、つくねんと石のイスに腰掛け、見上げたら本当の空が流れているようにしか見えない。雨の時どうするのだろうというは杞憂で、タレルの作品も空間と人間の関係をなき物にする妖術のようでもある。
晩年、視力をおとし、細かな筆致が不可能になったモネの睡蓮。大作としてはパリのオランジェリーにあるものが有名だが、ここの作品も有る意味負けていない。それは、齢80のモネが残る力を振り絞って描いたようにも見え、その迫力が少なからず感じられるからだ。
アートは作品そのものだけではない。それら作品を展示する空間もまたアートなのだ。ベルリンのゲマルデ・ガルリーのように絵画ばかりだが、空間も素敵な美術館がヨーロッパにはいくつもある。地中美術館は少し違う意味で作品とハコの共存を成功させた希有な例であり、現代美術の可能性を拓く大きな足跡でもある。
他の2施設も入館料はチト高いが、美術館建設という一大プロジェクトが隅々まで味わえる奇観の成功が、直島という瀬戸内の小さな島で展開されている。
結局芸術祭は1日だけ、それも直島のベネッセ施設だけ廻るので終わってしまった。ベネッセの美術館なら芸術祭に関係なく訪れることができるのだが。なので、今回は国際芸術祭報告と言うより、ベネッセの3美術館、地中美術館、李禹煥(リー・ウーハン)美術館そしてベネッセハウスミユージアム訪問記である。
通常公立の美術館はまずハコありきで、そこに陳列できる大きさの作品しか展示することはできない。年に何回も企画展を開催するのが普通なので当然と言えば当然だ。しかし、ハコから造る私設の美術館では、企画展にとらわれることなく何を展示するかによってハコも設計することができる。その典型例、成功例が地中美術館である。
展示されている作家はわずか3人。モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリア。そしてハコを設計した安藤忠雄。ベネッセの会長福武總一郎が「「自然と人間との関係を考える場所」を追求した美術館」をつくりたいと、すでに蒐集していた自然を愛したモネの絵を展示、自然をモチーフにワイドな作品を発表していた現代美術家のタレル、空間芸術ですでに高い評価を得ていたデ・マリア、そして安藤を招請。安藤は兵庫県立美術館なども設計しているが、コンクリート打ちっ放しの武骨な幾何学形は、「自然」とは似つかわしくないようにも見える。しかし安藤は、阪神・淡路大震災で大きな打撃を受けた兵庫県で県立美術館のほかに、淡路夢舞台や六甲の集合住宅など自然の中に違和感なく生える制作もこなしている。そして今回、安藤が企図したのは小さな島の景観を損なわない、外からは異物の美術館があるとは分からない構造、そうすべて地中に建築することであった。
しかし、地中にあるからといって、外の世界と全く閉ざされたコンクリートのハコであっては単なる地下室である。そこで安藤は得意の光=陽光を取り入れる隙間と吹き抜けを大胆に配して、地中にあっても明るく、また外からは建物があるとは見えない空間を演出したのだ。
そして、空間芸術といえばデ・マリアの登場である。デ・マリアはもともとインスタレーションを得意とし、アルミニウムの他、大理石を使った簡明ながら大規模、圧倒的な迫力でミニマル・アートを牽引してきた。ミニマル・アートと自然?すぐには繋がらないようにも思えるが、そこは安藤のハコ。教会のようなおごそかな空間に大理石の大きな球体がぽつり。周囲にはキリストの磔刑を思わせる金色に彩色された木彫3本がいたるところに。ここでは何を意味するかではない、何を感じるかなのである。球体の上は空。
空は作品の一部である。そう認識させられたのがタレルの作品。実は「オープン・スカイ」と名付けられたものは本当の空ではなく人工的に作り出されたものであるそうだが、つくねんと石のイスに腰掛け、見上げたら本当の空が流れているようにしか見えない。雨の時どうするのだろうというは杞憂で、タレルの作品も空間と人間の関係をなき物にする妖術のようでもある。
晩年、視力をおとし、細かな筆致が不可能になったモネの睡蓮。大作としてはパリのオランジェリーにあるものが有名だが、ここの作品も有る意味負けていない。それは、齢80のモネが残る力を振り絞って描いたようにも見え、その迫力が少なからず感じられるからだ。
アートは作品そのものだけではない。それら作品を展示する空間もまたアートなのだ。ベルリンのゲマルデ・ガルリーのように絵画ばかりだが、空間も素敵な美術館がヨーロッパにはいくつもある。地中美術館は少し違う意味で作品とハコの共存を成功させた希有な例であり、現代美術の可能性を拓く大きな足跡でもある。
他の2施設も入館料はチト高いが、美術館建設という一大プロジェクトが隅々まで味わえる奇観の成功が、直島という瀬戸内の小さな島で展開されている。