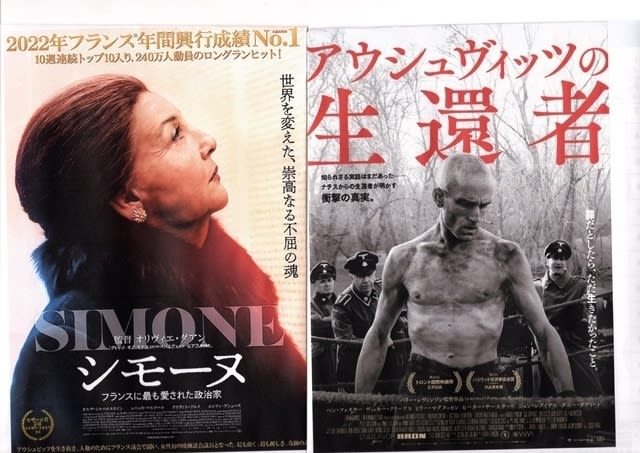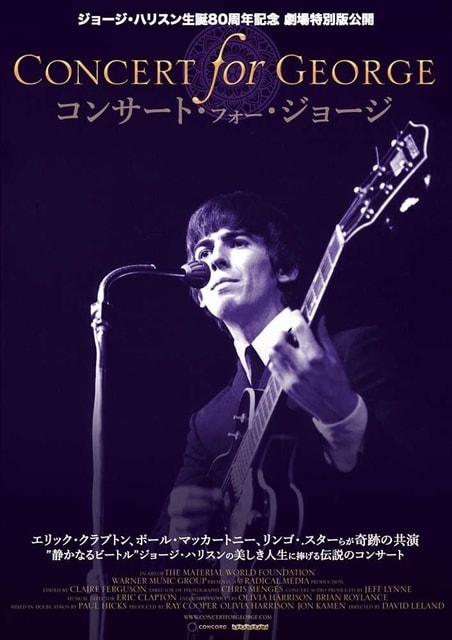私ごとで恐縮だが、甥がお連れ合いを失った。まだ42歳。母親を亡くした子どもは5歳。甥は「まだよく分かっていないのではないか」。体調不全と聞いてはいたが、お正月しか会わない程度なので、詳しくは知らなかった。甥の母(私の姉)によれば、「もともと病気を抱えていたが、コロナに勝てなかった」。父子にかける言葉も見つからない。甥の場合は、日々弱っていく妻を見ていて、半ば覚悟もあったかもしれないが、アントワーヌとまだ2歳に満たない息子メルヴィルの場合はどうか。夕方明るくコンサートに出かけた妻、母のエレーヌを見送ったばかりなのに。テレビや親族、友人からの連絡にコンサート会場で無差別テロルに巻き込まれたと分かった妻と再会できたのは3日後。美しく横たわっていた。
2015年11月13日夜。パリの数カ所をISIL(イスラム国、IS)のジハーディストが襲撃した。最大の犠牲者を出したバタクラン劇場に居合わせたのがエレーヌと友人ブリュノだった。事件後すぐに病院を探し回ったアントワーヌはやっとエレーヌに会えた後、パソコンにメッセージを書き連ねる。「ぼくは君たちを憎まないことにした」。瞬く間に拡散し、ビューは2万5千。もともとジャーナリストにして作家の彼は文才があったのだろう。しかし、怒りや恨みではなく、犯人らに対する穏やかな「憎まない」宣言はなぜこれほど人々の心を打ったのか。
実行犯たるISILの戦闘員が、その行動の背景に西洋社会に対する憎悪を抱いていたことは、正当かどうかは別にして多分間違いないだろう。そして、アントワーヌの理解によれば、戦闘員が望んだのは西洋社会のイスラム世界に対する憎悪を煽ることだった。しかし、彼はその土俵に乗らなかった。「憎悪で怒りに応じることは、君たちと同じ無知に陥ることになるから。君たちはぼくが恐怖を抱き、他人を疑いの目で見、安全のために自由を犠牲にすることを望んでいる。でも、君たちの負けだ。ぼくは今まで通りの暮らしを続ける。」
実行犯らが「無知」かどうかは理解の分かれるところだと思うが、少なくとも、アントワーヌはフランス社会が恐怖のあまり極端な監視国家、自由や民主主義を放棄することに断固反対する。自由、民主主義国家であり続ける限り、このような事件は再び起こり得るかもしれないのにである。これは、自由のためには憎しみの増幅という方法は取らないとする宣言だ。
王政を武力で倒し、共和政を獲得したフランスは国歌にまで「武器を取れ」とある。18世紀の武器はもちろん軍事力そのものを指すが、現代では言論の意味合いが大きいだろう、理想的には。現にフランスは中東地域で繰り返される戦乱に武力介入、武器輸出を行っている。だからISILがフランスを攻撃対象としたことは故なしではないのだ。
けれど、国家のような組織も「イスラム国」も一人ひとりの集合体である。一人ひとりの意志ではなく、組織の意思が個を圧殺、統制する思考回路そのものをアントワーヌは拒否したのだろう。さすが「一般意志」や「アンガージュマン」を生んだ国と言えるかもしれない。
ちょうど、映画公開と同時期にパレスチナのガザ地区を支配するハマスによる、イスラエル攻撃、そしてその反撃としてのイスラエルによる容赦ないガザ地区への攻撃で数多の死者が出ている。国家としてのイスラエルを認めないハマスには、人工国家イスラエルによる土地簒奪に対する憎しみが、ハマスによるイスラエル急襲に対し、イスラエルはホロコーストにも準え憎しみを増していると解説されている。とにかく「殺すな」しかないのだが、どこかで憎しみの連鎖を断ち切らなくてはならない。が、とても難しい。
アントワーヌは憎まないが「赦す」とは言っていない。国家犯罪、組織犯罪と個人による殺傷とは様相は違うだろうが、憎悪の放棄と赦しが人類社会に普遍的に存在する「争い」の特効ではない特効薬とも思えるのだが、和解の道のりは遠い。けれど希望だ。