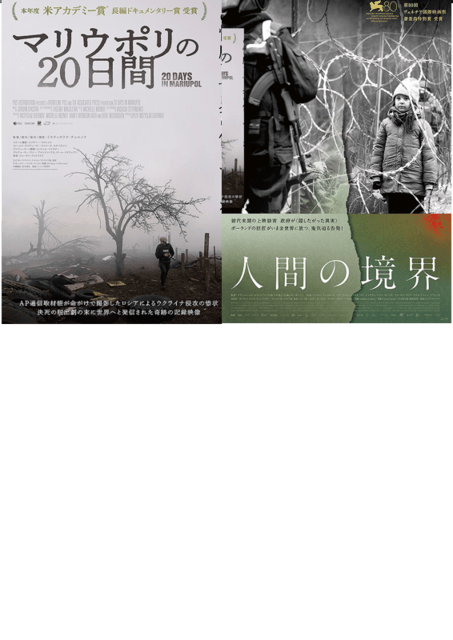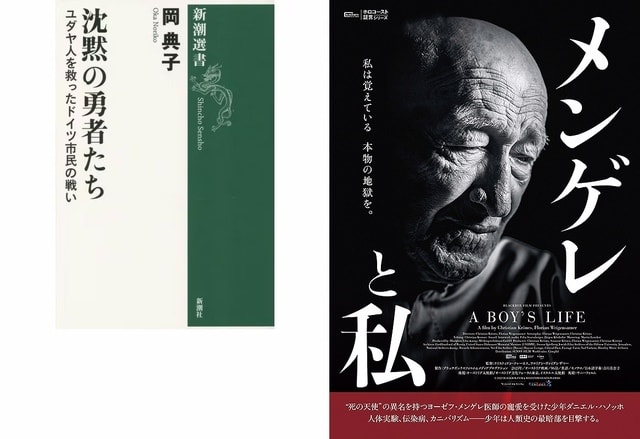タクヤには吃音がある。人前で話す最初の言葉が出てこない。だからあまり話さない。そんな彼をクラスメートは誰もがやりたがらないアイスホッケーのキーパーを押し付ける。でも、コウセイはそんなタクヤに寄り添っているし、タクヤもコウセイの前なら言葉にあまり詰まらない。
さくらは母の期待を受けてフィギュアスケートのレッスンに励んでいる。タクヤより少し年上、身長もある、二人に教え、アイスダンスを勧めるのは選手を引退し、コーチを務めるのは恋人五十嵐の田舎に移り住んだ荒川。五十嵐の地元は雪深い北海道の小樽近辺。タクヤ、さくら、荒川。この3人の一冬の物語。
主な登場人物が少ない。だからか一人ひとりの描き方が丁寧。話さないタクヤの心象はよく分かる。氷上に舞うさくらは女神だ。そんなタクヤの気持ちを知ってか知らずか、さくらも荒川も接する。やがて、スケートがそれほどうまくはなかったタクヤもメキメキ上達する。手を繋ぎ、揃って駆けるリンクの二人は前からコンビを組んでいたよう。しかし、成長期にある微妙な心の揺らぎ。残酷にも3人の関係は突然終わる。
監督・脚本・撮影・編集の奥山大史は本作でカンヌ国際映画祭で「ある視点」部門に正式出品された。「ある視点」部門とは、コンペティション部門とは別に主に若手(年齢というより作品数)作家の意欲的作品を取り上げるセクションで、過去には黒沢清が「岸辺の旅」で監督賞を受賞している。
本作でははっきりと描かれていない部分も含めて、どこかそれぞれ翳りを抱えている。タクヤは吃音であるし、父親もそうだ。さくらは母子家庭のよう。荒川と五十嵐はゲイカップル。そして深い雪景色が生活の音、喧騒を全て飲み込む。タクヤもさくらも思春期特有の照れと言葉の表現力に慣れていないせいか思いを表すことにはにかむ。荒川もなぜ選手をやめたのか描かれず、恋人のいる寂しい街に車で積める荷物だけで越してきている。
はっきりとしたハッピーエンドや結末がない分、いつまでも続くかのような物語。けれど思春期は短く、彼らを取り巻く環境、そして彼ら自身の変化もある。例えばタクヤのさくらに対する淡い気持ちは、北海道特有の粉雪のように春になると全く降らなかったかのように消えてゆく。タクヤは中学生になると道でばったり高校生になったさくらと出会う。ぎごちないが嬉しい。
なんと切ない物語だろう。3人が離れてしまったのは誰のせいでもない。誰かがそう仕向けたり、無理やり壊したわけでもない。けれど人間は別れるものだ。離れるものだ。特にまだ10代のタクヤとさくらには限りない将来がある。あの切ないひとときは、きっと成長の糧だったのだ。タクヤにとって輝いて見えたさくらが「ぼくのお日さま」であることは間違いないが、おそらくさくらにとってもタクヤと息のあったレッスンの時間が「お日さま」で、どこかパッションをぶつける先のない元スター選手の荒川にしても二人の子どもとレッスうが「お日さま」であったろう。
あの切なさがとてもとても愛しい作品だ。