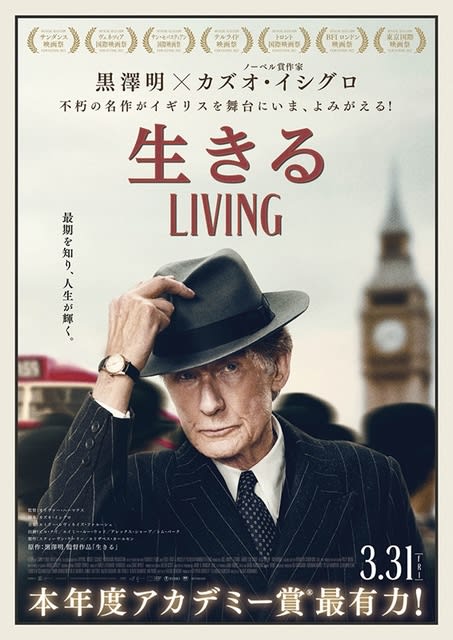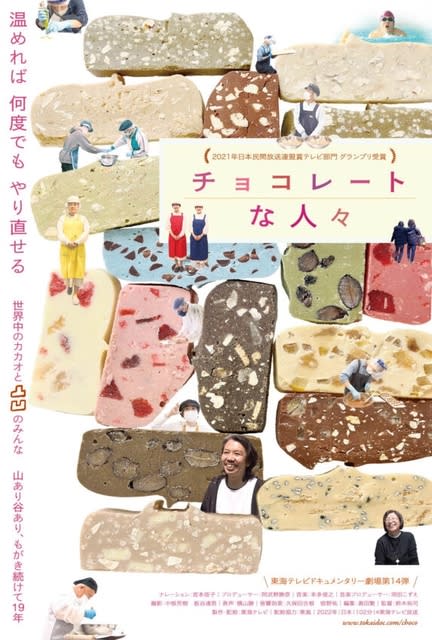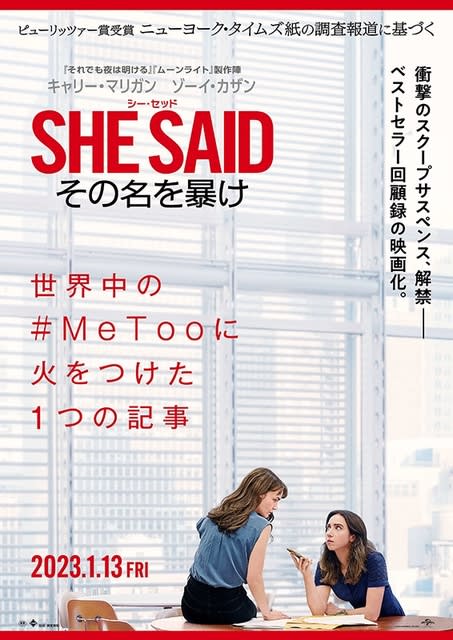ホフマンが何度もタバコに火を着ける。その炎と放つ光ははかない。そのはかなさ故か、ホフマンのこれまでの人生を想起させるメタファーか、炎はすぐに消える。けれどもホフマンの思いは続く。
ホフマンはナチス政権下で同性愛者との理由で拘束、収監されている。ナチスからドイツ市民を解放した連合軍のもとでも同性愛行為は違法。だから、強制収容所からそのまま解き放たれることなく、戦後ドイツの刑務所に移送されたのだ。他者を傷つけるなどの何らかの犯罪を犯したわけではない。性志向そのものが犯罪であった時代の話である。しかし、同性愛が非犯罪化されるのは東ドイツで1957年、西ドイツでは1969年である。しかも女性の同性愛は「ない」ものとして、男性だけを罰する(しない)法改正であった。男性たちは違法な逢瀬をどこでしていたか。公共トイレである。そこにも監視カメラが据え付けれ、違法=逸脱行為をなす男たちを見張っていた。そのフィルムが回されるところから本編は始まる。
ホフマンが移送された先で、同室になったヴィクトールはあからさまに拒否する。「変態と同室でいられるか!」。刑法175条と収監者の罪状が明記されているからだ。だが、ホフマンの腕に強制収容所にいたことの証としての認識番号を見て、ヴィクトールは「(刺青で)消すか?」と提案する。そこから、ヴィクトールとホフマンの友情は始まる。
岸田文雄政権はG7の中で日本だけがLGBT(Q)に対する法整備が遅れているとの実態から、急ぎ「理解増進法」を成立させた。法はあくまで「理解増進」であって「差別解消」でないことが問題と当事者団体等から指摘されている。同法の審議段階では与党自民党内から、「女性」と自称する男性の女性トイレや女風呂に入ることを妨げられないのではとの懸念が反対理由と示された。トランスジェンダーの当事者が、自己の出生時の性とは異なる性で社会生活を送る場合、公共トイレなどの施設を利用する際には、できるだけ外見的にも自分自身の意識ともトラブルのない段階でやっと、自己認識の性の側を選ぶという実態を無視したヘイト言説だとも思うが、今般の議論の遅れにかなり寄与しただろう。首相秘書官による差別発言もあった。
時代はもっと頑固である。ホフマンは何度も収監される。でもホフマンは刑務所内も含めて自己の愛を止めようとしない。いや、止めることなどできないだろう。興味、趣味ではなく性向であるのだから。いや、性向でさえもない。本源的な愛だ。ホフマンが刑務所への出入りを繰り返す中で、殺人を犯し長期収容されているヴィクトールに幾度も出会う。ヴィクトールには分かるのだ。ナチスの時代、強制収容所をくぐり抜けてきたホフマンこそ、自己を曲げない、曲げられない人間であることを。罰するべきではない個人の性向を法律で縛ることの不平等さを。
イスラム社会をはじめ、現在も同性愛を違法とする国は多い。しかし、あれだけ異性愛を最上のものとしてきたカトリックの国でも同性婚は合法化されてきた。一人ひとりが幸せを得るための価値観は変わっていくものだ。そしてそれを示すものとして、ヴィクトールという得難い友人を得たホフマンにとって、刑務所こそ自由で、外の世界には自分の居場所のない不自由な世界というパラドックスも本作は明らかにしている。