〇大室幹雄『檻獄都市:中世中国の世界芝居と革命』 三省堂 1994.7
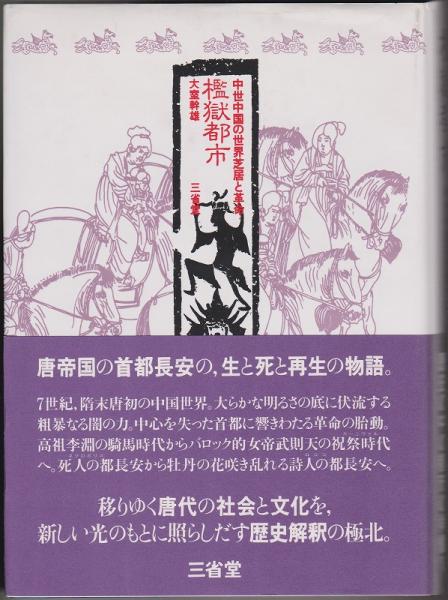 年末に中国ドラマ『風起洛陽』を見ていたら、むかし、則天武后のイメージについて、大きな影響を受けた大室幹雄の本を読み返したくなった。大室幹雄さん、Wikipediaでは「歴史人類学者」と紹介されている。1981年の『劇場都市』に始まり、漢~唐末を扱った中国古代都市文明論シリーズを計7冊出しており、私は90年代に耽読した。さて武則天が登場するのはどの1冊だったか、思い出せず、公共図書館をハシゴして確認し、ようやく本書を見つけ出した。
年末に中国ドラマ『風起洛陽』を見ていたら、むかし、則天武后のイメージについて、大きな影響を受けた大室幹雄の本を読み返したくなった。大室幹雄さん、Wikipediaでは「歴史人類学者」と紹介されている。1981年の『劇場都市』に始まり、漢~唐末を扱った中国古代都市文明論シリーズを計7冊出しており、私は90年代に耽読した。さて武則天が登場するのはどの1冊だったか、思い出せず、公共図書館をハシゴして確認し、ようやく本書を見つけ出した。
本書前半の主人公は、唐太宗・李世民。「最初は鷹、つぎは杜鵑(ホトトギス)、第三は鸚鵡、そして終わりは阿呆鳥」として描かれる。唐を建国した父の李淵(唐高祖)に従う、颯爽たる青年将校としての「鷹」の時代。兄の皇太子・李健成と弟の李元吉を殺害し、父を幽閉して皇位に就いた「杜鵑」の時代(ホトトギスは他の鳥に自分の卵を育てさせる「托卵」という習性があることから、親兄弟を蹴落とし、野心を遂げたことをいう)。即位後の太宗が、諫臣・魏徴をはじめとする廷臣たちと繰り広げた言語ゲームを著者は「鸚鵡」の時代と呼ぶ。私は『貞観政要』の抄訳本しか読んだことがないが、全体を読むと、劇場的な言語ゲームの間に、ふと太宗の本音が漏れている箇所もあるようで、著者の解読がおもしろかった。そして老いては「阿呆鳥」となり、凡庸な李治(高宗)を皇太子に立てて没する。
後半の主人公は、高宗の後宮で美貌と多産と政治的才覚(狡知、果断)を武器に勝ち上がり、ついに皇后の座に就く武則天である。高宗の死後は、唐皇帝家の宗室をほとんど粛清し、周王朝を樹立し、皇帝と号する。著者は、唐王朝に「遊牧草原文化に起源する女たちの明るく暢びやかな活動性」があったことを認めつつも、「むしろ性別を超越した、一個の卓抜な政治的人物、少なくとも宮廷政治の天才が彼女だった」と絶賛する。高宗もなかなか健闘したけれど、やはり天才にはかなわない。中国の伝統的な史論家が高宗をことさら暗愚に描くのは、強い卓れた妻を持った男はろくでなしという儒教的偏見によるのではないか、という指摘もおもしろい。
李世民と武則天を「主人公」と仮に呼んだが、著者にとって、歴史の主人公は都市そのものである。本書には、隋の文帝によって建設された長安の都市計画と、それを「居抜き」で奪い取った李淵・李世民によって加えられた変更が、実に詳細に具体的に記述されている。中国の考古学雑誌などから転載された興味深い図版も多数。かつて(ウェブなどの情報源がない時代に)私がこのシリーズにハマった理由のひとつはこれだ。ちなみに書名の「檻獄都市」とは、高い土塀に囲まれ、一種の「檻」である坊が整然と並ぶ長安の平面プランに由来する。
その長安を打ち捨てて、武則天が、恐怖と祝祭のバロック・ユートピアを打ち建てた舞台は神都・洛陽である。武則天の巨大癖(メガロマニイ)の現れである壮麗な巨大建築、明堂・天堂・万象神宮についても詳しい。ドラマ『風起洛陽』との関係では、密告を受け付ける銅匭(銅製の箱)が朝堂に設置されたことが出てくる。また廷臣の粛清に活躍した秘密警察組織があったことも。武則天の自由闊達な人材登用方針により、海千山千のやくざものたちが洛陽に集まり、よくも悪くも多彩な才能を発揮することができた。
それから、巨大な食糧備蓄庫である含嘉倉も本書に出てくる(これは忘れていた)。江南産の穀物は、大運河の終点・汴州(開封)から洛陽に搬入され、さらに西の長安に運ばれたが、洛陽と長安の間には三門峡という難所があった。汴州から洛陽周辺に巨大な穀物庫群を作ったのは隋の煬帝で、武則天はこの食糧政策を踏襲した。含嘉倉の考古学調査からは、武周時代の食糧管理行政の卓越した実態が分かるという。
武則天の詩文愛好と牡丹改良に認められる「華麗なものへの心情の傾き」(江南文化への関心と言ってもよい)は、次の時代(玄宗)の長安に引き継がれ、灰色の檻獄都市だった長安は、遊蕩的で性愛的な園林都市に変身を遂げる。この華北/江南の対立と混淆は、つねに中国史を貫くテーマでもある。
あと武則天の容姿は「豊碩、方額、広頤」と言われているのだな。『風起洛陽』の聖人役の詠梅さん、ぴったりである。90年代に本書を読んだときは、まだ中国ドラマの視聴経験が全くなかったのだが、今回、隋の煬帝や蕭皇后は『隋唐演義』の配役で想像していた。隋に滅ぼされた陳の王妃で煬帝の皇后となった蕭氏は、隋滅亡後も80歳まで生きのびて、唐太宗と会話を交わしていたりする。唐建国の功臣たちの晩年、その後裔たちの運命も味わい深い。
























