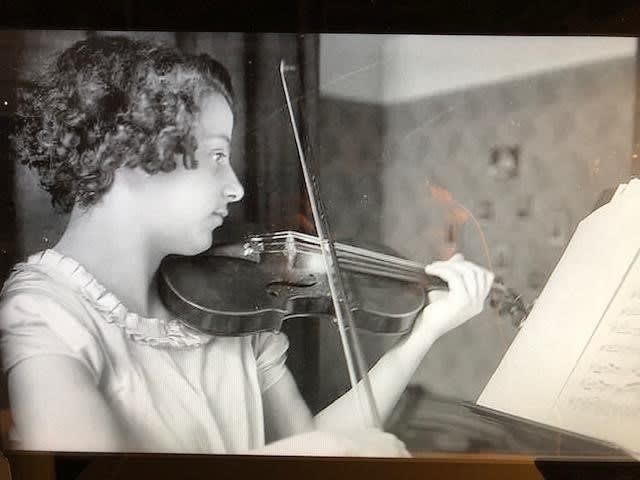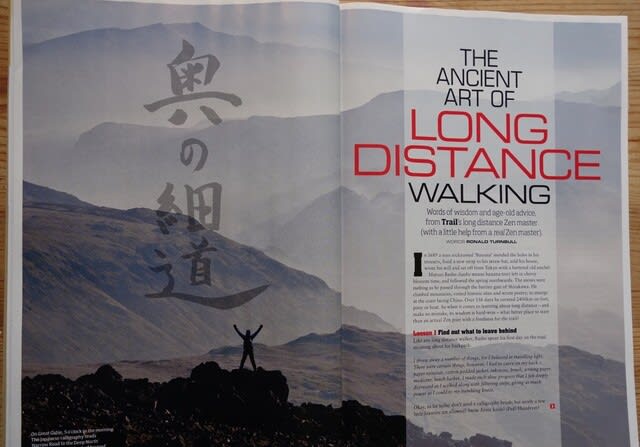「ナポリ、そして浜辺の歌」
ナポリへ行ったのは何年前になるだろう。
女房のキャロラインとホリデーをシシリーで過ごす予定だったけど、彼女が急に行けなくなり、予定を変更して僕一人でナポリへ行くことにした。
なぜ、ナポリだったのか?
ナポリの西方に浮かぶカプリ島の「青の洞窟」を訪ねたかったのと、本場のピッツァを食べたかったこと…が、その理由かな?
僕が初めてピッツァを食べたのは、上京した20歳の頃、東京は銀座でのことだった。それまで、なぜかピッツァの存在はまったく知らなかった。
ペスカトーレと名付けられた、ムール貝、アサリ、海老、ホタテ、イカ、アンチョビなど、魚介類入りのその味は衝撃的だった。この世にこんなにうまいものがあったのかとまで思った。
そして、イタリアのナポリが、ピッツァ発祥の地だとも知った。その後、いろんなピッツァを食べたけど、やっぱりペスカトーレに惹かれるなあ。
で、いつの日かナポリでペスカトーレを食べたい…と思うようになったのは、ま、当然ですよね。
ナポリ市内の安宿で荷をほどき、さっそく、ツーリストインフォメーションのお嬢さんが「とても美味しいですよ」と薦めてくれたピッツァ専門店へ向かった。
ナポリのタクシーには気をつけろとの友人の忠告に従い、宿にお願いしてタクシーを呼んでもらった。市内から15分ほど、ベヴェレッロ港のすぐ近く、潮の香りがするところに、その店「ジャン・フランコ」はあった。店の中に入った途端、僕は、あゝ、来てよかったと思った。
海辺に近いその店の、まず、インテリアに僕は目を見張ったんです。
幅20センチほどの板張りの壁と天井は、ライトブルーにペイントされ、フローリングのライトブラウンにとても合っている。そして、いくつかある大きく開放的な窓の枠はすべて白くペイントされていた。
いやあ、いかにも海辺の雰囲気やなあ…
海が見える窓辺の席に案内してくれたウェイトレスに、まず、イタリアンビール・ペリーニの生を注文し、そして、メニューにペスカトーレを見つけたときは、やや興奮してしまった。
そうなのよ。ついに、ナポリでペスカトーレや! 東京の銀座で初めて食べて以来、すでに30数年になるんとちゃうか?
ウェイトレスが「日本人ですか?」と訊く。そして「うちの料理人に日本人がいますよ」と言ったのには驚いた。…こんなとこに日本人がいるんや!…
で、わざわざ厨房から出てきて、僕にペスカトーレを運んできた青年は、ニコニコと、とても嬉しそうに自己紹介した。
「僕、三谷圭介と言います」
年の頃、二十数歳だろうか。その圭介君がいう。
「ほとんどの日本人ツーリストは、市内の有名店へ行くんで、この街はずれの店に来る方は少ないんですよ。よく来てくれました」
で、僕は、圭介君に、その昔の、僕とペスカトーレとの銀座での出会いを、やや興奮しながら説明した。
「じゃあ、わざわざペスカトーレを食べにナポリですか?」と、ナポリに来てすでに二年が経つという、笑顔がとても爽やかな圭介君は感激してくれた。
ジャン・フランコのペスカトーレは格別に美味しかった。やっぱり日本の味とは、ちょっと、いや、かなり違うなあ。
その、本場のピッツァを、ペリーニの生を飲みながら食べたあと、ナポリ近郊が産地だと言うフラスカーティ(辛口白ワイン)を、シシリーで水揚げされたマグロのカルパッチョとともに頂いた。
薄くスライスした鮪のイタリア風刺身・カルパッチョ…これも、とても美味しかった。フラスカーティにぴったりのその味は、港に落ちる夕陽の眺めに、とても相応しいものだった。
そして、この店に来て本当に良かったとしみじみ思った。脇に美人がいたらもっと良かった。いや、あのー、もちろん奥さんのキャロラインのことですよ。
私服に着替えた圭介君が
「僕は街中に住んでるんですけど、今日は早番なんで、車でウマさんを送っていきますよ」お言葉に甘えることにした。
そして、僕の滞在先とそれほど遠くないアパートに車を置いた彼と、すぐ近くの彼の行きつけのバーで、ゆっくり話をすることが出来た。
以後、ナポリ滞在中の8日間、ほとんど毎日彼と会うこととなった。奇遇と言うより、思いがけない、とても嬉しい出逢いだったですね。
ところが、それから三年半後、神奈川県の逗子で、彼、三谷君と再会することになるとは、その時は夢にも思わなかったけど…
バーでは、彼お薦めのグラッパ (イタリア産焼酎?)で、まず、乾杯した。そして、興味しんしん、彼の話を聞いた…
神奈川県逗子市出身の三谷圭介君は、高校卒業後、大阪の調理師学校で二年間西洋料理を学び、卒業後、東京は吉祥寺のイタリアンレストランに三年勤めた。
このレストランで、主にピッツァの調理を任された彼は、オーナーシェフに
「イタリアで本格的にピッツァの修行をしてみないか」と言われたのがきっかけでナポリに来ることになったと言う。
今では言葉にもほとんど不自由せず、毎日が楽しい上、店のオーナーシェフ、ジャン・フランコが、日本が大好きな人で、圭介にとてもよくしてくれると言う。
そして、圭介は、今では、ナポリが第二の故郷だと思うになったとも言う。
逗子、そしてナポリ…素敵な話だよねえ。
ここ、ジャン・フランコのピッツァは、大きな石の窯の高熱で、たった1分ちょっとで焼きあげると言うんで驚いた。ガスオーブンを使う吉祥寺の店とはかなり違うらしい。
「やっぱり薪をふんだんに使った高熱で焼かないとダメなんです」と圭介君は言う。僕は、その生地の旨さに感心した。
地元イタリア産の小麦粉を使っているというジャン・フランコのピッツァの端っこはやや厚く、軽く焦げていて固そうに見えるけど、実はとても柔らかく、しかも香りが香ばしい。
つまり生地だけでも美味しいのよ。もちろんビールにこの上なく合う。さらに、シシリーで水揚げされたと言う、ムール貝、エビ、イカ、ホタテなどの新鮮な魚介類の絶妙な歯応えが、モッツェレラチーズにこの上なく合い、申し分なく美味い。もう、絶妙のペスカトーレと言っていい。
僕はタバスコが好きなので、ウェイトレスにタバスコを頼んだけど、タバスコは置いてないと言う。その代わり、辛味のあるオイルをくれた。これが良かった。タバスコよりペスカトーレに合う。
圭介君によると、イタリアのピッツァ店にはタバスコは置いてないそうや。それにしても、ペスカトーレが好きでよかった。
ま、そんなわけで、ナポリで最高に幸せなウマでござった。
あと半年でナポリでのピザ修行を終え日本に帰るという圭介君と、例のバーで三回目に会った時だったかな。グラッパでかなりご機嫌になった彼が、ふと、こちらで知り合った日本人女性のことを語り出したんです。そして、僕は、その話に引き込まれてしまった…
「こちらに来てすぐのことだったんだけど、ある日、仕事から帰り、部屋のドアを開けようとしたら、隣の部屋から歌声が聞こえて来たんです。耳を澄ますと、なんと日本の歌なんです。で、思わず、ドアをノックしたら、とても綺麗な日本の女性が出て来たんで、もう、びっくり。僕の母親ぐらいの年齢かな? 聞くと、僕より一ヶ月ほど早くナポリに来たとおっしゃる」
「その鎌倉出身の河合美津子さんとは、同じ神奈川出身ということもあり、すぐ親しくなりました。彼女もナポリとピッツァが大好きで、もちろんジャン・フランコにも食べに来てくれるようになったんです。美津子さんもウマさんと同じでね、いつも決まってペスカトーレを食べてました」
「この美津子さん、とても歌が好きな方で、彼女の部屋からは、よく歌声が聞こえてました。すごく澄み切った透き通るように綺麗な声で、思わず聞き惚れてしまいました。ところが、いつも決まって同じ歌なんです。それでね、ある時、訊いてみたんです。その歌、なんて言う歌ですか?」
「浜辺の歌…私の大好きな歌よ…」
「美津子さんは、生まれ育った地元の鎌倉から近い由比ヶ浜が大好きで、小さい時からその砂浜をよく散歩したそうです。そんな時、必ず、浜辺の歌を口ずさんでいたと言うんです。そして、今でも嫌なことを思い出した時など、必ずこの浜辺の歌を口ずさむとおっしゃる。
この歌を唄うと、心がとても和やかになるんですって。それでね、彼女に歌詞を書いてもらい、いつの間にか僕もこの歌を唄うようになったんですよ。ウマさんはこの歌、知ってます?」
知ってるどころじゃないよ。僕も浜辺の歌好きだなあ。好きな日本の歌はたくさんあるけど、ひょっとして浜辺の歌が一番好きかも知れないね。歌詞にある〈あした〉の意味が〈朝〉だと知った時は驚いたけど…
あした浜辺を さまよえば
昔のことぞ しのばるる
風の音よ 雲のさまよ
寄する波も 貝の色も…
ゆうべ浜辺を もとおれば
昔の人ぞ しのばるる
寄する波よ かえす波よ
月の色も 星のかげも…
…それで、その美津子さん、今でもナポリにいらっしゃるの?
ところが、思いもかけない、そう、ちょっと悲しい話になった…
「いえ、…実は彼女…亡くなったんです…二ヶ月前に…」
「ある日、僕の部屋を激しくノックした彼女、とても苦しそうに、身体中痛くてという…僕はすぐに救急車を呼びました。
で、翌日、病院に美津子さんを見舞った僕に、医師は、乳癌ですが、すでに全身に癌細胞が回っていて、もう手遅れです。あと一ヶ月は持たないだろう」
その告知を聞いた美津子さん…
「圭介、お願い、鎌倉にいる娘に連絡してちょうだい」
飛んできた美津子さんの一人娘、奈美恵と圭介は今後の策を話し合った。すぐ日本に連れて帰りたいという奈美恵に、圭介はもちろん同意した。ところが、美津子さん本人は
「日本には、今すぐ帰りたくない。もう少しナポリにいたい」
圭介と奈美恵は、何度も話し合った結果、そんな美津子さんの意思を尊重することに決めた。
そして、二人は、車椅子で美津子さんをジャン・フランコへ連れて行き、美津子さんは大好きなペスカトーレを、しみじみと食べたという。
圭介と奈美恵は、港の外れにある浜辺に美津子さんを連れて行った。
美津子さんは、地中海に落ちる夕陽を眺めながら、透き通るような声で浜辺の歌をゆっくりと唄ったそうや…
僕は美津子さんに会ったことはないけれど…その光景、目に浮かびますね。
🎵 ゆうべ浜辺を もとおれば(さまよえば)…
美津子さんは、人生の最期に、まさに〈ゆうべ〉…つまり、夕陽に染まるナポリの浜辺を目に焼き付けたんですね。
なぜ、美津子さんはナポリに来たのか?
圭介が奈美恵から聞いた話によると、実は、心を病み躁鬱の激しい御主人によるDV、つまり家庭内暴力に耐えかねて、美津子さんは日本を逃げ出してきたらしい。
結局、美津子さんは、愛したナポリで最期を迎え、そして荼毘に付された。遺灰の半分は、本人の遺言通り、奈美恵と圭介がナポリの浜辺に撒いた。そして、奈美恵は遺灰の半分を抱いて日本に帰ったという。
ま、そんなわけでね、僕のナポリでのホリデーはジャン・フランコのペスカトーレと共に、嬉しさと、ちょっぴり悲しさを伴った、ちょっと忘れられない想い出となったわけなんです。
それからほぼ二年後、スコットランドの僕に、懐かしい圭介から連絡があった。
…ウマさん、日本に来る機会があれば逗子に来てくれませんか? 僕、自分の店をオープンしたんです。ウマさんには是非来て欲しい…
そして翌年、日本に行く機会を得た僕は逗子を訪れた。
逗子の海岸沿いを走る道のやや高台に圭介の店はあった。その、さりげない小さな看板に書かれた店名を見て、僕は唸ってしまった…
「ピッツァの店・浜辺の歌」…
そして、店内に入った僕はさらにびっくりした。
壁、天井はライトブルー、フローリングはブラウン、遠くに逗子の海が見えるその窓枠は、綺麗に白に塗られている…そう、店の規模は小さいけど、まるでナポリのジャン・フランコのインテリアやないか!
イタリアンビール・ペローニを持ってきたウェートレスが、ニコニコと僕に自己紹介した。
「初めまして、私、奈美恵です。ウマさんのことは圭介から聞いています」
驚く僕に、キッチンから出て来た圭介が言った。
「実は、ナポリから帰って二ヶ月後に僕たち結婚したんです。美津子さんへの結婚報告代わりに、彼女の遺灰を由比ヶ浜で二人で撒いたんですよ。浜辺の歌を唄いながらね」
僕は、思わずジーンときてしまった、というか、もう、胸が詰まって言葉がなかったですね。
不動産業をしていた奈美恵の父親、つまり美津子さんの夫もすでに亡くなっていて、その遺産が店の開店資金になったと言う。
ペローニを飲みながらナポリを思い出していた僕は、テーブルのメニューを開いた。もちろん、注文はペスカトーレに決まっている。城ヶ島を始め、三浦半島のあちこちから新鮮な魚介類が豊富に入荷すると圭介は言う。
ところが、メニューにペスカトーレがない、どこにも書いてない。エーッ? なんでー? キッチンから圭介が言った。
「ウマさん、メニューをよーく見て!」
メニューの一番上に「浜辺の歌」とあり、魚介類のピッツァとの説明があった。僕は思わずニッコリ膝をたたき、キッチンの圭介に、両手の親指を立てた。
ナポリ…逗子…そして、ピッツァ〈浜辺の歌〉…
あした浜辺を さまよえば…
昔のことぞ しのばるる…
追記:
「浜辺の歌」を開店して3年後、圭介にナポリのジャン・フランコから連絡があった。老齢で引退することになった彼には後継者がなく、店を処分することになったけど、もし圭介が店を引き継いでくれるのなら彼に譲るとのことだった。
とにかく何年でもいいから圭介に店をやってもらい、いずれ日本に帰る時がくれば、店の窯など持っていっても良いとまで言われた圭介は、奈美恵の賛同も得て「浜辺の歌」を閉め、二人で第二の故郷ナポリに戻った。
ジャン・フランコ、圭介、美津子、奈美恵…
ナポリが縁で結ばれた彼らを思うと、なぜか胸が熱くなるウマでござった。
そして、いつの日か再度ナポリを訪れ、ジャン・フランコで、奈美恵にペリーニの生を注文し、そしてもちろん、圭介の焼くペスカトーレを食べるつもりでいる。