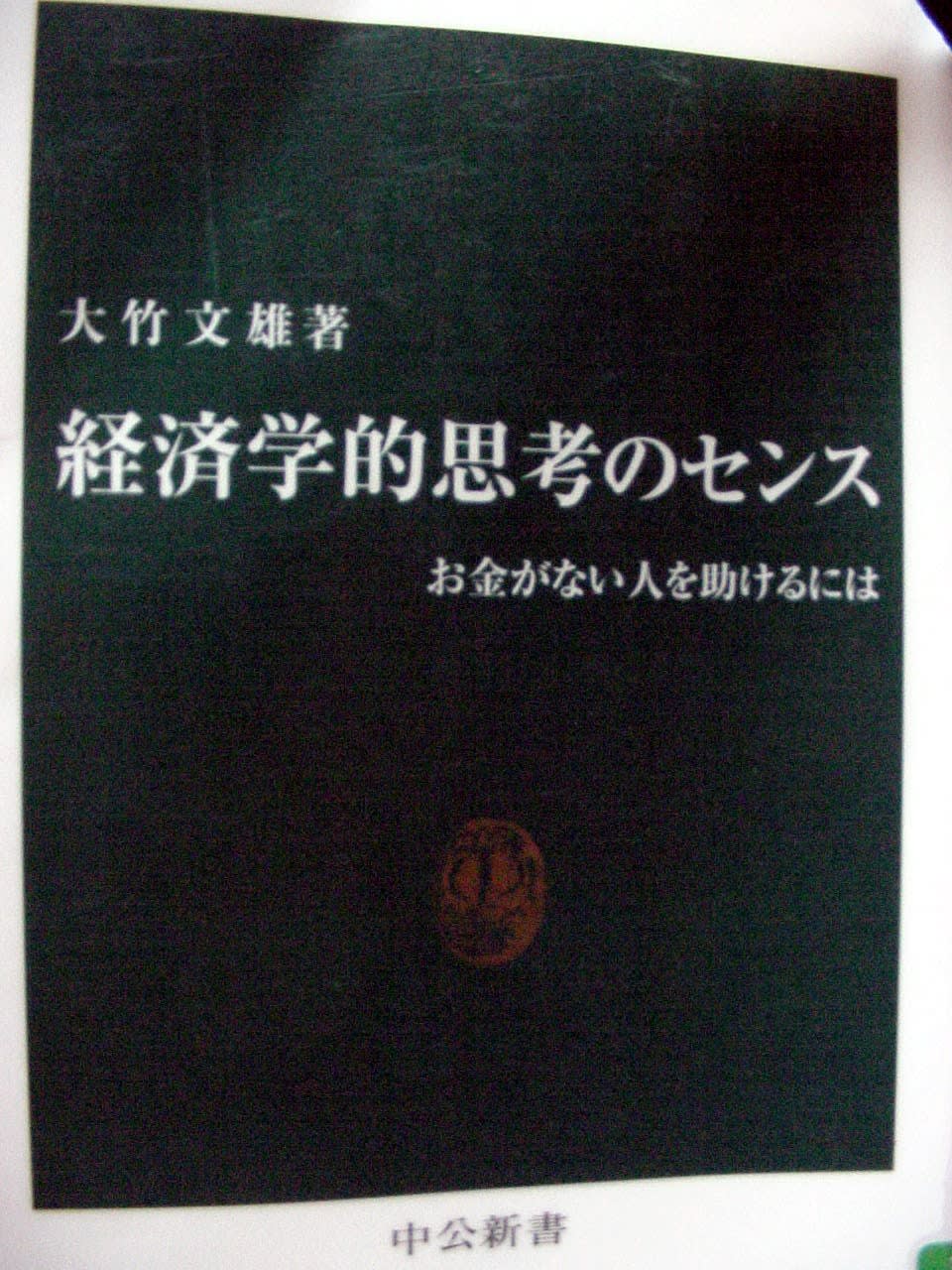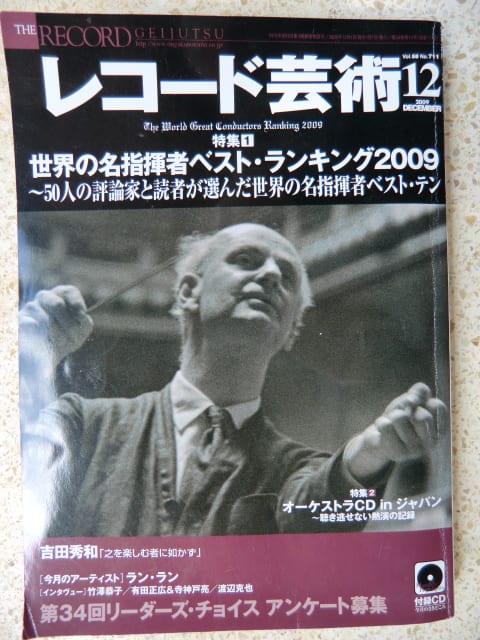「猫の額」ほどの我が家の庭に咲いていたピンクの百合の花。

日頃から殺風景なオーディオ機器の画像が多いのでたまにはイメチェンのつもりで載せてみた。
さて、このたび7月1日付の異動で娘が福岡から他県に転勤することになった。
異動は組織人としての宿命なので何もしてやれないが、以前から「どこに替わっても日経新聞だけは毎日読んでおくように」とアドバイスしているが、実はもう一つ内心ひそかに望んでいることがあってそれは「部下を定時に帰す」よう心がけること。
これには有名な本がある。

読まれた方も多いかもしれない。著者は東レ経営研究所社長(当時)の「佐々木常夫」さん。
本書の内容を要約すると、「肝硬変のため入退院を繰り返し「うつ病」を併発した奥さんと自閉症の長男を含む3人の子供を育てるために、毎日夕方6時に退社して家事の一切をやる必要に迫られたことからくる合理的な仕事術」を述べた本。
何といっても題名がいい。
「部下を定時に帰す」なんて、いかにも立場の弱い者を大切にする思想が感じられる。
業績を上げるために人を目一杯こき使おうとするのが普通の企業である。中には超過勤務手当てを支払わないで済むように名前だけの店長(管理職)にして過重労働を強いる”けしからん”会社があったりする。
「企業は人なり」で、こういう「人を大切にしない、育てようとしない会社」は早くつぶれてしまったほうが世の中のためにはむしろいい。
ふと自分の現役時代のことを想い出した。
勤務する部署によってマチマチだったが、毎日、夜の9時ぐらいまで残業が当たり前の職場がいくつもあった。早く家に帰って「オーディオ」をいじりたいのはヤマヤマだけど忙しくてそうもいかない。薄給なりとも当時は何せ両肩に妻子が乗っているからね~(笑)。
一番、感性が瑞々しくて豊かな若年時代がこんな調子で、加齢とともに感性が鈍り高音域が段々と聴こえづらくなった今の時期になって時間がたっぷりあるとは、世の中皮肉なもので「人生そうそううまくは運ばない」ことを思い知らされる。
それはともかく、今は「働き方改革」真っ盛りの状況で何とも「いい時代」になった。「ワーク・ライフ・バランス」つまり「仕事と生活の両立」なんて、当時はそういう生易しい時代ではなかった。
しかし、中には明らかに上司の指示がまずいために無駄な残業があったのも事実で、「残業の量は上司の出来具合に左右される」のは明らかだし、昔も今も原則として「上司の指示は絶対」なのはやはりキツイ。
「部下は上司を択べない」悲哀をそこかしこに味わったが、これは組織に勤める以上誰もが痛感し、経験することだろう。
こういう中、「部下を定時に帰そう」という姿勢をもち、努力してくれる上司に巡り会えるのは稀だしホントにありがたいことだと思う。
ただし、自分の経験からすると残業する側にもいろんなタイプがあって「十把ひとからげ」とはいかないのも事実。たとえば意地の悪い見方かもしれないが次のような例もある。
☆ 「超過勤務手当て」を目当てに残業したがる人間
☆ 家庭での居心地が悪いので出来るだけ会社に残って残業し「家では寝るだけ」にしている人間
☆ 残業をこなすことで「仕事をした」という自己満足に浸りたがる人間
本書の場合、著者が課長になって新しい職場に赴任したときに部下が目一杯残業をしていたので無駄を無くそうと具体的に取り組んだ話である。
通常、部下が残業をしているときの上司の対応としては
1 一緒に残業をする
2 管理職には「超過勤務手当て」が支給されないので見て見ぬ振りをして早めに帰る
3 部下の残業を無くそうと努力する
の3つに絞られるが、1は著者の家庭の事情があって到底ムリ、そこで2か3の選択になるのだが安易な選択の2に走らないのが、なかなかご立派。しかも通常、家庭がそういう事情ならアッサリ「出世」を諦めるところだが、この方は後々「社長」にまで上りつめる粘り腰がすごい。
とにかく、本書はそういった視点に基づいているので「精神論」ではなくて、現場で鍛え上げられた「実践論」に終始しているので分かりやすい。
「会議を半分に減らす」「会議の時間を半分に短縮」「資料は事前配布」「簡潔な資料」「重要ではない業務の切捨て」など当たり前の対策が緻密な現状分析のもとにきめ細かに綴られている。
組織で働く人にとって管理職はもちろんだが、これから昇進という方にも参考になりそうな本である。