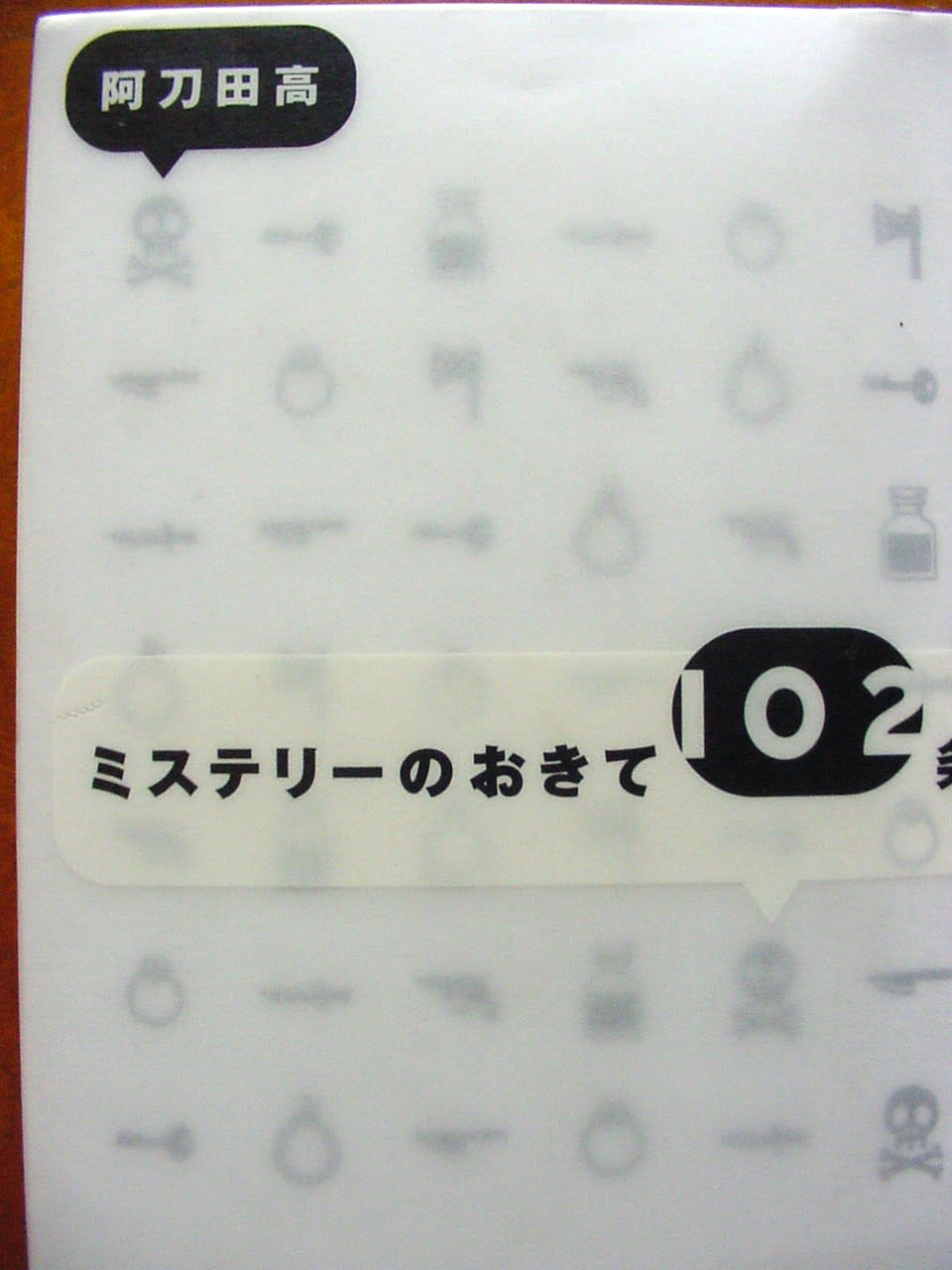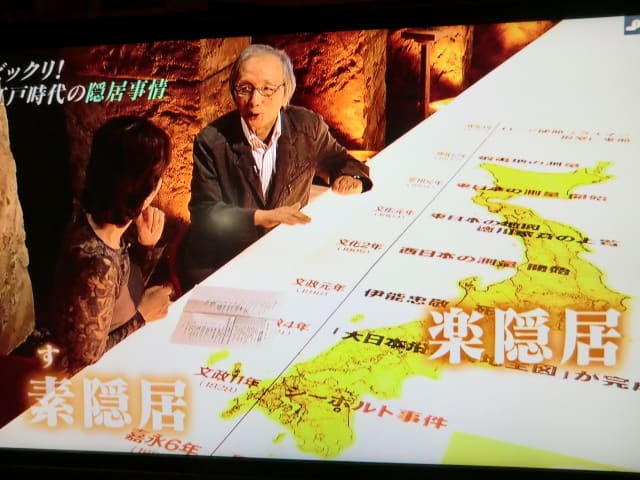今年(2017)から「月曜日」に限って、これまでのブログの中で今でもアクセスが絶えない記事をピックアップして登載しているが、今回は7年ほど前に投稿したタイトル「タンパク質の音楽」である。(「復刻シリーズ」)
2回に分けて投稿していたものを1本にまとめたので長くなったが悪しからず。それでは以下のとおり。
音楽の効用といえば通常、ストレス解消~精神の高揚などが言われているが、それ以外にもたとえば乳牛にモーツァルトの音楽を聴かせると乳の出が良くなったとか、トマトに音楽を毎日一定時間聞かせると成長が促進されるなどの不思議な現象の話もしばしば散見する。
その因果関係については科学的な根拠がハッキリと示されたわけでもないので「偶然の産物」とか「眉唾モノ」という受け止め方が一般的。
しかし、こうした生物と音楽とを結びつける不思議な現象の「科学的根拠」として提唱されているのがここで紹介する「タンパク質の音楽」だ。
「生命の暗号を聴く」(2007.8.14、深川洋一著、小学館刊) 
興味をもったのでやや”理屈っぽくなる”が順を追って紹介してみよう。
ただし、最終的にこの内容を信じる信じないは個人の自由であり、決して押し付けるつもりはないので念のため!
☆ 「音楽の不思議な力の由来」について
「音楽」とは一体何か。音楽を知らない人はいないのに、言葉で説明しようとするとうまく説明できないのが音楽だ。(そもそも音符を言葉で表現するなんて、どだい無理な話だ。)
まず、音楽の起源について。
中国では音楽を意味する文字として「樂」という語が一般に用いられていた。「樂」は象形文字で、楽器とそれを載せる台の組み合わせでできている。上辺の中心文字である白という字が鼓を象(かたど)っているとすると、太鼓のような楽器を叩いて音を出したことが、音楽という概念が生まれるきっかけになったとも考えられる。
西洋に目を転じると、「音楽」に対応する英語は「ミュージック」である。その語源をたどっていくと、ギリシャ語の「ムシケー」に行き着く。
これは「ムーサの技芸」という意味で、これに対応する英単語が「ミューズ」(学芸をつかさどる女神)→「ミュージック」(ミューズの技芸)となる。因みにミューズの女神を祭った場所が、美術館や博物館を意味する「ミュージアム」である。
ミューズ(女神)は全部で9人いる。いずれも神々の頂点に立つゼウスと記憶の女神ムネモシュネとの間に生まれた娘たちである。それぞれ、天文学、喜劇、舞踊、宗教音楽、悲劇、音楽、歴史、叙事詩(2名)を担っている。
(音楽には終始優しい女性的なイメージがつきまとっているがこの辺に由来しているのかもしれない)
なお、天と地の結びつきによって生まれた女神ムネモシュネ(天空の神ウラノスと大地の女神ガイアの娘)がミューズたちの母であるというのは音楽の意味を考える意味で示唆的である。
アフリカでは「音楽は神々の言語である」と見なされているし、カトリック・キリスト教でも、「音楽は天国の言語であり、それを人間が発見して真似したのが教会音楽である」とされている。
音楽が天と地をつなぐものであれば、神秘的な力を持っているのは当然で音楽の不思議な効果は古今東西を問わず、物語の形で多数残されている。
☆ 「細胞が奏でる音楽」とは
こうした不思議な効果を持つ音楽と生物を科学的に結びつけるカギがステルンナイメール博士(素粒子論を専門とする理論物理学者)による「タンパク質の音楽」の発見である。ご承知のとおり、タンパク質は生物の身体を構成する基本材料である。細胞の中で必要に応じて必要なタンパク質が合成されるから生物は生きていける。
たとえば皮膚のコラーゲン、髪の毛や爪のケラチン、赤血球に含まれるヘモグロビン、それに血糖値を下げるインスリンなどの酵素もそうだが、これらは壊れては新たに合成されるという新陳代謝によって生まれ変わっている。
ステルンナイメール博士によるとそれぞれのタンパク質は独自のメロディを持っているという。「コラーゲン」という題名の曲、「インスリン」という題名の曲があるというのだ!それぞれの曲はDNAの中に「生命の暗号」として隠れている。
DNAが四種類の塩基からなることはよく知られている。A=アデニン、T=チミン、G=グアニン、C=シトシンである。これらの塩基が決められた順番で並ぶことで一種の「文章」が作られている。つまりDNAとは四種類のアルファベットでできた書物であり、「辞書」を作ればそれを読んで理解できるようになるはず。
ステルンナイメール博士は理論的な研究に基づき、同じDNAという書物を文章としてだけでなく音楽としても読めることを発見した。タンパク質のアミノ酸配列を解読してメロディに変換する規則を見出すとともに、そのメロディの持つ意味まで明らかにした。その規則にしたがって得られたメロディを「タンパク質の音楽」と呼ぶ。
ひとつのタンパク質には合成を盛んにするメロディと合成を抑えるメロディとがあって、それぞれ独自の非可変式チューナーがあり、そのメロディを同調させて電磁波に変換して細胞に伝えていくという。
☆ 生き物に働きかける「タンパク質の音楽」
<トマトの生育実験>
1999年ベルギー人によりトマトの成長に及ぼす効果が実験で確認された。ラジカセにより2ヶ月間、一日につき12分間、エクステンシン(成長を促進するタンパク質)、シトクロムC(光合成を促進するタンパク質)などのメロディを聞かせたところ、そうでないトマトとでは平均で高さ20cmの差が出た。
しかし、薬と同じように適量の使用を守ることが大切で、度を越して聞かせすぎるとかえって害が出たり、合わない音楽を使ったりすると逆に副作用が出る。
☆ 「タンパク質の音楽」と「人間が作曲した音楽」の関係
さて、「タンパク質の音楽」と「人間が作曲した音楽」の関係だが、具体的な曲目を明らかにして話が展開されていくが、ここではとりわけ人間にとって極めて厄介な病気「ガン」について詳述してみよう。
これまでに見つかったガン遺伝子は100個以上にのぼるが、そのうち初めて人のガン細胞から見つかったラス遺伝子が非常に有名である。このラス遺伝子は細胞の外から中へと情報が伝達されるときの中継役を担っているわけだが、各種のガンで異常が見られるケースの割合は次のとおり。
肺ガン → 30%、大腸ガン → 40%、 膵臓ガン → 80%となっており、そのほか甲状腺ガン、子宮頸ガン、造血系ガンなどにも広範に関係している。
この恐るべきラス遺伝子の働きを抑制するメロディの断片を含んでいるのがサイモン&ガーファンケルの「サウンド・オブ・サイレンス」(出だしの部分)である。
さらに、ガン細胞を殺すNK-TRタンパク質にはベートーヴェンの「第九交響曲」の合唱部分「歓喜の歌」の出だし部分とそっくりのメロディが隠されている。日本では年末に「第九」が恒例のように各地で演奏されるがこれはガンを退治する上でもまことに結構なこと。
「音楽を聴くことで癌を寄せつけない」となるとこれぐらい”いい”ことはないが~。
くどいようだがさらにガン対策を続けよう。
ガンを殺すのに重要な役割を担っているナチュラル・キラー細胞だがストレスによってその活性が低下する。そのためストレス解消を謳ったCDが市場に数多く出ている。
その中の曲目でよく用いられているのがドイツ・バロック時代の傑作パッヘルベルの「カノン」である。この曲は特にストレス軽減に良いと言われているが、効果に科学的な根拠はあるのだろうか。
94年に「カノン」その他の音楽が身体に及ぼす影響を調べる実験がアメリカで行われた。被験者は男性外科医50名、平均年齢は52歳、自己申告によると全員音楽好き。
連続して引き算をさせるというストレスを与えながら、
1 パッヘルベルの「カノン」
2 被験者が自分で択んだ曲
3 音楽なし
の3つの場合で、血圧、心拍数、皮膚の電気抵抗を調べた。
すると、1の「カノン」を聞かせたときには3の音楽なしのときと比べて明らかにストレスが減ることが分かった。この「カノン」の特徴は出だしの八つの音符にあるが、このバリエーションに関係するのがGTP分解酵素活性化タンパク質(略してGAP)の主題のメロデイである。このGAPは前述したラス遺伝子を不活性化する働きがある。
ただし、1の「カノン」より2の自分で択んだ曲を聴く方がストレスがはるかに少なくなる結果が出た。因みに好きな曲は46人がクラシック、2人がジャズ、残る2人がアイルランド民謡を択んだが、面白いことに択ばれたのはすべて異なる曲であった。
この事実から、ステルンナイメールイ博士は次のように語っている。
「ストレスといっても人によって千差万別で、自分の好きな曲を聴くのが大切である。これは人によって問題のあるタンパク質が異なっていることを意味している。
だから、聴いた人が心地よく感じる曲を分析してその人のストレスにはどのタンパク質が関っているかを知ると、より適切なストレス低減ができる。このことはストレスだけでなく、病気にも当てはまる。」
続いて、ガン遺伝子の合成を促進するメロディを含んだ歌(「キス・ミー」)を長年歌い続けたばかりに2000年に肺ガンで亡くなったフランスの歌手C・ジェローム(53歳)の実例が紹介される。彼は晩年、「この曲を歌いたくない」と言っていたが「持ち歌」だったので仕方がなかったらしい。
用心しないと「タンパク質の音楽」を不用意に聴きすぎて副作用が出たケースも沢山あるそうで、音楽は自分の好きなものだけを好きなだけ聴くことが大切で、イヤなものを強制されて聴くということがあってはならないとのことだった。(さもないとガンになってしまう可能性がある!)
以上のような内容だったが、興味のある方は原典を読むに限る。
将来、自分のいろんなタンパク質のメロディを分析することで、病気になったときに薬や手術に頼らずに症状に対応した音楽を聴くことで治ってしまう夢のような時代がいずれやってくるかもしれないと思った。
いずれにしても、聴いて快感を覚える音楽が自分のある種のタンパク質が求めている音楽であり、病気の予防・治癒にも大いに効果を発揮するに違いない。
日頃、ふと、あの曲が聴きたいなんて思うことがよくあるが、無意識のうちにDNAが要求しているのかもしれない。
「モーツァルト好きはガンにならない」という統計結果あたりが出てくれると、おおっぴらに「音楽&オーディオ」に打ち込めて「けっして無駄な投資ではない」と、カミサンへの何よりの説得力になるのだが(笑)~。