 2003年10月28日付「情宣さかた」裏版より。
2003年10月28日付「情宣さかた」裏版より。
週刊新潮が鴻池氏の女性スキャンダルを報じているのでアップします。この人のマッチョさは変わっていない(^o^)
「(長崎における幼児殺害事件の加害者の)親なんか市中引き回しのうえ、打ち首にすればいい」鴻池防災担当相
「結党五十周年を記念して、2年後に改憲案を提示する用意がある」小泉純一郎首相
「子どもを一人も作らない女性が楽しんで、年とって、税金で面倒みなさいというのはおかしいですよ」森喜朗前首相
……もののみごとな失言の嵐。しかしそれが思ったほどの反響をよばなかったのは、発言者の品性云々という以上に、受け取る側がそれを受け容れる状況になっているからではないか。
無党派と呼ばれる人たちがいる。現在の日本における最大のマジョリティだ。そのこと自体はしごくもっともなことだろう。今の政治状況に絶望しない方がむしろおかしいと私ですら思う。
けれど、この層の【自分はこういう汚い政治の世界から遊離しており、有権者として無所属であることをむしろ誇っている】(杉田敦法政大教授)現状は、やはり少し幻想にすぎないだろうか。
この十数年、日本が失政の連続であったことに異論はないと思う。しかしそれでも政権が自民党から(あの8ヶ月をのぞいて)離れなかったのは、この無党派層が、与野党を伯仲させ「ちょっと自民党をこらしめてやりました」程度のことで充足してしまったことがその背景にないか。
なんか今たくさんの地雷を踏んだ気がするけれど(笑)、たとえば、小泉純一郎を支持する方々が、今回の自民党の定年制とやらで、中曽根、宮沢元首相を引退に追い込んだことに喝采しているようだ。でも、これが旧来の派閥抗争にすぎないことに早く気づいてくれないだろうか(マスコミもちゃんと書けよな)。
※圧倒的に無策だった前首相から小泉体制になった途端、与党VS野党の構図が、自民党内の守旧派VS改革派というコップの中の嵐ににすりかわっている不思議。一連の動きが経世会つぶしでなくてなんだというのだ。
確かに政治の世界は汚いし、何より土臭い。しかしそのことに目を背けてばかりいたのでは、汚くて土臭い世界の大好きな連中のいいようにされてしまう。投票所に行こう。くどいようだが、私たちには投票というまことにスマートな手段が残されているのだ。
……今から思えば、小泉純一郎は確かに郵政改革をやりたかったのかもしれない。しかしそれ以上に、清和会支配を盤石なものにしたいという欲望の方がまさってしまったのではないか。結果として、自民党は(彼が描いたのとは違った意味で)ぶっこわれてしまったわけだが。










 2004年2月24日付「情宣さかた」裏版より。
2004年2月24日付「情宣さかた」裏版より。
 このタイトルだけで笑ってしまうあなたは麻雀の怖さを知っている人だと思う。ど素人が、へたにプロのギャンブラーの世界に足を踏み入れてはいけないことが身にしみる短篇。
このタイトルだけで笑ってしまうあなたは麻雀の怖さを知っている人だと思う。ど素人が、へたにプロのギャンブラーの世界に足を踏み入れてはいけないことが身にしみる短篇。
 ……ね?ほぼ2ページ酒田の
……ね?ほぼ2ページ酒田の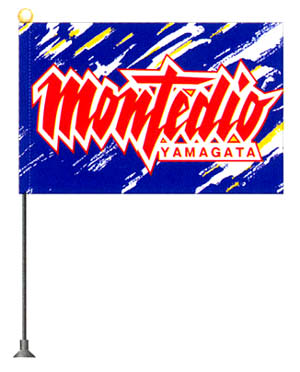 PART3は
PART3は PART2は
PART2は
 モンテディオ山形
モンテディオ山形 “みずから地雷を踏みに行くような”という表現は、わたしの知るかぎり
“みずから地雷を踏みに行くような”という表現は、わたしの知るかぎり



