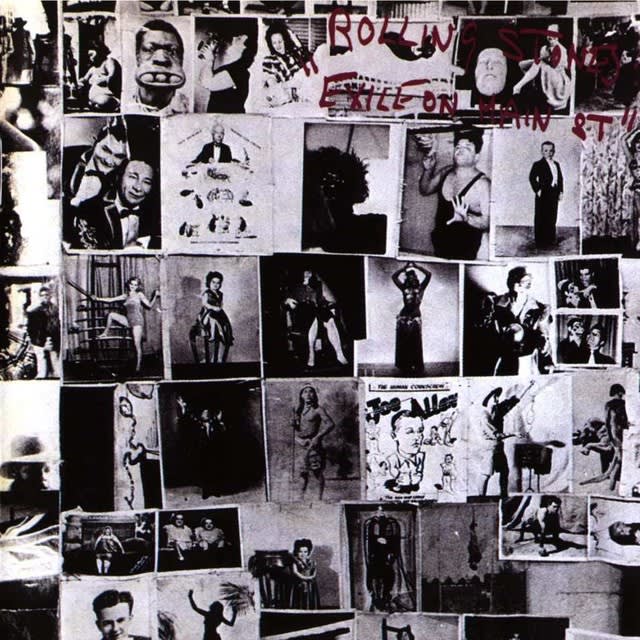「北方文学」77号が発行になりましたので、ご紹介します。先々号が338頁の超大冊になり、先号も330頁となりましたが、今号は少し落ち着いて244頁のボリュームです。新しい連載も数本あり、同人たちの意欲を感じさせるものとなっています。
巻頭を飾っているのは先号に引き続いて、館路子の詩「蛾が(記憶に)停まる、今も」。このところ動物をモチーフにした作品が続いていますが、今回は嫌いな人も多い蛾です。蛾は群がって朝に大量死を迎えたり、火に飛び込んで死んだりする習性があり、それを人間の滅亡への意志と重ねています。
大橋土百は評論「井月やーい」。長岡藩の武家の出身で、信州伊那谷に客死した俳人・井上井月の生涯をたどっています。大橋自身が伊那谷の旧宮田村出身であり、井上井月を温かく迎えた人々の末裔にあたるわけで、これを書くに誠に適任と言うべきでしょう。井月を論じて大橋の望郷の歌となっているところを、味読したいものです。
山内あゆ子訳、スティーヴン・マクドナルド作の戯曲「ノット・アバウト・ヒーローズ」の第二幕が先号に続いての掲載で、これで完結です。第一次世界大戦時のイギリスを代表する戦争詩人、シーグフリード・サスーンとウィルフレッド・オーウェンの詩を通した友情を描いた作品。二人の日記や書簡をもとに、二人の友情を克明に描きます。本邦初訳。
坪井裕俊が六年ぶりに作品を寄せています。同人の米山の小説を論じた「米山敏保論(1)―地方主義の止揚をめぐって」です。第11回新潟県同人雑誌連盟小説賞を受賞した、米山の「笹沢」をはじめ、初期の作品を中央文壇の堕落した作品と対峙させて論じています。若竹千佐子の「おらおらでひとりいぐも」などに対する批判は激烈を極めます。
評論が続きます。三番目は柴野毅実の「ヘンリー・ジェイムズの知ったこと(一)」。タイトルは今回論じている「メイジーの知ったこと」から来ています。難解で退屈と言われるヘンリー・ジェイムズの小説に、新しい視点を導入すべく奮闘しています。一回目で「メイジーの知ったこと」しか論じていないので、途方もなく長くなりそうな予感がします。
鎌田陵人の「アギーレ――回帰する神の怒り」はヴェルナー・ヘルツォーク監督の「アギーレ――神の怒り」について論じた映画論です。16世紀スペインによる南米侵略の中で、ペルー独立を宣言した狂気の人、ローペ・デ・アギーレを描いた問題作です。ベネズエラの作家オテロ・シルバの『自由の王――ローペ・デ・アギーレ』を参照しながら、最後にニーチェの「大いなる肯定」に結びつけるところが独自の視点。
昨年、玄文社からハーリー・グランヴィル=バーカーの訳述書『シェイクスピア・優秀な劇作家から偉大な劇作家へ』を上梓した、大井邦雄の次の対象はグランヴィル=バーカーの「シェイクスピア序説」シリーズの一冊「『オセロー』序説」の訳述です。これが大井が続けてきたグランヴィル=バーカー訳述の本命ということになります。今号はまだ取っかかりに過ぎません。
鈴木良一が書き継いでいる「新潟県戦後詩史」も、現在も活躍中の詩人たちが登場してきて、面白みを増しています。今号は1971年から1975年までの前半。「北方文学」の展開と吉岡又司の『北の思想』についての記述もあり、70年代前半の「北方文学」について知ることもできます。
新村苑子の「迎え火」は、 人間関係のトラブルで休職を余儀なくされている教師が、幼なじみと出かけた田舎の送り火の行事に、社会復帰のきっかけを見出すという話。たった二人の登場人物なのに、興味を最後までつないでいく手法のさえはさすが。
魚家明子の「眠りの森の子供たち(四)」がラストです。活劇的な展開が待っています。暴力沙汰あり、火事あり、新しい人物の登場もあって、波乱含みの回です。連載はあと一回で終了です。
目次を以下に掲げます。
館 路子*蛾が(記憶に)停まる、今も
米山敏保*旧街道
大橋土百*井月やーい
スティーヴン・マクドナルド・山内あゆ子焼く*ノット・アバウト・ヒ-ローズ(2)--シーグフリード・サスーンとウィルフレッド・オーウェンの友情--
坪井裕俊*米山敏保論(1)
柴野毅実*ヘンリー・ジェイムズの知ったこと(一)
鎌田陵人*アギーレ--回帰する神の怒り--
ハーリー・グランヴィル=バーカー 大井邦雄訳述*『オセロー』序説(1)/鈴木良一*新潟県戦後詩史 隣人としての詩人たち〈11〉
鎌田陵人*ミツメ「エスパー」を聴く
榎本宗俊*歌人について
新村苑子*迎え火
魚家明子*眠りの森の子供たち(四)
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。