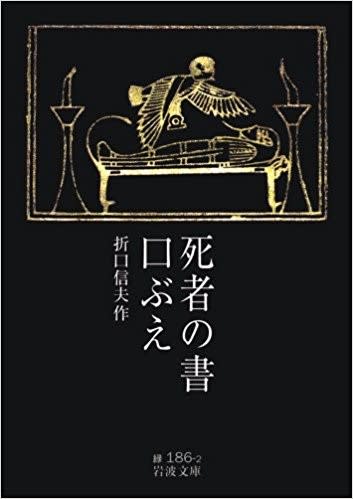それらの写真についての描写などもちろんない。ただ、そのほんの一部が伝聞の形で伝えられるのみである。「ムニョス=カノによると……」
「何枚かの写真にガルメンディア姉妹やほかの行方不明者の姿が写っているのがわかった。その多くが女性だった。写真の背景はどれもほとんど変わらなかったので、同じ場所で撮られたものだと思われた。女たちはマネキン人形のように見え、いくつかの写真では手足が切断されたばらばらのマネキン人形のようだったが、ムニョス=カノは、その三割が、スナップ写真を撮ったときにまだ生きていた可能性を否定していない。」
伝聞によってしかそれらの写真の残酷さを明らかにしないことによって、ボラーニョは大きな効果を上げている。読者の想像力に働きかけているのであり、つまり、これも黙説法の一種なのである。
『2666』においても、第二部「アマルフィターノの部」と第三部「フェイトの部」で、このような黙説法や、伝聞による仄めかし、あるいは夢の共有などによって、小説の不安を耐えがたいほどにまで高めていく手法が駆使されているが、それはこの『はるかな星』での手法の延長上にあるものに他ならない。
実際にこのような恐るべき写真展を開いた人間が、殺人の容疑で逮捕されずに済むはずがない。しかし、そうした下賤な疑問は写真展に参加したある人物の次のような言葉によって不問に付されるだろう。
「ここでは実際のところ何も起こらなかった、おわかりのように、世間一般の人々のあいだでは何も、ということだが、……」
この写真展は犯罪の証拠であるどころか、ひとつの芸術作品なのである。先のムニョス=カノという人物がそのこともまた間接的に証言している。
「展示された写真の並べ方はでたらめではなかった。ひとつの方針、ひとつの論理、(時系列に沿った、精神的な……)ひとつの物語、ひとつの構想に従っていた。天井に貼ってあるものは(ムニョス=カノによれば)地獄、空虚な地獄に似ていた。四隅に(画鋲で)貼ってあるものは、顕現(エピファニー)のように見えた。狂気の顕現。」
カルロス・ビーダーは詩人なのであった。写真展が詩として構成されていたのだとしたら、彼の殺人自体もまた行為としての詩であったのではないか(ボラーニョがそれを肯定的に見ていたのではないことは、この作品の原点が『アメリカ大陸のナチ文学』に含まれていたことから分かるのだが)。
カルロス・ビーダーはこの小説の中で2番目に登場する時に、小型飛行機で空に詩を書くパイロットとして、その姿を現すのである。ビーダーは行為としての詩を実践するパフォ-マーであったのである。
だから彼の殺人鬼としての殺人行為の動機などどこにも書かれていないし、彼が飛行機でラテン語の詩を空中に描くことになる動機もまた書かれてはいない。それらは無償の行為なのであって、ただ〝狂気の顕現〟であるだけである。
主人公カルロス・ビーダーの行為が説明され、解明されることは決してない。殺人鬼としてのビーダーと詩人としてのビーダーのあり方の関係について説明されることもないし、ビーダーが何を考えているのかについてもまったく記述はない。
つまりこの小説は、殺人事件を解明しようとする謎解きの小説なのではまったくないし、殺人鬼の心理を分析しようとする意志を持った小説でもない。それは『2666』が一見推理小説のように見えながらも、巨大な謎が解明されるどころか、かえって謎が深まって終わってしまうというところとよく似ている。
(この項おわり)